白崎 勇次郎さん
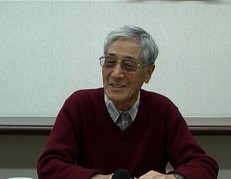
| 生年月日 | 1922(大正11)年3月5日生 |
|---|---|
| 本籍地(当時) | |
| 所属 | 陸軍 |
| 所属部隊 | 第11対空無線隊など |
| 兵科 | 通信兵 |
| 最終階級 |
軍国教育
白崎です。この話をする前に一番大切だと思うのは、軍国主義教育です。私は「これから軍国主義教育の話をします」と一度も言われたことはないが、いつの間にか大きくなったら兵隊になって天皇陛下の前で名誉の戦死をするんだと、なっちゃっていたんですよ。あの当時は毎日の生活がそれにつながっていた。私は小学校4年生の頃から、当時は「綴り方(つづりかた)」と言っていましたけど、この綴り方の時間に、今言った「大きくなったら兵隊になって天皇陛下の前で戦死するんだ」と書きましてね、それを校長先生が、「これはなかなか良いもんだから、これから白崎勇次郎君の作文を読む」と作文を読まされたことがある。それがずーっと頭の中に残っている。
当時は勉強なんかしませんで、学校が終わるとカバンを原っぱに投げ出して戦争ごっこをやるんですよ。川の畔に柳の木がありまして、その枝を適当に切って腰に差して、仲間が集まると両手に分かれて。当時、中学生とか軍隊が時々演習をやるがそれを真似していた。
本を見ると軍人のさっそうとした姿が出てくる。当時は少年倶楽部とかそういう雑誌がありましたが、必ず最初に、白い愛馬に乗った天皇陛下の姿があって、その次には中国、満州で華々しい戦功を立てたという兵士の写真が必ず載っていた。そういったものを見ているうちに知らず知らずにそういう風(軍国少年)になっちゃんたんですね。
1942(昭和17)年12月 第12航空教育隊に入隊
20才になると徴兵検査を受け、普通ならその次の年に入隊する。ところが私の場合は、4月に徴兵検査を受け、12月に教育召招集だという事で召招集された。兵隊になるのは来年の4月だろうから、あと2、3カ月はのんびりと思っていたら、12月1日に仙台の第十二航空教育隊から召集を受け、通信兵の教育を受けた。あれは通信兵が足りなくなっちゃったんですかね。
私が入隊して3か月の初年兵教育を受けた後に、私と同じ初年兵教育を受けた初年兵が入ってきた。それで同じ年に生まれたのに私が先輩になった。
私は、もともと今はNTT、昔は逓信省と言っていましたが、電信屋でした。トンツートンツーで電報を打っていた。当時は電話よりは電信のほうが早かった。電話を掛けようとすると何時間かかるかわからない。至急でも新潟から東京まで3時間4時間もかかる。電信は受けるのは瞬間的に届くけれども、配達時間がかかるので約1時間かかる。私が逓信省に入ったころは、電話よりは電信のほうが華やかだった。
私はもともと技量が優秀なほうじゃなかったけれども、軍隊では初めから習う人より、私はもう3年くらいやってましたから、とんとん拍子に進んだ。一選抜だというところまでいったんですが、ところがある日、軍隊の責任者、週番士官と言ったが、その週番士官が私のところにきて「おい白崎、今日は日曜日だから、みんなに音楽でも聞かせてやれや」と言ったので、通信兵の私は通信機(ラジオ)のダイヤルを回して面白そうな音楽を、隊内全体に流したら2~3分後に週番士官が走ってきて「こらー、白崎お前何やってんだー」デマ放送だぞと脅かされて、それから上官の覚えが悪くなった。
もう一つは入隊したとき「宗教は何だ」と聞かれ、面白半分にキリスト教会通ってたもんで「キリスト教」と書いた。(このことから)宗教はキリスト教で、アメリカの音楽なんかを流した。こいつは危険思想ではないかという事で、「こいつは前線にやっちゃえ」というんで、当時は日本の領土の最北端だった占守島といって毎日アメリカから空襲されるるところに転属になった。本来なら北海道にいて初年兵教育をやるコースだったが、そういういきさつで占守島に転属になった。カムチャッカが肉眼で見えるところだ。日本領土の最北端だ。
占守島の第11対空無線隊に配属 運のいい男
私が行ったとき、通信室はまだ地上にあった。すぐ地下に潜りましたけども、地上にあるとアンテナがあるからすぐ狙われるんですね。まず通信時は。それで敵機が近づいたという情報が入ると3人だけ残してみんな地下にもぐってしまう。私が占守島に行ってまもなく空襲を受けまして、班長なんか「白崎頼むよ」とか言われて地下に行っちゃう。残された3人は恩賜のたばこ、菊の御紋章の入った天皇からもらったタバコを1本ずつ配られて、「この空襲でもう死ぬかもしれないなー、でもこの恩賜のたばこを吸って死ぬんだからいいよなー」等と言いながら吸ってたところへに来まして。
爆弾が落ちてくると、にわか雨っていうか、サーっと音がするんですね。(その爆弾を)我々は人馬殺傷弾と言っていた。焼夷弾みたいなものに螺旋状に、日本刀の材料に使うような鋭い金属片がグルグル巻かれてる。それが部屋に飛びこむと螺旋状の弾が四方八方に飛び散る。無数の破片で、いろんな形の破片が四方八方に散るんですね。当時、私は隼戦闘機と通信をやってたが、隼の操縦士は操縦したり、銃を撃ったり、通信をしたりで、ろくな通信をやれなかった。(地上の通信士は)ずーっと聞いてないとわからないから通信機にしがみついてきいている。レシーバを掛けてるので余り音もしない。空襲はほんの数秒くらいだ。シューっと来たかと思いながら一生懸命やっている。それで静かになったと思ってみたら二人ともうつ伏せになって(戦死して)うんともすんとも何の音もしなくなっている。私はかすり傷も受けなかった。運が良かった。最初からそういう経験をした。
何度か空襲を受けて何人かが戦死したが私にはなぜか弾が当たらなかった。幸運な男だった。
占守島に行くときも輸送船に乗るが、私が甲板で外を見ていたら、船の船員さんが、そばに寄ってきて話しかけた。「兵隊さんは運が良いですよ。この船は潜水艦が攻撃しないんですよ」と言う。「どういうわけですか?」と聞いたら、「この「愛徳丸」は南方で敵の潜水艦をやっつけたことがある。ある時、潜水艦が浮上してきた。普通ならそれを見た商船は逃げるが、愛徳丸の船長は船を潜水艦に直角に乗り上げちゃった。潜水艦は上側の装備が弱いので潜水艦はそのまま沈んでしまった。それが敵さんもわかっているから、この「愛徳丸」には近づかないんですよ」との事。本当かなー。まさか商船が潜水艦をやっつけるなどという事は信じられなかった。
7から8隻の船団を組んで、真中に輸送船がいた。駆逐艦が周りにいて護衛している。7隻いて残ったのは2~3隻だった。残りは沈められた。北の海は水がか冷たいからすぐ冷凍人間になっちゃう。南方の海はフカに食われない限り2日でも3日でも泳いでいられるらしいが、北の海は心臓麻痺ですぐ死んでしまう。そういう事で輸送艦でも助かったし、爆撃でも助かった。言ってみれば幸運な男です。
ポツダム宣言受諾後にソ連軍が侵攻
占守島は、8月15日天皇がポツダム宣言受諾した日、あの後にソ連軍が来た。それが今でも癪に触ってしょうがないが、8月16日頃カムチャッカ半島から長距離砲が届く、爆弾が朝突っ込まれた。
(その時)占守島の日本軍は全然黙っていた。何もしなかった。それで向こう(ソ連軍)は日本が負けたという事を判っているんだと思い軽装備で占領しに来た。ところが占守島は北の第一線だという事で、敵が上陸しそうなところ(あまり多くはない)に大砲を設置し、照準を合わせていた。あの辺まで艦船が来たら一斉射撃しようと決めてあった。そこにのんびりしたソ連兵がきた。
「アメリカには負けたけれどもソ連には負けた覚えはない。ソ連になんか占領されてたまるか」といった気分だった。占守島は北の第一線だという覚悟はあったし、天皇は何か変なこと言ったけど、まだよくわからん、日本が負けるわけないと、そういう気持ちでいた。まず第一回目の上陸用舟艇は全部沈めた。むこう(ソ連)は、覚悟してるかと思っていたら手向かってきたという事で、ものすごく怒って、航空機からは爆弾は降るし、軍艦からは大砲の弾は来るし、目も開けられない状態、機関銃の弾が行ったり来たりだった。当時は我々は怖くてしょうがないが、古参兵は「海軍の大砲の弾なんか、(身をかがめて)低いほうにいれば向こうに行くから大丈夫なんだヨ、直撃はまずないから安心だヨ」などと言っていた。じっと(身をかがめて)大砲の音がやむのを待っていた。
大砲の弾はあたらなかったではないか? 占守島は縦25km、横10kmの小さな島なので、軍艦からの大砲の弾は素通りしたのではないか。2~3時間爆弾や大砲の攻撃があり、もう良いだろうと思って上がってきたソ連軍と相当激しい戦いとなった。私は通信兵で飛行場にいましたから、上陸したソ連兵と戦ったことはない。当時、占守島にいた第91師団の戦友会の報告によると、すごい戦いだった。
イズベスチヤ(ソ連政府が発行した新聞)によるとの、「占守島の戦いは、極東で唯一、ソ連兵の損害が日本兵の損害を上回った。戦車の数がソ連のほうが多かった。8月18日はソ連にとって悲しみの日である」と載っている。8月15日以降ですから公式な記録があるかどうかわからないが、いろんな本を読むと、占守島の日本兵の戦死者は約千名、ソ連兵の戦死は三千名と記録されている。
戦争が終わると戦場整理と言って、両方から同じくらいの兵隊を出して後片付けをやる。その後片付けをやった兵隊の話では、「ソ連が上陸した竹田浜では、ソ連兵と日本兵が重なって死んでいたよ」と報告していたので、相当激しい戦闘が行われたのではないか、と思う。
とくに上陸地点にいた戦車第十一連隊は殆ど全滅した、と言われている。その第十一連隊で生き残った兵士が新潟で本を出したと聞いたので、さっそく電話した。「第十一連隊は全滅したと聞いたが、良く生き残ったな」と言ったら、全くその通りなんだ。当時、日本の戦車は小さい戦車なんだけれども、第十一連隊は北の守りの第一線という事で相当優秀な戦車を配置していたと見えて、そこは6人乗りだと言ってましたね。日本では珍しいんではないかな。
戦車砲は飛び込むと、破片が四方八方に散らばる。戦車の中は狭いので、一発撃ち込まれたらもうだめで、みんな生き残れない。ただ運転席だけは分厚い装甲で覆われている。そのために当時運転席にいたその人は破片が分厚い装甲で止まっていて生き残った。大砲が来たなと気が付いて見てみると周りはみんな死んでいる。これじゃしょうがないという事で木陰で避難した。そうしたらその時は気が付かなかったけれどあちこちから血が出ている。休んでホッとしたら体のあちこちが痛くなった。その戦車兵はそう証言していた。
飛行機でも同じで、空中戦をやって傷ついて帰ってきて着陸するまでは、あまり痛みを感じないそうですね。ところが着陸したとたんにダメなものはそこで死んじゃう。だから着陸するまでのわずかな時間1、2分間は、操縦していて、痛みはほとんど感じないっていうんですよ。だから人間の精神力というか興奮状態だった言うか、普通では信じられないような現象が起こるもんなんですね。
聞き手:千島のアッツ島玉砕で南雲中将(正しくは山崎大佐)が亡くなったが、あの部隊か?
アッツ島奪還作戦という事で行った。だがもうアッツ島は奪還なんか出来る状況にはなかった。
聞き手:白崎さんは何年入隊ですか?
1942年(昭和17年)です。
最後の突撃
ソ連軍が上陸したのは竹田浜というところで、私は島の中央にある三好野飛行場というところにいた。ソ連軍が竹田浜に上陸してから2日位たってから、竹田浜の日本軍が全滅して、ソ連の大軍が飛行場目指して進撃中だと、そういう情報が入ったので、私はいよいよ最後だという事で本隊に電報を打った。「いよいよ最後の時が来た。これより我々は歩兵部隊に合流し最後の突撃に入る」という電報を本隊に打ち、通信所部を閉鎖し、飛行場の全面に無数にタコツボを掘ってあるのでそれに入って、ソ連の戦車が来るのを待っていた。タコツボには5、6発、火炎瓶が入っていた。私の通信隊は、本隊が北海道に引き上げていて残ったのは2個分隊だけだった。分隊長は私と同年兵で、私は兵隊、分隊長は下士官だった。分隊長は実戦の経験がなく、心配でいよいよソ連軍と戦争が始まるのにどうしたらよいかということで、前の晩は眠れなかったようだ。
私がトイレから戻った、ゴソゴソしてるので「分隊長、眠れないのか?」と聞いたら「白崎よー、明日ソ連の戦車が飛行場に入ってきたらうちの兵隊で逃げ出すやつはいないかなー」と繰り返しいう。私は「分隊長、心配するな。ソ連の戦車が来たら俺が真っ先に飛び出すから。みんな付いてくるから心配するな」と「死ぬのは分隊長が最後だからな」と「だから安心して寝ろよ」と話した。
ソ連軍の戦車がいよいよ来る。戦車は、上陸地点から飛行場までは相当な距離があるので、戦車そのものは全体が熱くなっているだろう。火炎瓶などというものは本当にお粗末なんですよ。そこにビール瓶にガソリンを詰めて新聞紙で蓋をしただけの火炎瓶を、熱くなった戦車にぶっつければ爆発するに決まっている。「とにかく火炎瓶を命中させよう」と、そういう命令だった。「どの辺まで来たら飛び出そうか」と思いながら、タコつぼに入って身を隠して戦車が来る方向を見ていた。そうしたら飛行場に突入する寸前に、もう駄目だという事になったんでしょうね、もう戦争は止めた、という停戦命令が出た。私はソ連軍の戦車にぶつからずに済んだ。どこまで運が良いのか知らないが、何回となく死ぬ目にあいながら生きてきた。
ホロムシロ王国?
私が特に言いたかったことは、私が育ったころは戦争反対とか戦争を止めようなどとは何処からも来なかった。だから大きくなったら戦争をするんだと、国を挙げての軍国主義教育の仕組みというのは、今でも系統的にしゃべれないが、兵隊が風を切って歩いていたようなことは(これからの人には)絶対にさせたくない。という想いがある。
もう一つは、第二次大戦が終わりかけたころ、エジプトのカイロで、ルーズベルト、チャーチル、スターリンが、日本が負けた時そのあとどうするかと戦後処理について話し合った(カイロ宣言)。そして、戦争は終わりにしようという話があった。世界の人々はみんなそうだと思う。
カイロ宣言で、戦争のもとになるのは一つは領土問題だ。この第二次大戦では領土を広げるという事はしない、という事を宣言した。カイロ宣言にはいろいろな学者などがいってるが、私はこの「領土を拡大しない」という一項が大変に重要だと思っている。それは日本の憲法9条の原型ではないかと思っています。それにもかかわらずソ連が攻めてきた。カイロ宣言の後のヤルタ協定で、スターリン、トルーマン、チャーチルの3人が集まって、「米軍が日本本土に上陸したら、日本兵は命知らずが多いので100万人のアメリカ兵が死ぬだろう」、という予想を立てた。それはかなわないという事で、ソ連のスターリンに向かって「早く参戦してくれ」と言った。ソ連が参戦すれば米兵は100万人も死なずに済む」と言った。
スターリンは「日ソ不可侵条約(日ソ中立条約)を結んでいる。日本とは戦争をしないという事になっている」にもかかわらずソ連は宣戦布告するという事は、それなりの代償がないとソ連国民は納得しない。ということで千島列島は日本にやる。というカイロ宣言違反の談合をヤルタ協定でやってしまった。
聞き手:ソ連軍が攻めてくるという事を認識した時の状況、わかった時の心情を詳しく願います。
私は通信兵なので、ドイツが降伏したという情報がある日受信された。その時「ドイツが負けた!」と言ったら、皆「ドイツが負けたんじゃ日本だけじゃだめだ」という雰囲気になった。そうしたら古参兵が、「ドイツと日本は国体が違う。日本は天皇が治める神の国だ。だから負けるわけがない。ドイツが負けても日本は負けない」と言った。そうしたら皆が納得した。だから、どこまでも軍国主義教育が徹底されていた。天皇が降伏宣言したが、良く聞こえず何言っているかさっぱりわかんなかった。「負けたのかい、負けそうだから最後まで頑張れと言っているのかどっちなんだ」というようなワイワイガヤガヤしていた。
聞き手:それは上官もわからなかったのか?
直後は分からなかった。そういうモヤモヤしているとき、偽情報か化もわからないが、「91師団の師団長命令で日本は降伏したと伝えられる。だけども帝国陸軍には「降伏」という二文字はない。だから本日、日本帝国から分離して【ホロムシロ王国】を建設する。ホロムシロには女性がいないから、永久に交戦することは不可能だけれども最後の一兵まで戦うんだ」という命令が出されたという情報が入った。
聞き手:それは何処からか?
何処からかわからない。うわさなのかもわからない。そうしたら皆な手をたたいて喜んだ。負けたという事でがっかりしているところに最後まで戦うんだと、それは良いやとみんな拍手。そういう状態でしたね。今から考えると信じられないでしょう皆さん。当時はそういう状況だった。
聞き手:それは白崎さんが聞いた時はどう思ったか?
そう思いましたね。だって、軍国主義教育の塊だったもの私は。だからソ連の戦車が来たら真っ先に飛び出すと、分隊長に約束したんだから。本当に来たら飛び出したと思いますよ。飛び出したらすぐ死んじゃったでしょうけれどもね。
聞き手:91師団長の命令のうわさが来たとき、日本の敗戦は(知ったか?)
天皇の放送の後ですからね。
聞き手:日本が負けたんだという事は、別の方から聞いたのか?しばらく経ってから(聞いた)?
どっちかね?と言ってるときにそういう情報が入った。「日本帝国から分離すると」いう。今考えたら荒唐無稽な話なんだが、当時は大歓迎された。「それでなきゃだめだよ。」という雰囲気だった。そのあとにソ連軍が来たもんだから、これはやられてたまるかという気持ちにつながった。それが本当に師団長命令だったのか、誰かのデマだったのか、それは確かめることはできませんでした。
聞き手:でもそれで士気が上がった?
そうですね。それは間違いないですね。ついでに言うと私は無線隊ですけれども、相手は隼戦闘機隊だったんですけれども、空中戦は相手の上に出たほうが勝ちなんだそうです。そのため隼は、上昇能力を上げるため、出来るだけ装備を軽くして紙と木でできてるような、出来るだけ軽くしてスピードが上がればいいと、ほんの一瞬でも上にいたほうがいいという事で、装備はお粗末なんですよ。アメリカの飛行機はそうではなかった。敵の機関銃が来ても跳ね返す装備は持っていたんだけれども、日本の隼は弾が当たったらおしまい。直撃を受けたら操縦士は死ぬと。そういう状態だったそうです。命を粗末にする日本軍は、今から考えるとおかしいと思いますが、当時は勝つためにはしょうがない、隼は優秀な戦闘機だと、思い込んでいた。今考えるのとは当時は逆のことを考えていた。
千島列島の占有権
さっきの領土問題ですけれども、千島列島はソ連軍の不法占拠だと今でも思っている。まだ日本とソ連は平和条約を結んでないですからね。法律上は今も戦闘状態だ。領土問題は日本の国会でも討議されたことはあった。私の遺言として伝えておきたい。
15年前、当時のロシアの大統領はエリツィンが領土問題は一気にかたずけたいと、という積極的な発言をしていたらしい。当時の日本の首相は宮沢首相で、宮沢首相とエリツィンがニューヨークで会談した際、エリツィン大統領は、北方問題について解決しようという意欲は持っていると、いう風に宮沢首相には受け取れた、ということから、日本も領土問題は早く解決しようと、いろいろ準備したみたいだ。当時は北方4島に2万5千人が・・北方4島というのは癪に障るが、択捉、国後、歯舞、積丹島に2万5千人のソ連人、今はロシア人が住んでいる。外務省を中心にその2万5千人に日本国籍を与えるためにはどうしたら良いかと、そんな話までしていた、そんな時代もあったみたいだ。当時、国会中継をテレビで放送していて私はそれを見ていた。その時、立木洋(たちき ひろし)という参議院議員がいたが、彼が「カイロ宣言で領土不拡大方針〈戦争によってその国のものにした領土は返す、平和的な話し合いでその国になったものは返す必要はない〉を決めてある。だから千島列島は「千島樺太交換条約」で千島列島は日本領、樺太はロシア領という事で話合いで決めた。「話し合いで決めた千島列島は返す必要がない」という事を立木氏が言いまして「こういうことがソ連の人に正しく伝わっていないから、ソ連の国民は千島列島を返すという事に反対という世論になっている。だから正しい情報を日本だけではなくソ連に伝える必要がある」と発言した。
この当時の外務大臣は渡辺美智雄氏。大臣は「ソ連には、ソ連に都合に良い情報が入るからソ連は千島列島を返すのに反対なんだ」と、だから「正しい情報を互いに提供しあうという話も今進んでいる」という答弁を大臣はしている。そうしたら当時の法制局長が立ち上がり、「サンフランシスコ条約で日本は千島列島を放棄した。それに調印した。だけど北方4島はもともと千島列島ではない」という発言をした。だから、北方4島は日本領だが、他は日本は放棄した。と当時の法制局長は言っていた。これに対して立木議員は「それは違う。カイロ宣言をよく読め」というやり取りをしている。
という経緯もあって、私は、千島列島は日本の領土だと思っている。これから戦争をするわけにはいかないけれども、これから平和的な話し合いで「千島列島は日本の領土だ」という考えを持っている。そうしないと千島列島で遺骨が白骨化してごろごろ転がっている。8月15日以降千島で戦死した私の戦友が安心して眠れない。そういう想いがあるから「千島は日本領である」という事をあちこちで発言しています。それが私が一番言いたいことだ。
聞き手:8月15日に残念会をやった後にソ連軍が攻めてきたという事がその時の雰囲気を教えてほしい。
あの時は大変だった。負けるはずのない日本が負けたという事で、飲めるお酒を全部飲んじゃえという事で、当時代用ガソリンというのがあったが(註:ガソリンではなくアルコールの間違い?)、ガソリンの入ったドラム缶がいっぱい並んでいる。蓋を開けて匂いをかぐと原料が分かる。リンゴで作ったガソリンが一番旨いという事で、それが入ったドラム缶を転がして兵舎まで持ってきた。それを入り口に置き水で薄めて毎日飲んだ。アルコール漬け。
聞き手:何日くらい?
ソ連が攻めてきたのが8月18日ですから2、3日ですね。空気が悪いという事で、入り口を開けた時にソ連の歩哨が歩いてきた。それが日本人そっくりで若く私の弟のような年齢だったから、思わず腕を出したところ向こうも手を出し握手した。その時相手は「グラスチ」と言ったと思った。後でロシア語に詳しい人に聞いたら「グラスチ」という言葉はないというが、私は朝の挨拶が「グラスチ」と思って、捕虜になった後で「グラスチ」「グラスチ」といって相手と仲良くなった。(くだけた「こんにちは」の意味、ズラースチーか)
その時は、もう負けたからにはもう帰れないと。ソ連に連れられて軍事基地を作る人夫にされる、工事が終わった後には、秘密を知られないために殺されるか、舌を抜かれるか、という話しがあちこちから出てきて、いずれにしてももう帰れない。と絶望的な雰囲気の中でアルコールを浴びていたという状態だった。私は内地に帰りたいという話しをあちこちでしていたけれども。
聞き手:その時、上官、将官はどうだったか?
当時、兵舎が兵隊、下士官、将校と分か別れていたため、互いに話をすることがなかった。物分かり人のいい将校もなかにはいて、共に飲んだという事は数少ないがあった。基本的には別だった。兵隊と上官が話す場はなかった。負けてもなかった。捕虜になってからも、将校大隊は将校大隊、兵隊は兵隊と別れて連れていかれた。千人に将校が1~2人だった。万国捕虜協定で「将校は働かせてはならない」となってるようだ。だから将校は働かないものだから別なところに入れられた。
カムチャッカに抑留される
一番感じたのは、当時のソ連というのは、働き具合によって糧秣が来る。100%働いた人には100%分、80%の人には80%分、60%の人には60%分、40%の人には40%分と、そういう事になっている。ところが最初は、みんな一緒でしたから炊事場も一緒なんですね。時々ソ連兵が来て、我々が飯盒ぶら下げて食料貰いにいくのを見る。それで、仕事の量、ノルマの達成度によって食料の配分が違うのにみんな一緒とはどういうことか、と将校が文句を言った。それで隊長がみんな集めて、「今日ソ連のほうからこういう風に言われた。なので明日から食料を働き具合によって糧秣を削除しなければならない」そう言ったら、当時の兵隊はまだ連帯感があったんですかね「同じ日本人が食べる量が違うというのは許せない。そんなこと言うのなら働くのを止めようじゃないか」という話しがあって皆が「そうだそうだ」と言って、働き具合によって差別するという事はできなかった。何回かソ連側が言ってきたけどもできなかった。ただ仕事の中身によって配分量を差別された。たとえば、森林組は100%、道路組は80%という風にやる。それはしょうがないですね。
最初に行ったのはカムチャッカです。占守島の海の先のカムチャッカへ行った。カムチャッカでは主に森林伐採で、それから農業。農業と言ったってない。食料は全部アメリカからの輸入品でカンヅメですね。カムチャッカ半島はソ連とは行き来できない。高い山があって越えられない。だから船で行くしかない。船で行くのは遠い。モスクワに行くなど。なので車でも何でもアメリカからの輸入品だった。食料もアメリカ製だった。ただ畑でできるものはジャガイモ、ジャガイモだけはできた。あれは短期間、2~3か月でできる。雪が解けるのが6月末で、泥んこの道路が走れるようになるのは7月半ばころ、9月には雪が降る。そういう中でできるのはジャガイモとキャベツ。その畑作業と森林伐採。
カムチャッカは占守島とは違い、風があまり吹かない。木はスラーっと長い20mくらいかな。その木を伐採し2mの丸太に切って並べて置く。一日の作業が、それの一山100本かな?。その作業が終わらないと(ソ連兵が)返さない。だが、ノコギリが変なノコギリで切れなくて、ノルマが達成できない。
作業は順当なら5時か6時には終わるが、向こうは一生懸命にやれば5時には終わるはずだと言っているがノルマが終わるまでは返さない。暗くなると仕事が危ない。伐採で木が倒れるもんだから。それで皆が「暗くなったし腹が減ったし動けない。もう仕事ができない」。みんなかたまって仕事をしなかった。すると歩哨が来て、ノコギリやナタだとか危ないものはみんな片付けて「仕事をしなけりゃ撃つぞ」と脅されたこともある。そういった点では過酷な作業だった。向こうは寒い。零下30度以下では作業中止という事になっているみたいだけれども、今日は寒いので屋外作業は中止する、という事は一回もなかった。そういうことは、関係なしに働かされた。
とにかく握っているものはみんな凍っちゃいますから、鼻も時々動かさないと凍てしまう。動いているときは何とか持つんだけれども、厚い毛皮の外套着てやってますから。休む時は木を積んで火を焚くが前は暖かいが背中は寒い。前のほうは火傷するくらい熱いが背中は寒い。ちょっと水を触ったら凍傷になっちゃう。凍傷で死んだ人もいるし寒さで死んだ人もいる。そういう意味では過酷な作業だった。
聞き手:どういう単位で?
道路作業は大人数だった。木を切るとか家を作る場合は10人とか20人だった。作業によって違う。30人という時もあった。
聞き手:収容所で生活しているのは何院ぐらい?
収容所と名のつくところは300人位居たんですかね。方々に分散していた。そこから10人とか20人が行く。いつか、30人位で伐採に行ったことがある。吹雪になると車が通れない。そうなると糧秣が届かない。吹雪の中20日位食べないことがあった。道路が通れないためしょうがない、不可抗力だ。ソ連の兵隊も歩哨も食べない。20日食べなくても人間死なないんだなと思った。やかんに雪を入れ水にし、それに岩塩を入れて飲む。それだけで20日間過ごしたことがある。腹減ったなーと思うのは2日目と3日目。それ以降になると麻痺しちゃうのかね、もうどうでもいいやという気になる。来るまで待とうという気分になった。
聞き手:その間労働は?
そりゃー出来ない。体が動かないもの。20日過ぎるとね、糧秣が来たぞーというから取りに行こうとしたら足が動かない。手で足を動かして行く。そんな状態でしたね。とにかく水だけで生きられるのだという貴重な経験をした。
樺太に移動してさらに抑留
聞き手:カムチャッカに2年、そのあとは?
カムチャッカの後は樺太です。移動するときは日本に帰るといわれた、が騙された。船で皆まとまって移動し北海道が見えるところまで来た。北海道に上陸できると思うところまで来て喜んでいたら、船がどんどん北に行っちゃう。とうとう樺太まで行っちゃった。
日本に返すといって船に乗せたのにと皆怒って、隊長のところに行って聞いてこいという事で隊長のところに行ったら、輸送司令官というのがいて「樺太の大泊まで日本兵を連れてこい、というのが私の任務だ。それ以外のことは一切知らない」と言われた。それで将校が怒って「日本に返すと約束じゃないか、お前らだましたのか」と抗議したら、「そういわないと、日本兵は暴動を起こすかもしれない。だから日本兵を大泊まで輸送するというのが私への命令だ。安全に輸送するためにそういったんだ。それ以上のことを私に聞かれても答えるわけにはいかない」そういう答弁だった。ソ連というところはひどい国だなーとその時は思いました。
樺太では途中までしか汽車が動かないんです。島の中央に道路が走っていて、一本道を三日三晩くらい歩かせられた。食べるものは当然無い。米は持っていたが水がないから炊くわけにいかなかった。二日くらい歩いたところで、へたり掛けたころに川にぶつかり、歩哨が水だっていうとそれまではくたびれてのらりくらりしていたのが皆走って、みんなしゃがみこんで水を飲んだ。夜なのでどんな水なのかわからなかったが、米をといで。朝明けてみたら泥水だった。よく泥水を飲み、ご飯炊いたりしたもんだなと思う。そういう経験もした。三日くらい歩いて、日本領だった時の国境線、真中位にあるとことまで着いた。三日くらい歩いたが、そういう意味では人間的な扱いではなかった。
樺太では私のところだけかもしれないが、当時は民家みたいなところに分宿していた。縁側に出てみると、庭に黒いのはプツプツ見える。抜こうとしたら抜けない。石炭なんですよ。石炭がちょこちょこ顔を出している。しかしそれは三菱か何かに払い下げられて、それは一般市民は取れない。三菱の許可がないと取れない。川の底も真っ黒で石炭だった。だから樺太というところは全体ではないかもしれないが石炭が露出しているところだった。その上に薄い泥があって畑が出来ている。そういう状態で、仕事は畑でした。
当時樺太に住んでいた日本人は60万人位居たという統計があるが、順番に帰っていたころだ。着いた時、部落長だか村長だか知らないがその人に連れられ、ジャガイモの供出、とにかく持っているジャガイモを出せという命令があったみたいで、集めて回ったことがある。殆どの人は出すんだけれども、中には無いという人がいる。だったら何日後に又来るからそれまで用意しておけよと、何軒かそういう家があった。部落長さんだか村長か知らないが、同じ日本人だから無いというのに出せというのを嫌がる。それで、「兵隊さん俺忙しいから残りはお前貰ってくれ」と。それでしばらく経ってから一人で回った。行くとき「いやー回ってもいいけど、無いからどうしても出せないという人はどうするんだい」と聞いたら、「その時はしょうがないよ」という事を聞いた。それで回ったら大体の人はジャガイモを出したけれども、一軒だけ「夫は兵隊に行ってまだ帰ってこない。いろんな都合で採ったジャガイモは全部金に替えた。だから無いんだ、出せないんだ」と涙出しながらいう人が一軒だけあった。私は「じゃー良いよ」といったが、そういう仕事もあったが嫌な仕事だったですね。日本人同士が「出せ、出さない」とやるんですからね。つらい仕事だった。
聞き手:その集めたジャガイモはどうするのか?
ソ連軍に渡すのかどうか、そこまでは聞いてなかった。ただ言われるままに動いていた。
1948(昭和23)年11月29日 函館に復員
聞き手:日本人はまだいたんですか?逐次、移動中だったかもしれないが。
日本人はまだ居た。乗船命令は直前にならないと出ないんですよ。何時間後に港に集まれというような命令だった。あわただしいんですよねー。作業終わって一人で歩いてきたら、荷車かリヤカーに一杯家財道具を積んで走ってくる。走ってくるんですよ。乗船命令が出たので何日まで港に行かなきゃならないんだ、と「家に沢山ごちそう作っているから言って食べな」と走りながら話をして行っちゃった。行ったら沢山ごちそうがありました。最後の晩餐なんでしょうね。私は一人で動けなくなるまで食べた。あわてて帰って行ったのでいろんなものが残っている。小学生が描いた絵とか作文が残っていた。イヤー「戦争に負けるとはこういうもんなのだと思って」おなか一杯食べたけれども何か悲しかった。
聞き手:日本への引き上げはいつごろになりましたか?
1948年11月29日。函館で復員しました。話しが断片的だが、ソ連でグループで勉強したことがある。帰るときソ連兵に目をつけられたらしく、モスクワ大学に入らないかと言われた。政治部将校というのがいて時々回ってくる。何か言いたいことはないかというので何回か質問したことがある。当時は壁新聞が流行っていてそれを書いたりしていたが、「もしモスクワ大学に入る気があるなら入学手続きを取ってあげる」と政治部将校から言われた。何人かはOK出した人がいたが、私は嘘だと思った。何度も「帰る」「帰る」と騙されたから信用できなかった。という事で私は断った。実際はモスクワまで行かないでハバロスクまで行って、そこの収容所で教育を受けたそうだ。モスクワまではいかなかった。だからソ連はあてにならないと思っていた。今もあてにならない。
聞き手:私の部隊も、シベリアに送られ鉄道建設をやらされた。私は途中ではぐれて行かなかったが聞くところによると、鉄道をひかされて過酷だったと聞いている。
作業量はソ連人に当てはめる作業量で、日本人は体力がなく、ろくな機械もなかった。だからソ連人向けのノルマは日本人は達成できない。だからノルマが達成できないから、糧秣は40%とかした。100%というのは何回もなかった。40%、60%だった。黒パンは一回で一日分くれるが腹が減っているから1日分を1回で食べてしまう。あと塩汁みたいなスープだけだから、捕虜期間中は「おなかがすいた」「おなかがすいた」で過ごした。
聞き手:カムチャッカではお風呂は入れたか?
ドラム缶で入れた。毎晩シラミだった。寒いせいか、発疹チフスとかはなかった。あまり病人はなかった。ケガで死ぬ人はいたが病気で死ぬ人はいなかった。また風邪をひかない。菌が無いから。
聞き手:ケガで死んだ人の処理はどうするのか?
穴掘って埋めるだけです。
聞き手:決められた場所に?
いやそのへんに。凍って硬いので余り掘れないし場所もできるところを掘った。個人的言えば私はだいぶ楽をしました。さっき言った「グラスチ」のおかげ。ロシア軍の捕虜の中で通訳みたいなことをやらされた。簡単な作業は手ぶり身振りで大体わかる。だから今日の作業はこれだというようなことを(通訳した)。だから重宝された。
聞き手:白崎さんは鉄条網を張った収容所には入らなかったのか?
それはなかった。逃げても食料がないのですぐ死んでしまうので脱走はなかった。ただ、捕虜が夜中にトイレに行くとき、ロシア人歩哨に言葉がわからず撃たれて死んだ人が何人かいた。歩哨はあっち行けと言っているのに、捕虜がこっち来いと言っていると勘違いして撃たれて死んだ。
聞き手:60万人のうち6万人が死んだという事になっている。実際にはもっと死んでいるけれど、記録がないし調べていないから。
カムチャッカは、夏がほんとうに少なかった。冬のほうが作業しやすい。道路に前の晩に水を撒く。そうするとカチカチに凍る、そこで脱穀などの作業をする。森林も切った木は冬のほうが、雪があるほうが運び出しやすい。だから向こうは冬のほうが作業しやすい。小さい川なんかは、柳などの木を渡して水をかけておけばコンクリートの橋になる。向こうは氷は生活するのに役に立つ。
聞き手:蚊はいなかったか?
蚊はいなかった。それだけ寒い。
体験記録
- 取材日 2006年4月22日(miniDV 60min*2)
- 動画リンク──
- 人物や情景など──
- 持ち帰った物、残された物──
- 記憶を描いた絵、地図、造形など──
- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─
参考資料
- 地図 ───
- 年表 ───
戦場体験放映保存の会 事務局
■お問い合わせはこちらへ
email: senjyou@notnet.jp
tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)
■アクセス
〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2
JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分
都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分
Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.