目次
- 加藤 與治兵衛さん
- プロフィール
- 1939(昭和14)年12月1日 歩兵第17連隊留守部隊に現役入営
- 勇ましくなければいけないと説いた母
- 1940(昭和15)年1月 山西省に着くとすぐに戦闘
- 不動、敬礼、前進。初年兵教育
- 2回目の戦闘は行きたくないと思った
- 黄河を渡った戦闘と遺体処理
- 周りはみな敵
- 歩兵の本領、工兵の役割
- 上等兵になり、初年兵教育にあたる
- 共産軍攻撃によりニューギニアに行かずに済む
- 1945(昭和20)年5月頃 特攻(ゲリラ)要員になる
- 戦後13軍司令部要員となり、秋田県の復員恩給業務を担う
- 1943(昭和18)年 独立歩兵第84大隊に転属
- 妹に婿を貰う話が出ていた
- いつ死んでもいいと覚悟したら、恐ろしくなくなった
- 食糧事情
- いつも死に水は残しておいた
- 特攻隊と、帰される命令
- 体験記録
- 参考資料
加藤 與治兵衛さん
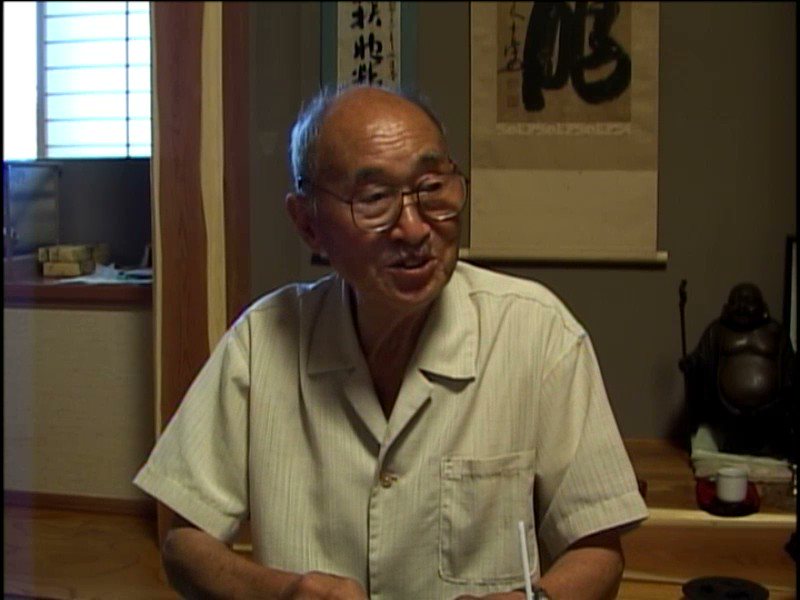
| 生年月日 | 1919(大正8)年10月27日生まれ |
|---|---|
| 本籍地(当時) | 秋田県 |
| 所属 | 陸軍 |
| 所属部隊 | 歩兵第17連隊留守部隊→歩兵第223連隊→独立歩兵第84大隊 |
| 兵科 | 歩兵 |
| 最終階級 |
プロフィール
1919(大正8)年10月27日 秋田県生まれ
1939(昭和14)年12月1日 現役兵として歩兵第17連隊留守部隊に入営
1940(昭和15)年1月 中国山西省へ 歩兵第223連隊
1943(昭和18)年 共産軍の攻撃でニューギニアに転戦できず、独立歩兵第84大隊に転属
1945(昭和20)年5月頃 特攻要員になるが、攻撃直前に負傷兵を伴って帰される
1945(昭和20)年8月末か9月 上海で13軍司令部要員に、一月後地方世話部の要員に
1946(昭和21)年1月2日 鹿児島に復員
改めて臨時召集され、秋田県の復員業務にあたる
インタビュー記録
1939(昭和14)年12月1日 歩兵第17連隊留守部隊に現役入営
私の家は10人兄弟で私一人男です。私が長男で、女9人。こういう夫婦のなかで、これ親父と母親です(写真を指す)。私、実を言うと小学校しか出ていないです。小学校は今で言えば、昔は高等科に歩く人もいたんだけれど。私の家は少し言い過ぎかもしれんけれども、先祖から聞いた事を言えば男鹿地域で古いほうでだいたい五本指ぐらいに入ってる。地元で一番古いと言われて與治兵衛、與治兵衛どんと言われた。約400年。本明寺というお寺があるんですよ。その本明寺の改築があって、本明寺を作った。400年記念祭が平成17年だから、7年前にあった。私の家もすぐそばで同じく400年だから、寺の改築で各世帯の過去帳が全部ありまして、それ が立証されました。
小学校に、姉が1人いるんです。母が暮らしてきた家に、(同席者:暮らした家から暮らした家に嫁いでくる、田舎はみな。)その姉は小学校高等科まで行って、昔は養蚕学校という学校があって、そこに入ってそこに入ってるうちにね、私の家との関係があって、私の家に嫁に来てるわけですよ。18歳ぐらいですから、17歳かな。私は19歳で生まれた。18歳で私の姉が生まれた。
俺の姉が学校の先生してるんですよ。昔はちょっと女学校一つ出れば、姉が学校の先生。それは私がどこにも歩いてない(学校に行ってない)。俺、学校歩かせればすぐにいなくなる。男の子だし一人っ子だから・・・歩かせられない。うちの親父が口にしてきて歩かせない。それからその下がね、今に思えば原因がここにあるんじゃないかと、私の二つ下、チエと言って書いたものあるけど。これが昭和12年から13年。13年だ、日本に一つしかない大阪の造幣局ね、造幣局に勤務している。やっぱり昔の女学校終わってね。そして造幣局は日本に一つしかないけど、秋田に支店があって、造幣局の。
秋田の茶町に造幣局の支店があった(注:秋田市茶町菊ノ丁にあった造幣局秋田出張所のこと)。秋田の支店に入ったんだけど、本庁に来てくれということでそっちに取られた。俺が軍隊に入る前だから、13年。この妹がチエというんだが、次女。その次の年14年の12月1日、秋田の17連隊に入った。
聞き手:歩兵17連隊?
17連隊だけれど、当時17連隊は本隊が満州に行ってしまっていた。私は留守隊に入った。証拠はあるんだけど、探しても急に、夜中にうちの息子も、2日間・・・・・・・昭和14年12月1日に留守隊に入って、1ヶ月間教育を受け、すぐ戦地。昭和14年12月29日か30日に出発して、確か広島から中国に出発した。
聞き手:その当時すると年齢的には?
その当時私は21歳。20歳で検査して21歳で入った。
聞き手:20歳で徴兵検査、甲種合格でいらっしゃって?
甲種合格。当時50人くらい同級生がいたけれど、私ら早生まれなのかな、同級生で半分くらいは徴兵検査をしないわけです。同級生では徴兵検査で私とシモマツネジという2人だけが合格した。そして私よりも1年先輩であった別家の加藤清治ていうのが、同じ部隊に3人、12月1日に入った。シモマツネジは丈夫な男だが、頭は私よりも少し悪い方だった。それがね、すぐ即日帰郷させられた。
聞き手:即日勤務?
即日帰郷。家に帰れと。シモマツネジはいかない。
それで3人一緒に入ったけれども、歓呼の声に送られて入ったんだ、そしてシモマツネジが私が代表して挨拶すると言ってね。これが色々あって、面白いんですよ。加藤清治、別家の旦那、これが三番目が二番目か、せいじ、清い治めるね。これで同じに入ってそれはずっと一等兵になるまで約1年くらい一緒だった。彼があのいわゆる病名を言えば痔。痔で入隊してからほとんど戦をしないで入院生活。私のことを力にして、本気なもんだから。彼は次男、私は長男なもんだから、私より1年先輩だけれど、私のことを力にしようとして。彼は学校の成績が悪かったかもしれないけど、あの長い軍人勅諭を全部暗記していた。彼は次男坊だから兵隊で暮らそうとして、あの長いの、約30分以上かかります。全部暗記していて、大したものだなと思って。
軍隊入ったら、軍人勅諭をしっかり暗記していないといけないと。それで彼がね、あれは暗記してるのよ。清治に俺も負けてられない思って俺一生懸命勉強したが、なかなか半分ぐらいまでしか分からなかった。とうとう1年くらいしてから今度俺もようやく、その30分の軍人勅諭全部わかった。ようやく、苦労した頭も学歴もない。そしたらね(彼の入院した所は)10里くらい離れているんですよ。手紙が来て入院しているというんで、加藤清治の面会に行った。そしたらよくないけどこんなもんだと、さかさまになって。男同士だけど、尻を人に見せるのはよほど恥ずかしいこと。今でもなんともないけども、あの時代はね。さかさまになってこういうもんだと尻を、俺は大丈夫だってわからないです。そうして面会に行ってきた。 そしたらまもなく1、2か月のうちに彼が急に亡くなった。その病院で亡くなったの、中国の。加藤清治ですよ。分家の。その夜に、いわゆる魂で来たの。夜中に目が覚めたら、夢で俺のこと起こして、俺起きて目覚めたら気持ち悪くてね。起きてね。ちょっとその外の方向に回って。そして寝たことある。そのまま加藤清治は死んでしまった。
勇ましくなければいけないと説いた母
うちの母は実際偉かったと思う。というのはこう言った。私が兵隊に行くという時、女の中に生まれた一人の男の子だから、行くときに涙をこぼしたり、後ろを見たりってことを心配したんじゃないの。うちの母がね「男の子というものはな、勇ましくなければいけないよ。日露戦争、日清戦争、満州事変、支那事変、いろいろのことがあったんだ。男で兵隊に行くっていうのは誇りであると。私の兄弟を見なさい。男の子が4人いるけれども。1人は目が悪くて不合格だが、海軍2名、陸軍1名。みんな勇ましく行ってきたと。行く時に後ろを見たり、涙をこぼしたりしているような男は男じゃないと。男の子は勇ましくなければダメだって、こういうお母さん、うちの母が。自分の母のこと言うのは悪いけれども、一般的に素晴らしい能力であったってことは、男と一緒に高等2年まで歩いた。成績2番であったという。
それで兵隊に入った時に、母がもう一つ言ったことは、戦が終わったら、日清、日露戦争で女の人はね、従軍看護婦というものがあって赤十字に入った。そこにね赤十字の非常に内容の良い歌あるんだね。その歌をね、自分で歌ってね。そうして、こうして勇ましく行ったもんだって。そういうもんだば、俺もどうせ死ぬ時は死なねばなんだいんだったら勇ましく死にましょうと。母親の言うこと聞いて、そのおかげで後で言うけれど全てを恵まれて、能力がない。学歴も力もない、何もないけれども、まず恵まれた。
県庁においても、県庁を辞めるまでの間、ずっとこう考えてみれば48年間公務員。戦場生活6年。その戦場生活、後で話したいけれども、軍人というものはね、どこでも同じだと思う。そのみんな平等でない。良い人と悪い人もいる。例えば中国に行った時、何でとかというと、おそらく私ほどの苦労した人はいないと思う。と言うのは。第一線に出た。上陸するときは攻撃すればあのいいの。攻撃する時はね、中国の当時の長というのは、日本の教育を受けてた。台湾総統の蒋介石。彼は日本の軍隊の教育を受けて、互いにね。
1940(昭和15)年1月 山西省に着くとすぐに戦闘
俺は12月1日に入って、12月の末に広島から立って、向こう(中国) 着いたのは21年(昭和15年の間違い)の1月の2日か3日に着いているですよ。1週間かかっている船で。そしたらね、まっすぐにどこ行ったかというと、その当時最初の人までは上海、ウースンという所に上陸して。その頃はもう上海とか天津とか奉天とか、日本よりまだまだ良くて、恵まれて平和で、しかも日本人と顔まで同じで、朝鮮はちょっと違う、朝鮮ははちょっと顔がなんとなく変わってる。服装も変わってるしね。すべて変わっている。
そういう状況で、私が向こうに着いて1週間くらいかな、現地に着いた。疲れて疲れて、ようやく着いて、脱いで。そうしたらね、私の兵舎の真向かい、そこに見えるんだ。1里先4キロだね敵が。それが蒋介石軍、これが中国の本当の軍隊だ。これが強いんだよ。日本の教育受けているから。日本の教育はドイツの教育を受けている。海軍はイギリスの教育を受けている。そういうことで日本の教育を受けた蒋介石軍が強くてね。山の上に200人ぐらいか300人くらい上がったの。そしたら先輩が「あれは中国の軍隊だ、あっ、来たな」こう言った。「我が中隊は直ちに攻撃しよう」とことになった。
同席者:昭和15年?
まだ初年兵の、1週間の着いて間もなくの時。そしたらね、敵が上ったから、その時班長がこう言った。「初年兵はどうする?初年兵は優秀なものは連れていく、優秀でないものは連れていかれない」と。いやー優秀になりたい、俺も上等兵になりたい。とこう思った。私の先輩が、私より3つか4つ上の、満州事変、支那事変に言った先輩方。安藤マサジ、藤井、優秀なものが4、5人。児玉マサノスケ、これらは上等兵になった。その時、上等兵になって星3つ付けて帰って来ると、星3つ付けて除隊してくる。これまもう大威張りしてくるほどに徽章つけて、女の人はもう上等兵になってきた人は神様のようになって最高の立派な人に見えたんじゃないかな。それを私、見ているもんだから俺も上等兵になりたいと思って、死んでもいいから上等兵になりたいと張り切っていた。
俺も上等兵になりたいということで、結果的には全員一致で行った。そうしたらその日は恐ろしい戦になった。今までいろいろあったけれど、これほど恐ろしいことはなかった。その日は一晩中、ここに山がある、我々はここ、敵はここに来ている。(手で状況を示す)、この間50mか70m、手榴弾を敵にぶつけると後ろに落ちる。我々のが敵に、敵のが後ろに落ちる「ボン、ボン」と後ろで破裂する。そのくらい近い。最初は山の上から撃ち合っているわけ、我々は下の方から。その日は一晩中、眠らないで戦をした。弾が撃つと真っ赤になって飛んでくる。「シュートと」(手で状況を示す)、機関銃の音「パンパンパンと」頭の上とか、耳の上とか「シュー、シュー」と。前に落ちると火が「ポオッ、ポオッ」と上がるの。それでも、おっかないと思わなかった。上等兵になることだけ考え、張り切っていた。うちの母に「勇ましくなければいけない。卑怯な真似をして死ねば、遺骨は荒縄をつけられて帰ってきてみんなに恥ずかしい、家族に恥ずかしい思いをさせる」母にそう言われた。卑怯な真似をして死ぬと荒縄をつけられたら大変だと思って、戦死してもよいと思った。
そうしたら一晩中「パーン」と火が出るわけです。弾が当たれば単独の場合は、人に弾が当たれば体の中に入っていく。弾道は真っ直ぐに来るのではなく、必ず弧を描いてくる。だから夜の鉄砲というのはなかなか当たることは無い。100発で1発当たるかどうか。闇夜の鉄砲というのは何もおっかなくない。でも、昼はある程度おっかないけれど、ある程度弾道があるから、弾というのは簡単に当たらない。近くで撃てば別よ。50や100m以内であればやっぱり当たる。100m以上離れた場合、弾は2キロか3キロ飛ぶけれど、弾道があって弾はほとんど当たらない。当たっても弾力がないから体の中まで貫通しない。
だけど、初めての夜(の闘い)だから恐ろしい。弾が赤くなって飛んでくる、「ダダダ」と音はする、前には落ちる、後ろにも落ちる、耳の両側に弾が行く、手榴弾投げても、敵の手榴弾か後ろで破裂するし、どういう風に投げたら敵に届くのか、さあ突撃だ、白兵戦で突っ込んでいくが、中国の蒋介石軍も突っ込んでくる。こっちも行くけど、白兵戦。それでも最後は日本が強くて勝つんだが、それで12人死んだ、その日。そして我々が攻撃していった。そしたら
逃げていったから敵を追って行った。ずっと10日ぐらい追っかけて行った、遠くまで。そうしたらずっと逃げる。帰ってきたら我が方の味方も12人くらいが死んでいた。敵の方は20人も死んでいる。もっと多かったかもしれない。
そして死んだ人を運んで、死体を並べておいて、夜は歩哨につかなければならない。その気持ちが悪いこと。死んだ人の、同僚の死んだ者を並べておいて歩哨は二人だが、同じところに立つわけではなくて、一人ずつ入口と死体のそばに立つ。戦が終わったせいか、死体を見れば気持ちが悪いの。やっているときは緊張しているからそういう(ことは無いんだが)。それはそうして終わった。そうしたら班長が「今年の初年兵は難儀したな。今まで戦は何度もあるんだけれど、今度の戦は恐ろしい、大きな戦であった」と言った。「恐ろしかったな」と(自分も思った。)
その後、我々が行ったところは山西省、閻錫山(エンシャクザン)という殿様がいた。蒋介石のような能力のある人物。河南省とか河北省とか、徐州、蘇州、杭州などは日本の東京みたいな気候は良い、開けていて、日本の流行歌を歌いながら、楽園というような、これが戦場か戦をしているのか(というような状況だった)。ところが、山西省に入ると毎日敵の真ん中にいる状況だった。
閻錫山はモンロー主義ってね。モンロー主義を唱えた。自分の州、山西省は自分の国だと。モンロー主義で、敵は絶対入れない。他にも行かない。それだから閻錫山が強くて、なかなか逃げない。そしてそこは山奥で、山西省も広いとこだから、下は川が流れているので降りると、上るのに1日かかる。至る所こういう地形で、ずっと降りて川を渡る。まずこういう土地あるものかと思う。こうしてみればすぐ近く(に見えるんだが)、降りて行って上がると言えば1日かかる。
ご承知と思いますが、中国では揚子江と黒竜江(黄河の間違いか)の二つの大きな河でね、私は揚子江は北の方、満州の方だから行ってないけれど、黄河の方にはずっといた。ここで戦死したアキモトでもタカクの親爺でも、入ってすぐ死んでいる。タカクの親爺は・・・・・・相撲は強いし、あの性格が違うんだもん。あの人恐れない方だったから、相撲は強かったし。弾が当たってすぐ死んだ。(自分の頭に指を当てる)
同席者:そういう強気の人だから、もうやってしまえと
死んだ、先週死んだと聞きながら、私もそこさ行ったもんだから。山西省に行って戦死した人はかなりいる。俺の別家でもトクゾウも山西省、山西省では日本の犠牲者が非常に多いはず。南京とか北京とかはまるでのどかな所で、食うものは日本から来るし、土地からは何でも没収し、獲るから好きなようにやれた。
不動、敬礼、前進。初年兵教育
聞き手:その年は昭和15年ですか?
私行った時は昭和15年の1月からその戦場で、ずっと帰るまで21年、いや昭和20年の8月まで、そういう事はまだまだあるからあとで話しましょう。
聞き手:普通、最初三か月ぐらい初年兵の教育とかあるのが、全然ないままにもういきなり戦闘に入って、山西省に送られる形になってしまったんですか?
聞き手:14年入隊?
はいはい。そして12月1日に
聞き手:15年の1月には中国、中国に広島からですよね。だからそういう訓練がそういうのが無くていきなり中国の本土に渡った。そういうことですね。
内地で1ヶ月居たわけです。これは不動の姿勢と三つ、敬礼、それから行進、前進、これ基礎教育。「何でも従います」と敬礼すること、毎日不動の姿勢で、動かない。「気を付け」と言われて絶対動かないのが不動の姿勢。基本姿勢。敬礼というのは「あなたの言うことは火の中、水の中何でも聞きます」とこの印が敬礼、上官に出会えば敬礼、又敬礼。これは陸軍だけで海軍は1日に1回こうする(右手を顔の前に持ってきて立てる姿勢をする)、敬礼(右手を耳の横に持っていき斜めにする姿勢をする)はやらない。陸軍礼式と海軍礼式は違う。陸軍は今ここでやったのを、又こっちくれば(敬礼)をやらなければならない。「いつでも火の中、水の中、あなたのおっしゃるとおりに従います」と。それが陸軍礼式の不動の姿勢と敬礼、前進はね「進め」と言われたら、何かぶつかっても、火の中、水の中、ぶつかってもその場で「止まれ」と言われるまで、こうやっている。(足踏みの姿勢をする)そういう指導なの。それが基礎教育。
聞き手:それを1ヶ月受けて、軍事訓練はされなかったのですか?
今度、軍事教練、
聞き手:それは入れて一ヶ月?
それはいれない。不動の姿勢だけ。
聞き手:すると上陸して、中国が上陸してから軍事訓練?
そう、本当の戦の教育。今度は鉄砲の撃ち方、寝て撃つ、膝撃ち、立ち撃ち、中国本土に行ってから。その教育が6ヶ月間。(軍隊に)入れば二等兵、星一つ。6ヶ月過ぎれば一等兵、一等兵になれば、次は古兵。そして1年過ぎると、初年兵入ってくる。これで、古兵となる。これがここの使い方(自分の胸のあたりを指して)で、自分が気にいらなければ初年兵を叩くわけ。自分がそういう目に合っていながら、自分が古兵になればやるんだもの。筋の悪い奴は。
聞き手:古兵が全員というわけではなくて?
悪い人。ちょうど今の舅と嫁みたいなもんで、嫁が何すれば、自分もあれだったから認めてやればいいのに、自分が苦労したような嫁としても同じことを繰り返しているようなもんでね。悪質なものは叩くことを楽しみにしている古兵がいる。いくらいても一等兵だもの。帰るまで、1年間、2年間居ても一等兵だもの。上等兵にならないで帰ってくる人が大部分だ。上等兵になるには仮に50人いれば、10人か15人くらいかな。6ヶ月ごとで進級するから、3人とか5人ずつなるわけ。最後までなれないものは帰ってきても一等兵のまま。二つ星のわけ。そういうのはいらないと言う人もいるけれど、上等兵で帰ってくれば、星三つ付けて、
聞き手:同席者:星三つ付けて帰れば誉になるからな。
2回目の戦闘は行きたくないと思った
そうそう。それで私はさっきの(戦が)終わってからね、1ヶ月足らずのうちにまた敵が来たと言う。今度は別のところに。そしたら、又行こうとしたの。いやーという(感じだった。)
聞き手:その時も山西省ですか?
そう山西省です。同じ山西省でも広いんだから、省が大きいから。こんどまた攻撃行こうと。「いやー」とあの思い、1週間敵を追って行って、叩くだけ叩いて、突撃もして、鉄砲や手榴弾やったでしょう。それ思い出すと、その時の本当の思いは「手とか足とかに弾が当たってくれればいいな。負傷すれば内地に帰れるな」と本当そう思ったんだって。上等兵はいらないと。
聞き手:最初は母親には上等兵になると言っていたが?
そうそう。それまで母親の言っていたことを死ぬ気になって守ってきたんだけど。だからよかった。1ヶ月くらいしたらまた(戦に)行くと言われたでしょう。いやー行きたくないと思ったんだけど、行かないわけにはいかないでしょう。
聞き手:現実を最初に見てしまったから2回目はそう思ったんですね?
正直言うとそういう気持ち、死にたくないから手か足に弾が当たって、負傷してくればいいなーと、内地に帰れるなーとこう思った。それでもなかなか、手とか当たるわけにはいかない、(額を指して)当たれば死ぬし。しかも死んだのが良い場所の場合はいいけれど、死体を持ってこれるけれど、敵を攻撃していて、なんともならないような作戦となれば、二ヶ月後三ヶ月も(敵を)追っかけていくわけだから、そうするとね倒れたものは置きっぱなしなの。穴を掘って埋めてきて。かわいそうだよね。遺骨も何も持ってきてないんだ。
黄河を渡った戦闘と遺体処理
それから後の話をすれば、黄河の話をしたいんですが、黄河を渡って敵を攻撃したわけです。やっと敵の山に上がって。敵とにらみ合った、1ヶ月以上も頑張ったが、敵も下がらない。そしたらね、ちょうど4月29日だと思うが、天長節だったから。その時に1週間ぐらい雨が降った。山地域にいる時、敵も逃げない、こっちも攻撃できない。
聞き手:同席者:にらみ合いになったわけですね。
そしたらしたら晩方になって、背嚢とか何とか、完全軍装すれば、背嚢には食う物とか武器弾薬、それから着るもの、雨降った場合のテントとか外套とかあるじゃないですか、完全軍装すれば13貫くらいある。米一俵16貫、13貫ぐらいの装備で、腰には弾をつける(腰の部分を手で示す)弾薬。刀も下げてる。そして鉄砲(全部で)13貫くらい、13貫目を背負って、立って歩いて、そうして戦をするんだよ。その装備をちょっと脱いで下ろして、そして背嚢を下ろして、敵を攻撃する。今思って見ればよくやったもんだなと思うけれど、軍は行軍して行くけど、一部の者は残ってその背嚢を二つか三つ背負わなければならない。負傷者もいれば、それから負傷しない人たちで持たない人もいるでしょう。ものを持たないで敵を追いかけていく人もいる。
そうすると、いかにして日本の軍装というか、背嚢とか食い物とか米とかみんなあるんだから、ずっと行軍していくんだから、米を炊く飯盒とかも。そうすると、そういうものを負って行ったら敵さぶつかったわけだ。敵が後ろから、黄河を渡って敵の陣地に着いたら、1週間も雨が降っているので、敵が後ろ回って我々が上がっていく1個中隊、300人くらいが、ぐるっと包囲された。逆に、追いかけていったら、逆に敵に包囲された。敵は自分の地形が判るでしょう。後ろから回ってきた。その上がってきた時に応戦はしたものの、白兵戦、我々もみんな脱いで。なんせ、敵が大量に来ているものだから、逃げることも大事だから。一回だけ逃げた。逃げるが先みたいなもんで。空手で逃げるわけにはいかない。背負ったものは置いて行ったが、鉄砲は離さなかった。
聞き手:同席者:自分を守るためにも
そうして、逃げた。やっとそこから逃げた。晩方だからよかった。見えないから。日が暮れてきていたから。それでも追っかけてきていた。我々はしゃにむに逃げた。その時の記憶で15人くらいが殺られた。それは置きっぱなしできた。我々もしばらくして我々も、元のところに帰って、もう一度あそこを攻撃しようと、そうしたら宮下曹長というのは、立派な男らしい男だったが、宮下ミノルという人だが、この宮下曹長以下15名くらいが敵に刺されて死んだ。それを置いてきた。それを1週間ぐらいして我々が再攻撃して、あそこを奪還しようと、又(攻めて)行った。
そうしたら穴を掘って、綺麗に着てるもの全部脱がして丸裸にして、15人の人を全部埋めてあるの。綺麗に並ばせて、砂をかけて埋めてある。そして、日本軍官兵の墓と書いて、「官は官、郷土の兵隊と言う意味」で、日本軍官兵の墓と書く。そうして、ちゃんとした死亡処理をしてある。それで、俺が見てきた。クドウマイというが、直ちにこのものを全部掘り上げて、片方の腕で良いから全部腕を取って、それを15人の名前を書いて、これを付近から火葬する木材、竹などを集めて、これ焼いて、そして遺骨にして俺のところに持ってこいっていう。俺の1個分隊そっくり(全部)、そしてほかの物は、背嚢とか残ってるものは全部、附近の住民を徴発して、背負わせてついて来いと言う。もう可能性があるとかないとかでなく、とにかく命令なの。「ハイ」と言わなければならない。できるできない時は別だ。
それで、私は官兵の腕を切って、腕を落としてきた。刀で切って、そして腕に名前をつけて、そして並べて、焼いて、腕だけだからそんなに時間がかからない。建物で素晴らしい廟というのがあって、所々にある。その廟を壊して材料を持ってきて、焼いて、それを背嚢に背負って持ち歩いた。
聞き手:同席者:15人分ですか?
本隊は前の方にどんどん進んでいる。どうして行ったか、どこに行ったか分からない。(それをやったのは)一人ではなく、俺の分隊、1個分隊14、15人。ニコというのは、「ニ(你)」というのは相手のことを言う。「ニー」というのはお前という意味。日本語では君とかあなたとか、「オー」というのは自分のこと。「オー」は我。「オーメイ」とはお前たちということ。背負ったまま何日か戦をして、そして(死亡)診断書を送った。届けた。それからは、上海の方へ送られていく。そして日本へ、内地に送られる。名札がついたままで。(腕に触る)
宮下曹長以下、今は一人一人名前はわからなくなったが、宮下曹長はしっかりした、いい男で私のこともよく面倒を見てくれた。私はそのころ伍長か軍曹になっていたから、そして部下も14、15人いたから。
周りはみな敵
(手で山を指しながら)寒風山(男鹿の山)のようなあんなところに1個分隊が上がっていると、その付近に鉄条網をはっている。そうしたら下に、イワクラとかハヤサカとかオオクラ、マエダ、イノボリ、アキモト、タニザワ、モモザワ、ハダチとかあるでしょう。こういうものは皆敵ですよ。
表面は日本人でも偉い人は、大人(タイジン)、大きな人ということで、先生ということはシーサンという。シーサン、シーサンという。大人は最高の人ということ。
聞き手:同席者:尊敬すると言う意味で大人ですよね。
そういうこと。言ってるけど表面であって、内心は、(日本軍は)なんで人の国に来て、我々を追っ払って、自分たちは良い思いをしている。内心は、面白くない気持ち。
同席者:腹の中は違うと。
それで、夜中などは攻撃してくる。夜中に、寒風山みたいなところに我々の分哨に。
同席者:分哨で対峙していれば、日中は普通の農民だが、夜になれば兵隊さんになると言うことですよね。
そうそう
聞き手:同席者:いわゆる軍服を着ていないから、わからないんだよね。
そう、わからない。
聞き手:取材者:蒋介石軍でなく、八路軍ですか?
それがね、八路軍は「戦は勝つためにある、負けるための戦はするな」というのが八路軍の教え、毛沢東の。
聞き手:同席者:今の話は八路軍でしょう。
いままで(さきほど)の話は蒋介石軍だ。日本軍は蒋介石軍と戦をするのが建前にある。だけどあの国は八路軍と蒋介石軍、各州、省におる将軍など殿様がいっぱいいるわけで、日本だってもともとから言えばそうだった。
われわれ下の方の者は、「まつろはぬ者ども」で、「討ち平け給ひ」で、軍人勅諭にあるんですかな。南の方、あるいは島根県とか、京都、東京は誰が中心で、四国、九州、東北のものは・・・、自分所のものしか・・・・。田村麻呂という将軍が、東北征伐をやったんだけど、そういういきさつがある。
これ(後ろにある本を持って)素晴らしいこと書いてあるけれど、本物を見れば、いやー戦というものは、後から質問が出ると思うけど、誰が死ぬんであれ、いーということは一人もいない。みんなあっては困るし、無い様にしてもらいたい。誰も死にたい人がいるはずはない。しかし(死にたい人は)いないのに、なぜ戦をやるかというと、日本が戦に負けたと言うのは、これからは科学兵器と物量、日本の飛行機100台とか50台とかではなく何百台という、1キロとか、1キロは大したことが無い、1里は4キロだね、8キロも10キロぐらい並んでいてブーンとやってくる。そしてブーブーと落とす。(手で動作する)そして、1つが2つ、2つが4つ、4つが8つ、8つが16と、そして最後に「ボーン、ボーン」と屋根の上からみんな落とされる、そういうことで物量のアメリカに日本は絶対に勝つ見込みはない、南方の方の話を聞くと一番よくわかる
歩兵の本領、工兵の役割
聞き手:本当の戦闘行為を経験なさっているから、こう包囲されたら、やはりきちんと逃げるとか、そういうそれも作戦のうちのですものね。
だから、八路軍のね、兵法というのは戦は勝つためにやるのであり、負けるためにやるのではないと言うのがある。だから我々有利だったらおおいに攻撃しろ、不利だったらしっかり戻れと。不利になったら、ゼロになれと。有利になったら攻撃しろというのが八路軍の兵法。
聞き手:じゃあ一番困ったというか、あの日中は普通の中国人で、夜なれば攻めてくるじゃないか。すると加藤先生も兵隊さんに上官でいて、やっぱり日中は仲良しこよしみたいな顔をしてる中国人。夜になれば、この攻撃してくるすね。
そういうことだ。有利な時は攻撃し、不利になれば逃げるそれが八路軍。それが八路軍の戦法。日本は、絶対敵に後ろを見せてはいけないという。日本には騎兵と言うのがあるでしょ。騎兵は馬に乗って(馬に乗る格好をする)、役に立たない。刀下げてチャンチャンバラバラ、馬に乗ってエイ、ヤー、ヤーとやるんですよね。そんな戦は戦にならない。私が(軍隊に)入った時に騎兵は廃止。
聞き手:あれは戦国時代の戦いで、鉄砲が無くて、
それからもう一つはね。それが騎兵廃止の原因。騎兵が無くなった。我々が歩兵というのはね。歩くのだから、もう白兵戦。組み合い、突き殺すまで。最後まで、勝利を土地を占領するのも歩兵。勝敗を決めるのも歩兵。歩兵の任務は非常に重いということが、「歩兵の本領」というものにちゃんとあるわけですよ。それで我々その歩兵であったけれども。その中にね、俺が後で話したいと思ったんだが、シンジに発生するあそこ黄河を渡って、敵に突っ込もうとした時、黄河をどうして渡るかと思っていたの。そしたら工兵というのがあるでしょう。工兵の任務の重さと言うのをつくづく感じた。
我々が行軍して、もちろん夜ですよ。黄河がこう流れてる。(手でかっこうする)我々よりも1週間前からここに行って、この黄河に船を両側から真ん中に縄をつけて流れていかないように停めて、その船をやるために板でもなんでも、我々が(渡る)時には下のある所は肩で担いでいる。
聞き手:河の中で?
河の中で、深い所は船、船の下に板を渡し、板が外れないようにして、それも敵が向こう側にいるんですよ。それがね、夜だからいいの。夜暗いから。暗いからといっても、我々歩兵は動けるから、気まぐれができる。隠れることができるんですね。この工兵の方々は、船を動かさないようにしている、捕まえている。(縄で)締めるところは締めているんだが、黄河の流れがあるでしょう。そうしたら動くでしょう。そして我々がそこを渡っていくんだもの。夜中に。敵はダダダ―と撃つが、夜だから当たらないんだ。それがおっかねんんだやっぱり。夜だから。当たらないと言うことはわかっていながら、夜襲っていうのは本当に恐ろしい。でも、当たらないんだ。でも怖い。この夜襲っていうのはね。本当に恐ろしいのが銃火の攻撃ですよ。近い場合。銃火の場合、鉄砲のね。刀でのヤーヤーというのはとても戦にはならない。げんこつで闘う方がずっといい。
聞き手:やっぱ近距離の戦いっていうのは本当に怖いでしょうね。
上等兵になり、初年兵教育にあたる
だから、そういう戦の要点だけは本当にちょっと言ったけれども、6年のうちほとんどは、私はいいことでね、一番本当に恵まれてね。私のような者が初年兵教育を命じられてね。初年兵を教える教育、教育、教育係。助教助手っていってね。最初は助手、それから助教。
聞き手:それ何年ぐらいの時?
それはね上等兵になれば。1年過ぎて上等兵になった。
聞き手:(昭和)15年?
14年に入ったから15年。15年の暮れから16年のはじめ頃だなぁ。
聞き手:上等兵になったのは早いですよね。
上等兵になってから、今度は初年兵を教育する。戦の教育から気をつけ、敬礼、前進、全体停まれとか、前に進めとか、前に進めと言われると言われるまでこうだ(歩く格好する)、
聞き手:それは中国で?
中国。それから戦場の鉄砲の打ち方、それから叩きあいする、格闘とかね、そういうのみん教えるわけだ。その係が、幹部候補生まで全部来る。将校になる人も。私が(教えた)。日本の軍隊は頭のいいものだけを将校として。あの、幼年学校というのか。頭の良い奴だけを、例えばあの小村ジュンイチとか、そこにある(手で指す)、持ってきて見せてくれ。(奥さんに言う)
聞き手:小村さんは士官学校を出ているのかな?
士官学校、あの人は幼年学校出だもの。あの人がね、終戦だということが我々はだいたい解っていたが、中国におれば毎日戦だもの内地のことほとんどわからない。いいことも、悪いこともわからない。そうしたら、20年のいや18年までは負け戦と言っても、まだ負けた気持ちはなかった。18年以降、19年、20年に後になると全然駄目だと言う、というのは東京が焼け野原にされいてる。それから主な4大都市はほとんどやられる。秋田は20年の8月14日、あこの石油会社全部やられている。それから20年は広島に原子爆弾やられ、そして長崎は6日と9日に、わずか1週間足らずのうちに、両方の県がすっかり焼け野原にされて。ということがちゃんと情報が入っている。
聞き手:それは何年ごろ?
入ったのは20年の7、8月ごろ。
聞き手:終戦間近にね。
共産軍攻撃によりニューギニアに行かずに済む
ほとんど戦、負けるんで。日本の天皇が原子爆弾の広島と長崎によって、日本はこれ以上頑張っても無意味だと。南方は飛び島作戦と言って、島いっぱいに置いて、南方の軍隊はほとんど戦で死んだわけではない。行く途中に撃沈されて、それからやっと渡ったものは、上から爆弾、それから南方だから病気、病気ね、そういう病気で死んだ。だから秋田県では私の本隊だった223連隊というものが、秋田の軍隊は強いもんだから、私はその先遣隊というの、それで1個大隊、私の9中隊から、1個中隊から一人、私が分隊長として14、15人連れて、各中隊から1個分隊で、全部集まれば1個大隊くらいになる、約1000人近く。それをニューギニア要員として、先遣隊として。歴代の負け戦で、なんともならないから。
一個大隊が行こうと思ったら共産軍にぶつかった。あの中国の。河南省から行こうと思ったら、18年の年だ。それで、俺行けないのニューギニアへ。共産軍のおかげでニューギニアに行かなくなった。(笑顔で話す)、俺の大隊がそっくり八路軍に攻撃されたものだから、汽車から降りて攻撃した。そして八路軍を追いかけていった。逃げたものだから追いかけた。そして(敵は)また戻ってくる。とうとう先遣隊がいけなくなった。ニューギニアへ。それで、俺の本隊である約3000人のうち、1000人が撃沈されている。行く途中、ニューギニアに行く途中に爆撃されて。やっと1000人くらい上がったの、上がったものは今度は病気で、病気と、敵は隠れている奴には無差別で爆弾を落とした。隠れていたものは、山にはバナナとかサツマイモがいっぱいあるわけだ。それを食えばよかった。極端に言えば、ニューギニアでは男でも女でも着るものが無い。男でも女でも、ここに木の葉っぱをつけて(股のところでその恰好をする)、ここに木の葉っぱ置くだけ。着るものいらない、気候も寒さも何もない。食い物は何も心配ない、山に行けばいっぱいある。そういう所に、我々223連隊が遣られた。
聞き手:すると加藤先生は17から雪部隊である223の方に行ったんだ。
ニューギニアに行くと思っていたら、山西省で攻撃を受けて敵を追っかけて行ったから、追って行ったらまた敵も来るんだから、先遣隊に行けなくなった。そしたら本隊が直接行った。無理していった。そしたら1/3が行く途中で撃沈されて、2/3が島に上がったんだけど、病気で半分が(死に)、終戦によって帰ってきたのが1000人。3000人のうち、2000人が死んでいる。1000人は帰ってきた。
聞き手:加藤先生は17(連隊)で山西にいて、戦闘繰り返していましたよね。18年頃、昭和18年頃南方がちょっとやばいとそういうことで、223の方で所属になったと言うことですよね。
そうそう、223連隊に命令が来た。命令来たのだけど、まず先遣隊をやって、向こうに準備要員として出されようとした。
聞き手:223(連隊)は最初から223(連隊)ですか?
最初17連隊と言うのがあって、これま満州のほうに行ったと思うよ。満州を抑えて、そのあとに優秀なやつをフィリピンの方に連れていったの。東北の強い奴。それでフィリピンに行って、ほとんどもう苦労したんだ。フィリピンで最初は良かった。それで、マッカーサーが盛り返してきて、飛び島作戦で硫黄島なんかは全滅している。そして後の方は、何が起きたかというと、人の食い物が無いと人が死ぬと、食いものを届けられないようにした。飛び島作戦といって、一つ一つ順序良く片づける必要はない、所どころ抑えれば、あとは構わないと言うやり方。だから日本兵法いうのは、昔からチャンチャンバラバラの戦が、ずっと精神力だけの戦だった。だから物量と科学の力に日本は負けた。量でいっても全然話しにならない。それはもう一つは一致協力する体制、○○が敗戦の情報知らなかったってことかな。とても勝ち目は全然なかった。17連隊が満州に行った。
1945(昭和20)年5月頃 特攻(ゲリラ)要員になる
私は、特攻隊の一つに入っていった。20年の5月ごろ。特攻隊要員になった。今も、特攻徽章がありますよ。これは命と交換ですよ。
聞き手:18年にまずニューギニアに行かないで毛沢東軍と戦う、18年、19年。その時はまだ中国の山西の方にいるんですよね。
山西省。
聞き手:14年から結局ずっとあそこの中国にいるわけですよね。
全部中国。
聞き手:一回も途中は戻らなかったですか?一回も秋田の方には戻って来なかったんか?) 一度ね、初任兵受領にきた18年、初年兵受領に来た。初年兵を迎えに来た。
戦後13軍司令部要員となり、秋田県の復員恩給業務を担う
20年の年に、戦を日本が今これ以上はできないと判断したのは昭和天皇なの、昭和天皇。ポツダム宣言。自分が英米に対して戦いを信じて、ちゃんと戦争を仕掛けたの。天皇陛下が。わかるでしょう。昭和16年12月8日に、大東亜戦争。それは天皇が、米国と英国が中国を支えるために、陰の。これらがついていると日本の中国進出ができないということで、このままでは大変だということで、米英に戦いを宣告した。それで12月8日に真珠湾攻撃して、あの勢いでグーと飛び越したら勝っていたかもしれない。アメリカもこれじゃと言うことで、全部総力で来たから。20年の8月に天皇がこの調子では日本は終わりだから、ポツダム宣言を受諾すると言うことを天皇陛下が。そうしたら軍部が戦をして負けたらどうなるかわからないから、絶対降伏しないと。しかし南方はすっかり負けているわけだから、降参、降参で。すっかりダメなんですよ。
勝ってるのは中国だけ、約100万の無傷の軍隊が中国では健在だった。それで本国が無くなっても、この大中国があれば、日本人は1億2000人、我々学校当時は国民7000万人、あるいは8000万人、それから10年くらいたっているから1億くらいになっていると言う。産めよ増やせよの時代で。1億2000人と言われた時、中国は何人いたかと言うと10億はいた、10億人だ。日本の10倍、世界の人口38億と言われていた。そのうち中国が10億、後の28億のうち日本が1億、後はアメリカとか何とか、そういう状況であったものだから、今度終戦時に天皇陛下がそう言ったら、天皇陛下に反対しているのが、中国の日本の軍隊なの。それでこれでは大変だと言うことで、昭和天皇が朝香宮殿下を中国へ、飛行機で行かせ「直ちに天皇の命令だから復員せよ、一兵たりとも内地に帰れ」とこう言う命令が来た。その時に、日本の本土はどういう状態かと言うこと(情報)が入ってきた。そしたら、日本は終戦になり、天皇が降参したから負けたんだし、これはどうなっているか、どうするかということについては、日本では内地にいる軍隊は全員復員、外地におるものは帰ってきた翌日をもって全員復員、つまり一般の国民だね。なれというこういう命令だね。
それで、どうしたかと言うと223連隊の連隊長が高木正実(高木正実少将・陸士27期)さんと言うが、その高木連隊長が、俺は終戦時特攻隊は解散したから、上海まで来た。そしたら13軍司令部、登兵団と言うのが上海で命令で、俺じゃない、あの当時俺は84大隊(第69師団独立歩兵第84大隊)にいたが、そこの代表として13軍司令部要員になったの今度。
聞き手:それはいつ?
終戦の年。20年の8月、8月9日も持って天皇が降参すると、9日をもってソ連が出てきた、ソ連が。条約をもって出て来られない奴が出て、ソ連がいうこときかないで逆に攻撃してきた。満州にいた日本人と日本の兵隊を全部ソ連の開発のために奥地に連れて行った。これが5万人、5万人連れて行った(注:抑留者数は約60万人弱、うち6万人ほどが亡くなっている)。1万人以上、約半分くらい病気になったり、死んだりしている。生き残った者が帰ってきている。約2万人くらいが生き残り、約半分復員。最近みんな死んでいるけれど。ほとんど死んでる。日本では各県の復員業務の中に、地方世話部というのができている。その地方世話部要員にお前が行けと。私の13軍司令部から来いと言われて。それは20年の9月、8月の末か。
聞き手:それは上海で?
上海で。上海の登兵団の要員になった。そこで1か月間今度は地方世話部の要員になったら、地方世話部の部長の言うことを聞けと、大陸の一兵卒にいたるまで復員するまで面倒見ろ、それがお前の任務だと。まず俺は見込まれて、人が復員するのに俺は復員できない。それで俺はいったん21年の1月2日に鹿児島に上陸した、上海から。その時健康で帰ったものは秋田県で私一人。あとは全部患者とか病人船。そういう方々を船(運ぶ)で準備している。その中に、俺が入って、各県に1名ずつ中国からついてきている。鹿児島に2日に上陸して、3日に地方世話部に来た。うそを言うわけに行かないから、全部書いたものがある。兵籍が。
それで高木正実という連隊長が、それが少将になって負傷した、中国で。それで内地に来て、歩兵学校長になって、少将になった。秋田地方世話部長になった。そして俺が挨拶したでしょう。そしたら「オイ、君来たのかい」と言った。あの連隊長が。
聞き手:あの雪部隊の連隊長が223の連隊長が回りまわって。 世話部の部長になったということ?
そうそう、世話部部長というの。その次に滝本一麿(かじまろと言っているがひでまろと読むこの人か?)と言う人が少将で、高木正実連隊長じゃなくて部長、その次に滝本一麿と言う人が少将、その人に俺使われてずーと、23年まで国家公務員、私。21年の1月3日以降復員、同時に臨時召集を命じるということ、秋田県では俺一人。終戦後、臨時召集になったのは。そして23年の12月新憲法で、それまでは地方事務官、国の職員。23年からは秋田県庁、県の職員になった。そうしたら、地方事務官から、お前辞めるなら辞めてもいいよと言うこと(通知)が出た。俺のところは、財産もあるし土地もあるし、おれは(辞めて)帰ってもいいと思ったが、言われたことは中国で「1兵卒のところまで面倒見ろ」と、「お前全部やれ」と。陸軍も海軍もそうだけど、ご承知のように戦傷病者、戦没者遺族等援護法という恩給法があって、終戦後初めての新法律による戦傷病者、戦没者遺族等援護法は厚生大臣の裁定による裁定調査、それに使われて遺族に対する年金、弔慰金について俺と3人班長になって、当時は班長と言う制度は無く、一番下が事務官、それから私らが雇員、それから雇い、そして認可されなければ恩給法上の対象にならない。恩給法の対象は任官してから17年間しなければ恩給貰えない。それが軍人の場合は戦場生活していれば1年が3年の加算、4年プラスになって、戦場生活3年いれば12年。12年が恩給法に加わる。それが南方に行ったものは1年したら、17年に行った人だ、18年、19年、20年と3年行った人で、1期生だけが恩給法の資格がある人。あとは何にも貰えない。あとは、3年以上戦場にいれば一時恩給。そういう制度。恩給法と言うのは各県の公務員の裁定、国の総理大臣の管轄です。
1943(昭和18)年 独立歩兵第84大隊に転属
それから18年以降は内地に初年兵受領に来たという記憶はある。また初年兵教育をして18年以降は223連隊がニューギニアの方に行かなくなったから、独立歩兵、勝84大隊(第69師団(勝兵団)独立歩兵第84大隊)に、中国に残って。独立がつけば小隊であっても単独で戦ができる。それでないと上司の指示でないと動かれない。勝手に戦ができない、ただ攻撃された場合は応戦している。独立部隊は自由行動できる。我々のように、これ貰える(バッチを示す)ようになれば1人で、3人一組で(行動する)。桜部隊、俺は。そこに(本を指で指す)初年兵時代の思い出は、書いてあるが。それは2部か3部あるから1部はあげてもいい。初年兵時代、厳しかったと言うこと、経験したことが全部入っている。(加藤さん本を探しに席を立つ。)
上海は終戦になってから、内地に帰るために命令によって、上海に集められた。それまでの間、ニューギニア要員として行こうとしたら、共産軍とぶつかって行けなくなって、84大隊へ223連隊からいった。これが独立歩兵84大隊だ。(写真を指で示す)4214だな、勝大隊(勝4214は独立歩兵第84大隊の通称号)。(写真集をめくりながら)これ見れば、嘘か何かみんなわかる。これあげる。
名簿全部出ている、(本をめくりながら)これは俺が現役の時のものだから、しっかりしたものだ、間違いないものだ。全部名前がある。死んだ人は死んだ人で。死傷者名もある。勝第84会会員名簿、それから写真も付いていて、説明もみんな付いている。(勝第四二一四部隊 独立歩兵第八十四大隊誌)の本を見せる、大判、茶色の表紙)
聞き手:18年以降の加藤先生の動きが判る
(本をめくりながら)勝84隊の歩み。
妹に婿を貰う話が出ていた
聞き手:加藤先生一つだけ聞きたいのですが。復員した時にお父さんとお母さんがいますね?
いた。
聞き手:長男であるたった一人の息子が帰ってきた、加藤興治兵衛家の跡継ぎが帰って来た。かなりお父さん、お母さんは喜んでいたのではないですか?
それがある面では真実はわからないけれど、おそらく中国に行った者は帰ってこないんだろうと、中国では日本の本国がほとんど駄目だったから、我々は中国には無傷の100万の軍隊がおるんだし、(中国は)我々がみんな把握していた。全部ではないけれど、大事な所は、北側と南の方までこう(手で示しながら)獲っている。西の方だな、西の方だけはまだ獲っていない。そのことについては、これからの我々の仕事だと、天皇陛下にある程度中国の軍隊は反対した。ポツダム宣言受託、降参するなと。そうした時天皇は「何を言うか、全ての責任は私の身はどうなっても良い、日本の国民だけは残したい、責任は私にある」と天皇がこう言ったという。それで、朝香宮殿下を遣わして「私の命令だから直ちに従え」と「天皇に反対する者は非国民だ」とそれで、急に帰ることになった。それで18年以降の、状態がこれ(名簿を示しながら)で、名簿から会員名簿から。このころ4人の班長と、モリという班長とハナダダイシロウ、4人は私と何回も会っている。
聞き手:夫人:一度帰ってきた時、お父さんとお母さんどういう風だったかと聞かれている
そうだったな。家の親爺はもう帰ってこないだろうと、これ(奥さんを指さし)と同じ年でレイコという学校の先生をしている(妹に)婿を貰う案を出していた。
聞き手:もしなんかの場合はね。
しかたないと、そこに(指さしながら)土蔵があった。真向かいに。土蔵の所に住んでして、俺のことあんちゃんあんちゃんと言っていた。ヨンジと言っていた。與治兵衛だからね。ヨンジと言うのは親だから。帰ってこないんだろうと、俺の親爺が○○○で、北の方に向かって。学校の先生でこいつ(奥さんを指さし)と同じ年の昭和3年生まれのレイコと言うのが、ゴジョウナミノから初代の県会議員がここから出ている。ケイイチだか言う初代の県会議員が。(俺が)死んだときは婿を貰うと言うことで計画していたんだと言う話だった。「何言うか、貴様、そんなこと言うか」と○○○言った。それが今だにまだ元気だ。学校の先生している。
聞き手:加藤先生は中国にいて、いつくらいに日本はやばいと思ったんですか?
それは我々にはわからなかった、情報が我々末端にはわからなかった。一線にいるし、常に敵と相対してと同じだから。内地とは(違って)、表面は大人だけれども、シーさんである、先生であるけれど、内心はどんなに腹悪くしているかわからない、一歩間違えばいつ自分が殺られるかと、これは常に何気なく相手を信じていない、中国人を俺自身は信じていない。だけど、表面は「オウ、オウ」(握手する仕草)と握手やって、毎日楽しく過ごしていた。我々は毎日会って、敵対行為と同じ。、ここまでは自分の領域で、監視しなければならないと。そういう任務だし、向こうは日本人はここに来てこうしているから、今のところ日本人には勝てない、だから表面はあきらめている。でも内心はいつでも暇(隙)があれば、中国全般でいつでもやってやるという立場であるんだなと私はそう思っていた。
いつ死んでもいいと覚悟したら、恐ろしくなくなった
聞き手:加藤先生は14年ごろは上等兵になりたいと思った。次は実際戦闘行為をしてちょっと怖い、敵に背を向けても帰りたい、しかしすぐに偉くなった。教官として部下に教える立場になった。考え方の中で、この戦争と言うのは後半戦はもしかして負けるかもしれないと、早いところ終わるべきだと言う本音はあったと思うんですが?
私はそう思わなかったな。あくまでも日本は戦では負けるとは思わなかったし、でも入ってきた資料から言えば、もう日本の本土は駄目だと、それから南方諸地域も全部叩かれてしまって、自分の○○な容易でないところまで来ているんだな(という思いはあったけれど)、日本の本国の38倍、ないし50倍ある中国で、世界で面積の一番ある国が中国、その次がソ連だと。ソ連は北極が多くて住まれない場所が多い。そういうことしか聞いてないし、知識もないもんだから、上の人が言えばその通りだなと言うことくらいしか感じていなかった。だから戦は負けるとも思わなかったし、負けるにせよ命は生まれたものは必ず死ぬんだから、死ぬってことを恐れない、だから、いろんなことを一旦やってからまた戻ろうと、弾が当たってもいいから、負傷してもいいからまた行きたくないなと言う気持ちもあった。
同席者:人間だから、俺もそう思う。
実際そう思ったんだ。しかし、行かねば、行かないわけにはいかない胸がどきどきして、落ち着かない。これじゃ困ったなということで、思い直した。「やろう、どうせ死ぬ気なら一度は死ぬんだから、死んでも良いと。いつ死んでも良い」。しかし先輩の1年ないし1年半前の古年兵の人で、佐藤シンスケという人が、横手の人で84会の会長もやっていた。この人が戦に行くと言えば鼻歌歌って冗談(言ったり)、おはら節歌って「はー」と、紛らわす。「この精神がいいなと」こう思った。それから、死ぬと思うから恐ろしい、死ぬと言うことを覚悟した時には何も恐ろしいことは無い。
だから今この方(奥さんを指して)、バカなことを言うって、いつも言うけれど、若い人方も「私はいつ死んでもいいよ」と言えば、そんなバカなこと言うかって本当にしない。私は今日は、今はいいけれど明日以降はわからない、明日死んでも良いとこういう覚悟がある。だから、非常に気楽な面は気楽だ。自分より早く死んだ人たちに比べれば自分は幸せだ。いい時も○○も、私の肉親の叔父(叔母)、私の母の死んだ末の妹、101歳で去年死んだ。近藤コンと言う。立派な家に行っている。近藤カツタロウと言う司法書士の所、そこの人間。それから、男では俺の母の弟、キンジという。北海道に住んでいて秋田に来たときは遊びに来て、酒好きだから私と酒する。うちの親爺も酒全然飲まない、これは(鴨居の写真を指しながら)母の方、俺の父の方は誰も酒飲めない、俺の親爺も。
食糧事情
聞き手:中国で弾だとか食料が不足していた時期はありましたか?
(戦いは)どこまで続くか分からないから、大事にして使わなきゃいけないよというふうな、節約して、大事にしようというそういう暗示を与えられたけれども、常に私は特に擲弾筒手だったから、擲弾筒手っていうのは、1分隊、2分隊、3分隊、4分隊、一個小隊に4分隊あるんですよ。一個小隊ね。1個小隊に擲弾筒というこういう弾がある。でこれが擲弾筒でここを引っ張れば、ボーンといって敵の山からこう落ちる。(手でその弾道を示す)それでその擲弾筒手だった私。つまり私自身も筒(とお)を持っている、それから弾薬手が両側について、私が「弾込め」と言うと、私が方向定めて、風力を考えて、距離とを修正をして、私が引くとボーンと(弾が)出る。そして「次」「次」と言われた時に、こうどんどんどんどん敵に。(手で弾を込める形を示す)
聞き手:弾、そういうのは不足したなと言うのは?
あまりそう思わない思わない、思わなかった。でも大事にしなければいけないよと言う注意をされてた。
聞き手:注意があって大事に使ってるけれども。要するに絶対ないということではなかったんだね。
不足ではなかった。そういうことはなかった。
聞き手:食料も食べ物も?
食べ物は、不自由を感じられました。というのは誰でも米来るやつが、米が内地の方で無くなったということで、、それが送られる途中で撃沈され、届かなかったと。それと南方の方ではほとんど食糧にやられてると、国内の人も腹いっぱいご飯食べれなくなったということは情報が入ってる。それで私たちもあの普通であれば一回にね、時によっては5合ぐらいを一食で食べるのだが、5合を。食える時は腹いっぱい食って、あと2日も3日も食えないで敵を攻撃する。
聞き手:5合一人で?
一人で、1回で。食べる。今は1合もやっと1回で食べればいい。
聞き手:1合はだいたいお茶碗で二杯ぐらい?
それで、これ一つが1合(机の物を取って示す)、これ5つくらいは1回で食べたことがある。
聞き手:食べる時に食べておこうと。
そうそうそう。
聞き手:でもそれに関しては食べるものがまずあったということだね。米は。
そう、あった。でも終戦間際には米が充分来ないというので、今度○○○わけです。菜の花を混ぜたり、他のトウモロコシか何かやっぱりほかのものを混じえてね。あるいはあの何か副食となるものと混じえたりね。
聞き手:現地で調達するってことあったですか?中国人の?
中国にはそれぞれの場所によって、米が主なところと、米はなくほとんど粉だね、麦の粉だね。それで中国人は(粉を)ちょっと入れると、水いっぱい入れて糊粉(のりこ)にして、こうやって(大きい鍋を手で抱える様子を表す)2杯も食べる。場所によってね。食い物がうんとある所と,不憫な所と。それでも、食いものが無ければ生きていけない。それなりに米なり麦なり、それから主食の代わりになる副食みたいなものが所々にあったから、そいつらのものを最悪の場合は徴収してくる。早く言えば、奪(と)ってくる。まず。あるものはね。チャンチューと言ってね、日本では米、酒、中国ではチャンチューと言った。トウモロコシとか麦とかで作る酒。チャンチューはよく飲んだ。しかしチャンチューは非常につよくて、日本で言えば焼酎。ジーンときて甘味も何もない。日本の酒はおいしものね。甘味があって。
夫人:食糧続かなくて、中国の住民の食べるものを取って食べてたのか
作って食べるんだよ。
聞き手:襲ったりするではなくて、戦闘して、中国の兵隊さんが持っているものを取って食べることもあると。 地域の住民からはそういうことないでしょう?
住民からは我々は宣撫班、仲良くしようと言うのが任務だから。昭和14年以降はね、仲良くしようと。昭和6年の満州事変、昭和12年の支那事変、1~2ヶ月、チャンチャンバラバラはあるんですよ。期間はわずか1~2ヶ月。その期間で、ぐーっと突っ込んでいって。(銃剣で突っ込む姿勢をする)それで、敵が手を挙げて。負けた、負けたと、はい分かりましたと。(手でその恰好をする)。その勢いが日本はあるから、チャンチャンバラバラのそういう気持ちがあるから。何やっても勝ったんだから。その勢いを我々は持っていた。だけどいつもそういうわけにはいかない。イギリスもアメリカも協力して中国を支えるようになった。
聞き手:まず食糧は基本的にやはり最前線の中国にいらっしゃる陸軍だから、最優先に山西部隊と言うか陸軍本部のあったところだから食料はあったと思う。
食料は最悪の場合は、中国人が10万人いると(言っていたけれど)、実際は100万人おると言われた、実際何人いるかわからない。今でも中国の本当の人口はわからないと言う。末端まで届かないんだね。国でも、まだまだ未開発地がいっぱいあるという。日本の面積の38倍あると言っていたが、だけど50倍もあるんだと、こう言われた。人口も10万人と言うけれど、100万人だよと言う人もおったり。なんぼいるかわからないと多いのが中国。だから中国では一夫婦に一人しか子供を産んではいけないと言う。
聞き手:一人っ子政策ですね。
届け出は1人でも、実際は2人とか3人も産んでいる。あるいは10人も産んでいる。
聞き手:戸籍上は1人でもね。上海や都市部は金が払えば産めると言うのもある。
加藤先生が中国で一番苦労したなーと思って、6年間もいたからね。普通は3年とか2年とかだが、6年もいたのだから。苦労はね。最初、戦をしたころの恐ろしさ、それは身に染みて恐ろしかった。それから作戦をして計画的に敵を攻撃して2ヶ月も3ヶ月も追いかけていった。一つの村に1回、1大隊が行けば1000人以上だから、あるいは3000人、5000人、1万人と言うように、また・・・・・部隊行けばすぐ水がなくなる。米もマンマ(ごはん)炊くし、水無くて洗う暇(こと)がない。(食器を洗う格好をする)水が第一で、食いものにはそんなに不自由はしなかったが、食い物はやっぱり一番大事だし、まず心配した。
聞き手:戦争中だからね。1000人の人が一気に食糧、水を使うものだったら、やっぱり水はそんなにですね。いやー、一気に行くからね。
いつも死に水は残しておいた
夫人:水に不自由したことはあったかと言う質問ではないか?
聞き手:いま、水が不自由したと言うことは今聞きました。
それはね、水筒に水を入れると言うのは「死に水」と言って、死ぬときに水を欲しがるものだとこういうふうに聞いていた。私は水筒に一旦水を入れ、どこいっても水をまず入れるのが第一。同時に一口か二口を残しておいて、ちょっと口を湿してしまってしまう。最後に飲もうと思って。常に。
とにかく一滴を残している。ちょっとちょっと。死ぬときに飲もうと思って、こういう気持ちでやっていて。その水の尊さは身に染みて感じている。水、食い物よりももっと水。水だけ飲んでも、一ヶ月、20日以上生きるよと。死ぬときは水によって、死んだ人は、花園はどこいっても毎日花園のどこがあるけれども、一番欲しいのは何も食いたくない、水だけは一番ありがといと、こういった話をしたと坊さんが言ったけれども、私に直接。俺のかかあも、俺のアイコが死んだのも、私は1回も、50年だか一緒になったけれども、水飲んで死んだことないと、坊さんの言うに。1ヶ月くらいしてから、「與治兵衛さん、俺のかかあが初めて夢に出てきたと言うの。よう(夢に)出てきたなー、いろいろ話をしたけれど、時間だから行くと言うの。待て待て、何かお土産やるからと言ったら、「何にもいらねー、なにも食いたくねー、毎日任務があって、毎日歩くことが仕事だ」と言って、そして一番大事なことはどこへ行っても花園、花のきれいな所、崖登って見下げればまた花園、このあらゆるところ見ればきれいな所、危険な所もあるけれど、そこを突破していけばまた開けてくる。一番欲しいのは水だとこう言った」と言うの。それがアイコと言う、藤原て言うの、もとはここにいた。藤原アイコと言うの。トモの姉だ。法妙寺の前のお坊さん、私の三つくらい上だった人。三つ下の妹が私と同級生。その妹がトモという。その、坊さんの言うことになるほどなと、一番大事なことはご飯あげるよりも水をあげること。最高のありがたさ、死んだ人は。花よりの一番大事なのは水だと。
同席者(ご遺族):毎日水あげている。自分の親爺さん
それが最高。
同席者(ご遺族):毎日、一番早く水上げるのが。自分の実家は○○(キンダン?)にあるから仏壇向こうにあるから、位牌の小さい奴二つ持ってきている。俺、次男坊だから。写真をこういう小さい奴、毎日朝5時半)
たいしたもんだね。能力が大したもんだ。
特攻隊と、帰される命令
聞き手:こちらですが(徽章を示しながら)、84大隊の人は特別な任務の人が持っていたものですか?この徽章は?
これはそうじゃない。 これは師団から。桜部隊と言うのを編成した。特攻隊要員、希望者を取ったの。いや希望者じゃない(首を振りながら)、各中隊に何名出せと言う、約300名くらい募集した。
聞き手:師団と言うのは何師団ですか?
69師団だね。海軍ばかり敵の軍艦に突入して、神風特攻隊で。特攻隊の資料ありますよ。全部あるんだけど。これはいよいよ、陸軍もこれではいけないと、特攻隊を編成、桜部隊と言う。それで、独立歩兵・・・50?(考えるが出てこない)、
聞き手:昭和20年何月ごろ?
昭和20年だけど、その前から出ているけれど、私は3回目に特攻に話があった。私の大隊から下士官が1名、当時は曹長だ。私が曹長になってから、俺の先輩が2人行っている。これじゃ駄目だということで、資格無いということで、2人は帰された。2人は同じ下士官で、同じ曹長で。それで中には住民の自衛隊みたいな、そういう役割をした人もいた。使い物にならないと帰された。それで、3回目に一番後に私のところに特攻の話がきた。
聞き手:陸軍の特攻ですか?
そう、陸軍の特攻。独立52中隊だ。それに出ていないかな?(本を指さす)出ていると思うけど。
聞き手:斬込隊ですか? どういう任務なんですか?
任務は、敵の重慶、蒋介石軍の、大物がいる所に夜行軍をして、日中は隠れて、穴を掘って橋の下とか、藪の中とかに隠れている。夜、敵の要所要所に隠れていて、敵の主要な所に、(特攻部隊は)300人くらいの人で、1班が3人、3人が一つの仲間、私が2人の仲間を連れて、そして私の部下が14、15人いるから、3人ずつ一組になって、文殊の知恵で3人の協力によって、3人一緒に爆破させる。そうすると、あっちでもボーン、こっちでもボーン、とやられると。
聞き手:決死隊ですね、決死隊。
その任務だ。勝ち負けではなく、敵の重要な重慶近くの、ところどころの連隊、師団、大隊のあるところ要所要所に配置されて、ボーン、ボーンとあっちでもこっちでも破裂させた。
聞き手:死ぬのを覚悟で行くと言うことですね。
そうそう、死ぬのを覚悟で。
聞き手:普通の兵隊のように、危ないから逃げると言うのではなく、完全に特攻で?3人一組で目的を果たせと言うことですよね。爆弾を持っていくと言うことですか?
そう、爆弾をもって(腰に巻く格好をする)、隠して、普段は軍服を着ていない。便衣という中国の服装。中国人と同じよ。そして軍人のあれ(装備)は何もなく、便衣で、そして腰に爆弾を全部隠していく。
聞き手:アフガンのテロみたいなことですよ。
もちろん、テロ。あっちでもボーン、こっちでもボーンと、要するに相手を脅すこと。そういう任務だった。その任務に入ってから私は一番後から行ったから、特攻隊長がササキシンジと言う岩手の人だった。紫波郡紫波町、優秀な男で大尉になっちゃった。この特攻隊長が、この男が、私が一番役に立たないと、一番後から行ってるせいかね、今爆破をする(その任務に)入る4、5日前に、敵地に入ってから、私も一緒に行った。部下連れて。そしたら、「加藤まいれ」と呼ばれ敬礼した。(敬礼の恰好する)、「命令、加藤にただいまより部隊長代理を命じる」と言うの。桜部隊長の代理を命じると言う。自分が部隊長で「師団との、69師団だね、師団との連絡を密にしようと。これが一つ。二つ目は遊泳特攻隊ということで、同じ加藤という男でね、国体かなんかで水泳の非常に、指導者をやったと言う男で、100人の水泳をやれる人を選んで、そこの隊長になってうちの方に来た。当時、日本全国の水泳の選手まで選んだようだ。その100人を連れてきて、その休養、給与に任ずべしと、休む方の休養と食べるほうの給与、休養、給与に任ずべしと水泳特攻隊の。そして、師団との連絡を密にせよと。現在地に残れと、ここから下がってもよいと、特攻に入っている人は別だよ。私一人だけだよ。
もう一つの任務は、すでに負傷した、病気になった人が10何人おった。300人の中で。1個小隊、3個小隊と、指揮班と、4つの隊で。一つの隊で3人くらいいれば3×4で12人。約20人近くいた。それの休養、給与を担当しろと命令で。俺は死にに行くと言うときの寸前に、現在地に残り、師団との連絡を密にせよと言われたから、私は「ハイ」とこう言っていながら、「加藤も爆破に遣(や)っててもらいます」とこう言った。そしたら部隊長が「何!命令だ」と言って軍刀に手をかけ(軍刀に手をかける格好をする)、1/3くらい抜いた。私はその場で「ハイ」と言ったの。その上俺の言うことを聞いたとなったらたいへんなことになる、隊長の資格ないもの。命令だもの。命令に対して反対したと言うことになる。「現在地に残れ、師団との連絡を密にして、次の3つの任務を達成せよと、終わり」と(部隊長は)こう言った。 それに反対して「加藤も遣ってもらいます」とこう言ったら、「命令だ!」(軍刀を抜く格好)とこう言われた。それで(私は)「ハイ」、(部隊長は)「守れ」と。「ハイ」と私は残った。だから最後のところで、ボーン、ボーンやった時に、健康なものは私一人残った。負傷したものは10人くらいいた。かなりの(重症の)者もおった。負傷とか、病気とか。そいつらのことをみんな診なければならない。これが任務。健康なのは俺一人だったから。そしたら俺の分隊の、体の悪い奴がやっぱりおった。分隊にも2、3人おった。そいつらは俺のおかげで助かって、みんな帰ってきた。
それは、終戦間際朝香宮殿下が来て、命令が出て爆破する直前に逃げてきたんだ。
今まで生きてつくづく感じることは、今の自衛隊のようなもの、誰だって自分が自由に生きたいというのは言うまでもない。自分が一番大事なことも言うまでもない。それでは社会っていうのは成り立たない。やはり大事なことはね、あの今の自衛隊のような所に1年ないし、1年半、2年以内義務付ける必要があると。社会のためにあの本当の、お金を貰うじゃなくて、最小限度の月に3000円なら3000円、2000円なら2000円、チリ紙買うとか石鹸買うとか、そういう小間使い(必要なものを買う金)もらってもいいけど、お金は全然もらわないでで、相手の為にその奉仕する、そういう制度を18歳から20歳までの間に、これを義務付ける必要があると。でないと誰も今のような自己本位の、自由主義になればみんな自分のことばっかり、人のことを誰も考えない。これでは社会は成り立たない。
だからその制度がね、これが是非欲しい。必ずその苦労、苦労しておれば、他の人のために、あるいは天災があった場合、津波があった場合、役立つ、重要な任務を果たせると思う。この制度が是非必要だなとこう思っている。これ本当にね。私だけでなく、自衛隊に行った人はいい例だと思う。ある程度言う事きかねば、自分の意見はとおらないんだから。いわゆる社会の維持していくためには、やはりそういう人のために尽くさなければならない義務があるという、義務が必要だと私はまずそう思ってる。これご参考にね。
体験記録
- 取材日 2006年 月 日(miniDV 60min*2)
- 動画リンク──
- 人物や情景など──
- 持ち帰った物、残された物──
- 記憶を描いた絵、地図、造形など──
- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─
参考資料
戦場体験放映保存の会 事務局
■お問い合わせはこちらへ
email: senjyou@notnet.jp
tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)
■アクセス
〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2
JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分
都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分
Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.