金丸 幸輔さん
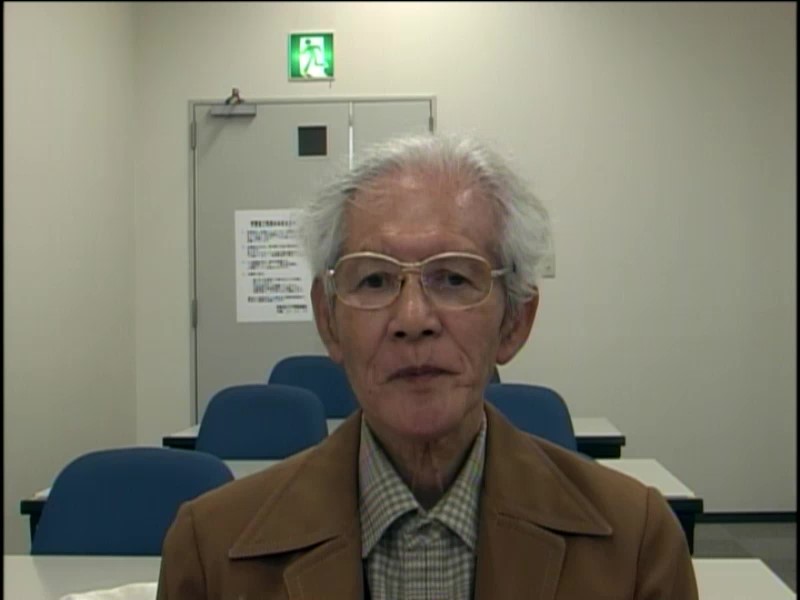
| 生年月日 | 1930(昭和5)年1月17日生 |
|---|---|
| 本籍地(当時) | |
| 所属 | 民間人 満鉄職員 |
| 所属部隊 | |
| 兵 | |
| 最終階級 |
プロフィール
1930(昭和5)年1月17日生
民間人 満鉄職員
1944(昭和19)年に満鉄入社
1945(昭和20)年3月チチハル鉄道局へ
1946(昭和21)年9月チチハルを出発して博多港へ引き揚げ
インタビュー記録
1944(昭和19)年4月満鉄入社~終戦
満鉄に入ったのがですね。昭和19年4月です。最初から鉄道に従事したのではなくて、吉林というところから少し離れたところの新吉林、これは日本名の駅ですが、新吉林というところに満鉄の専属の訓練所がありました。ここに当初3カ年間の入所の予定だったらしいのですが、まあ戦況がだんだんだんだん変化して、満鉄職員もだんだん入隊者が多くて業務に携わる人員も少なくなった関係で、急遽約11ヶ月でそこを卒業ということになりまして。昭和20年の2月にそこを卒業しまして、3月から北満のチチハル(斉斉哈爾)鉄道局に移転をしまして、ここでまた約3ヶ月、駅関係、鉄道関係に関する訓練を3ヵ月間みっちり訓練をしました。そして5月に現地の業務に就きまして、チチハル(斉斉哈爾)駅の私の務めは旅客案内係でした。その他に出札、改札、集札、手小荷物、輸送、それから取次、貨物の受け取り、受け渡し、そういった種の日常の職務についておりました時に8月の終戦を迎えたわけです。
終戦の当日から我々は青年隊舎、工養隊舎と言ってましたが、そこの隊舎に、そうですね、全員で約300名ぐらいおったでしょうか、そこに何ヶ月おりましたでしょうか…翌年の5月頃までおりました。もちろん仕事そのものはもう終戦後5日後には満鉄を放任されたというんですかね、職場を失ったわけですが。それからはもう全日本邦人と同じように、自力で生活をすることになったわけです。幸いなるか私たちは特に若い者ばっかりで、工養隊舎は。しかも家族など1人もおらず、ある意味では幸運かなと思っておりました。それぞれのご苦労はありましたけれども怖かったり、楽しかったり、残念だったり、腹立たしいことやら色々やっぱり残念なことがありましたけれども、5月に元関東軍の大きな倉庫に引っ越しをしまして、そこで各部屋ごとでなくて大広間に雑魚寝というですか、そういうようなことで元気な者がそれぞれ仕事につきました。仕事もいろいろでしたが、そういった人たちが若干の収入を得て、そしてその収入のおかげで皆さんの食料を買ったり、いろいろとお互いに助け合うというのがずっと21年の9月まで続いたわけです。
私は故あって2月頃から中国人の家に住み込み働きをしまして。それも各所に働き口、長いところで約20日、短くて3日くらい、そういったような仕事場を探しながら中国人と一緒に寝起きをしまして、そして引き揚げ時期をただ必死に待とうというようなのが当時の日本人の合言葉でありましたので、いろいろな体験をしまして。
引き揚げが始まったのが9月の、昭和21年の9月の18日にチチハル(斉斉哈爾)では一番最後の引き揚げ列車として引き揚げて帰ったわけです。ただ各地、全満でも同じようにたいがいなところの日本邦人は、最後に引き揚げたのは満鉄の職員たちだったと後日聞いたことがあります。チチハル(斉斉哈爾)でも邦人を先に帰して私たち、特に私たちのような若い者はいろいろな、なんですかね、厳しいような条件があったり、涙ながらに話さんと話せんようなこともやっぱり若いながらいろいろと体験をしました。いま若い者に話しましても「そのような事は実際にあるものか」と「あまり話を吹聴しとるやないか」というような人がかなり多いです。しかし当時の人たち同士では、真実に現在でも話し合っております。現在、満鉄会というのがありまして、宮崎県にも満鉄会支部というのがあります。ここの顧問みたいなのを現在務めております。毎年5月、今年も5月ですが、いま満鉄会の総会の準備に時間を過しております。まあどのような事から話せばいいのかわかりませんけれども、ここにいろいろろ箇条書きでですね、(資料を指す。)
終戦、駅の混乱~満鉄解散
聞き手:(資料を見ながら)プラットホームのパニックと武装解除とありますが、これは終戦間際のパニック?
間際というか3日目です。
聞き手:8月18日の話ですか?どういう事が起きたんですか?
はい。だいたい終戦の日からですね。満鉄はチチハル(斉斉哈爾)だけでなく全満的にパニックになったはずです。チチハル(斉斉哈爾)も空襲一つ受けていないので顕然たる被害そのものは全くありませんでしたけれども、もう列車に乗る人も列車から降りる人もいないわけです。ただ、3日目にですね、まだ終戦当日とその夜と、それから3日目がプラットホームのパニックになるんですが。列車は動かなかったけれども、我々は駅の近くに隊舎がありましたので交代交代で勤務状態をそのまま引き継いで、私たちは駅を守っておりました。そうしましたら朝早く、大体8時から8時半が勤務引継ぎだったのですが、もう朝8時も6時もなく誰か彼かが駅を守ろうということで、まあ5時頃から大なり小なり若い者ばかりがいっておりましたら、3日目の8時前に中国人がですね、使役用に連れて来られていた中国人、まあ“満人”ですが、そういったような人たちが郷里に帰るために、その人たちを送るために列車を仕立てたらしいのです。まあ私みたいな下っ端にはそういう情報は全くその知らされていなかったので、まあ吃驚しましたのですが。私たちが駅に行きましたらすでに列車が入っていて、暗いうちから中国人が押しかけてきまして。私たちがホームに行きました時にはかなりの中国人労働者ですね、クリー(苦力)と言いますが、そういった人たちが(列車が)満員になっておるのに、それでもか、それでもか、と無理押しするわけです。それで荷物がなければかなり乗れるんですけれども、それぞれがもう手いっぱいの荷物を持っていて、荷物があるために「荷物はホームに置いて体だけで乗ってくれ」と警告するんですけれども、そうこうするうちに殺気立ってきましてですね、手に負えるような状態じゃなかったんです。
結局、何列車かが各方面に出ていきました。それが満州里方面、ペイアン(北安)方面、黒河方面、そういった各地のほうに、そうですねえ、昼近くまでかかったんじゃなかったでしょうか。そうしましたらもうプラットホームというのは猫の子1匹おらん静かなプラットホームになったわけです。それで私たちはそこに気抜け同然のように座り込んでおりましたら、今度はまた予期しない列車がある方面から入ってきまして。どこから来てどこへ行くのか、誰たちが乗っているのか分かりませんけれども、まあ列車が出入りするのは私たちの仕事だったのだからそれを迎え入れましたところが、殆どの人が日本人ばかりです。
しかもその列車というのが1等車、2等車、それに2等車の寝台車まであるわけです。見ましたら満州里方面から、満州里線だったら遠いところでハイラル(海拉爾)、ジャラントン(扎蘭屯)。そういったようなところからの日本人の日本人ばっかりの避難列車ですかね。もうそれこそ荷物をいっぱい持ちましてチチハル(斉斉哈爾)に避難してきたわけです。それを私たちがやっぱり迎え入れたわけですが、中には病人、担架で運ばれとる人、特別な、やっと一人歩きできるような高齢者、それから幼い子供たちと。それはもう大変でございました。しかもその整理ができないうちに次から次から各方面から同じような列車が来まして。あの長かったチチハル(斉斉哈爾)のプラットホームは、もうそれこそそういったような人たちでごった返しでした。その人たちから色々な話を聞かされました。例えばハイラル(海拉爾)方面からとか、やれペイアン(北安)地区からだとか。まあ、あの色々話を聞いたんですが、異口同音に返ってきました答えは昨日までおりました地区のところが急に終戦と同時になんか模様が変わりましてね。おかしな状態になりまして身の危険を感じておりましたら「チチハルに早く避難せよ」と、なんかあの通報が来たらしく、急げ、急げというようなことだったらしいのです。それでもう大事な荷物だけを(持って)自宅から出たとたんに、外の周りにおりました中国人がドヤドヤドヤドヤ入りまして、手当たり次第に荷物を持ち出していたとか。急げ、急げということを中国語では「クァイデ、クァイデ」と言いますが、「クァイデ、クァイデ」と荒ら声で急き立てられたとか。それこそもう列車に乗るまでは生きた心地がしなかったというのはどこの列車にも異口同音に同じ答えでした。
その人たちはそれなりの監督者、指導員というのが列車ごとにおられたらしくて、どこかのチチハル(斉斉哈爾)市内の学校とかいろいろな所に落ち着き先があったのらしくて、しかもそれが終わるのがですね、午前中いっぱいかかりました。
私たちももうぐったりと、前日からの勤務だったので、ひとまず帰って隊舎に帰って食事でもしようと帰りかかったら、最後の列車がまた入ってきたらしく、駅長さんやら助役さんたちが「最後らしいからもう一回がんばってくれ」という事でまたホームに返ったわけです。そうしましたらロシア兵の武装した兵隊だったわけです。私たちは恐々と遠いところから見ておりましたら、彼らも珍しそうに近づいてきてニコニコと話しかけてきましたけれども、言葉がさっぱりわからなくて、ロシア語ではないようなことで、よく見ましたら蒙古、蒙古の軍隊でした。その外蒙古の軍隊が武装しながらゾロゾロとホームに降りてきて、その時に見ましたら軍服はきておりましたけれども油と汚れで黒ずんでおりまして見る影もないような、これでも正規の兵隊かというようなあきれたような服装でした。しかも、大概ほとんどの人がですね、手のところに入れ墨をしておったわけです。まったく江戸時代に島流しにされた罪人が入れ墨を、その入れ墨が場所によって罪の上限だという風にものの本で読んだことがありますが、まったく上のほうに入れ墨をしておりました。しかし監督指導は全てロシア兵でやっぱり規律が厳しかったんでしょうね、ニコニコニコニコと我々に話をしましたけれど何ら言葉が通じないわけです。そうこうしておりますと今度は一方の方からそろりそろりと同じような列車がまた別のホームに入ってきました。今度は全員が日本兵です。しかも全員が完全武装しておるわけです。なぜだろうか、ここでまさかドンドンパチパチと喧嘩をおっぱじめたらどこに逃げたらいいんだろうと余計な心配をしましたけれども、日本兵が降りたと同時にホームにあらゆる武器を並べだしたわけです。小銃から手榴弾、擲弾筒、機関銃、そういったようなものをですね。そうしますと相手の兵たちは「タジンター、ツリーストリー」(註:ロシア語の1,2、3 アジン、ドゥヴァー、トゥリー)と言いまして人数を数えているんですね。武装解除だとわかったときに私たちは残念で涙が出ました。その時に本当の敗戦を味わいました。腹立たしいか残念かわかりませんでした。
それから翌日、さらに翌日の5日目に私たちは満鉄から追放されたわけです。もう日本人の職員は特別な技術者以外は必要はないと。そして千円という退職金をいただきました。当時の千円というのはそれはもう大変でございます。私たちの給料はやっと月三十円か三十五、六円。しかも当時は国債を割り当てて、まあ一割くらいの国債を全員が買わされました。それと同時に強制的に貯金をしておりました。これも給料から差し引いて通帳に記入されるわけであって、手取りは二十円前後じゃなかったかと思います。それでその二十円弱で身の回りの品とか勤務明けの休養の時の小遣い、街に行って食事を食べたり映画を観たりというのが唯一の娯楽の時代でした。それでその時の千円です。百円札が十枚です。嬉しかったですね。
結果的にその時いただいた千円は本当に使う段になりましたら千円の価値は五百円くらいに、また最低に価値がなくなったのは三百円くらいにしか使用ができなかったわけです。その理由はですね、終戦直後は旧満州の紙幣だけだったわけです。綺麗な紙幣でした。日本に流通しておるようなサイズと同じように似たような印刷と紙質も同じような見るからにドッシリと重力感のある日本紙幣でしたんですが、ソ連が進駐しましてから軍票を使いだしたわけです。赤い十円札の軍票でした。それを彼らが外出する時にはあらゆるポケットに山のように持ってきて、何を買うにも赤い軍票を見せびらかして買い物をするんです。中国人はその軍票を…何ですかね、当てにはしておりませんけれどもその他には無いんです。しかし中国人はそういうような時にはなかなか狡賢く、(言い直して)頭を発揮しまして、同じ饅頭を一つ、例えば百円する饅頭を一つ買うのにもソ連の軍票なら百円で買えるのです。我々が持っている退職金、それこそ威厳のある札束は百円ではなくて百五十円出さないと同じ百円の饅頭が買えない。全てがそういうようなことで、千円は上手くいって五百円がたくらいだったと思います。
しかも早々とデマがもう飛び回ったわけです。10月には日本に引き揚げるんだと。9月頃になりましたらすでにそういったようなデマが始まりまして、もうそれならば贅沢をして、もう帰るまでは。日本に持って帰れば使えない金だから十分に使っちまえというようにそれとなくいつの間にか無くなった千円の退職金でした。それから10月になりまして電気・水道・電話、そういったものが、もう電話なんか最初からなかったんですが電気・水道は止められたわけです。電気はしょうがないですけれど水道は止められたのはこれはもう一番の痛手でした。井戸を掘ったりなんかしまして、井戸を掘りましたけれども飲める水じゃなかったんです。しかしそれをお湯にして沸騰させますと水が澄んで色も臭いもなくなり立派な飲料水として飲める水に変わりましたが、それを沸騰させる燃料が無い、竈が無い。そういうような事で約300人の隊舎が毎日毎日どうしたらいいか、この隊舎だけでもなんとかいい知恵を出そう、三人寄れば文殊の知恵というが三百人いれば百倍の文殊の知恵がでるんだからと色々しました。結局何一ついい塩梅の回答がなされないまま11月、12月と進んだわけです。その頃になりますと今度、今年冬が来たらどうするかという冬将軍が怖くなりまして。まあそういうような事で若い者同志で色々しましたが、まあその、あれなんかが皆さんそれぞれが苦労しておりました。
私は皆さんと同じようなことでおりましたのですが、私は満鉄に入りましてから一番の後輩でありますので、先輩ばかりで後輩はいないんです。戦前から軍隊と同じように満鉄でも特に若い層は先輩・後輩の絆っていうのが線が引いてあるように厳しかったわけです。ちょっと失敗すると対抗ビンタを食らったり。洗濯なんかと靴磨きは後輩が当然するべき仕事として戦後までその仕来りは続いたわけです。しかし、暑い寒いの時は、暑い、普通の時はかまわないけれども寒い時にみんなの布団を、一部屋5人だったのですが、そういったような事がありましたので二部屋分を一部屋にしてそれぞれ持っている布団とか毛布、そういったものみんな仲間として着て抱きつきながら冬の寒いときには寝ておったわけです。それはもう先輩も後輩も同じですから堪えはできたんですけど。朝方一番早い、特に2月頃の朝方となりますと昨日の日中までなんとかストーブを焚いておった部屋のぬくもりも消えておりまして。それこそもう零下70℃?くらい、その零下何十℃くらいを2枚重ね、3枚重ねで皆寝ておるときに、「金丸!ストーブに火を入れとけ」先輩が言うんですね。その時の辛さというものは手ももうかじかんでおるわけです。しかも先輩が命令することですから、それを行わないと食事を減らされたりビンタを食らう。まあそれが嫌で私は隊舎を1人、まあ逃げ出したっていうんじゃないんですけど自分を守るために。このままでは凍死するだろう、それがあるので中国人の仕事探しをしたわけです。
敗戦~チチハル(斉斉哈爾)の生活
当時の中国人といいますのはですね、日本人と、たとえば満鉄にも中国人の職員は割と多かったんです。そういった方たちとまがりながら中国語も通じておりましたけれども、全く戦前の中国人と同じ戦後の中国人と会話というのは私たちが話すのは通用しないんです。同じ日本人のことを「レヴェンレン」(註:中国語で日本人、リーベンレン)っていいますが、誰かと問われたときに「ウォスゥ リーヴェンレン、私は日本人だ」。「シェンムァ?」何度も尋ねるわけです。何だということを訊きますので、やはり同じく「リーヴェンレン、リーヴェンレン」って言いますと中国人が「ウェテアー?」〇〇いうと、どこが違うんだろうかというぐらいに全ての発音がですね、日本人とあまり戦前会話の少なかった人たちには、私たちが見よう見まねで覚えた中国語っていうのは全く通用しませんでした。その中に飛び込んだわけです。
しかし当時の中国人は、あのー、本来は蒋介石が「日本人を苛めるな」という御触れが回っておったらしくてあまり苛めるというかランチバ(乱痴罵/方言?)的な行動はあまりありませんでした。「日本の国は終わったなあ、お前たちは苦しいじゃろう、まあ頑張れよ」と。却ってそのような言葉が返ってきたわけです。何故ならば、後で私の感じたことですが、満州におられた中国人は日本人を相当敬愛しておったわけです。ロシア人を追い出したと。ロシアの統治時代はなかなか酷かったらしいです。それを日本人が追い出したと。そして日本人が復興したと。当時の駅でも街でも電気一つとしてもうあの最高の機材をという、あんなのを日本が建設をしまして。中国人でも可能な限り職業を与えたりしたのがやっぱり有難いというような噂があったらしくて、その日本人をいま使っているんだ、と。やっぱり鼻が高かったというような声も聞いたりしました。私たちとしてはもうそれこそ嬉しい話でした。
しかし自分に向く仕事、そんなのにあまり就くのは少なかったです。色んなことをしました。まず中華料理店で食後に、「何か俺を利用できる仕事はないか」と言いましたら、まだ当時私は17歳ぐらいでしたので向こうから言うと「ショーハイ(小輩)、ショーハイ(小輩)」で通るくらいでした。「リーヴェンレン、ショーハイ。珍しいからいいよ。」早速その日から中華料理店に入りまして、食事はもちろん、ひもじい思いひとつするわけがなかったのですが、掃除、拭き掃除、整理整頓、それから皿洗い、いろいろ、考えるよりも仕事はありまして。それで寝泊まりができるんだからと私は一生懸命務めたわけですよ。まあそういう風に務めると愛着というのが出てくるんでしょう。まあその点は良かったのですが、隊舎が「金丸が中華料理店におる」と噂が広まりまして毎日のように2、3人で私に面会に来るんです。「金丸、何か残り物でもいいから何とかならんか」と。最初のうちはそれこそ残飯なら構わないだろうとジャングイが、ジャングイというと主人ですが、ジャングイが言いますので最初のうちはそれを食べさせておったわけです。そうしましたら2、3人が4、5人、4、5人が5、6人と人数が増えて、しかも毎日のように来るようになったわけです。さすがに私も店と同僚との板挟みで。ジャングイは「気にせんでもいいが」と最初のうちは言ってましたけれども、さすがにその状態には正規の来客に目障りになるということになりまして私もそこを仕方なく辞めたわけです。
それから私の放浪生活というのが色々と変わりました。馬追い、羊追い、それから豆腐店、洋服仕立屋の小間使い、日用品商店の店員、まあ数え合わせますと一口に言われんような色々な仕事に就きまして。そうこうするうちに一月経ち、二月経ち…段々段々中国人と同時に寝起きをするもんですから、中国人がどのような中国人だという、本当の中国人というのをその間にじっくり見させてもらいました。まあ話しても噴き出すような話まであるし、また八路軍に危うく入隊しかかった時にある女性から救われて、それが縁で危ないところを八路軍の兵士にさせられなかったという、今でも忘れようとしても忘れられないような思い出というのがずーっと延々と続いたわけです。
しかも4月から5月頃には国府軍から、国府軍というと蔣介石軍ですね、ロシア軍が4月に引き上げると同時に一晩のうちにドンドンパチパチがありまして、朝起きてみましたら国府軍の代わりに、代わった兵隊がおりました。いわゆる共産軍、八路軍ですね。小学校の五、六年生ぐらいの子供が大人の軍服を着て三八銃をぶら下げて、そして市内をずーっと3人、4人って一塊になって町を巡回しておるわけです。これは24時間だったです。その姿を見た時に我々もですが日本邦人は、もうこれは、特にあの戦前から中国の共産党というのは追い詰めちゃったから。バセンザン(馬占山)に至っては何度も殺害し遺体も掘り起こされたというような人もおるくらい共産軍には痛手を負わせたわけですが。その分子がいま目の前を、チチハル市内をどこにいっても銃をぶら下げておる。しかし八路軍が入ってからチチハル(斉斉哈爾)市街というのはものすごく治安が良くなりました。もちろん強盗や強姦、ランチバ(乱痴罵?)行動なんて全くありませんでした。しかも日本人が困っておればそれを救済するように徹底的に八路軍は日本人を庇ってくれました。
しかし酷い面もありました。それは日本人に対してではなくて中国人同士です。5月頃になりますと蒋介石軍に加入しておった国府軍の兵隊が、家族がチチハル(斉斉哈爾)におるもんですから身を変装して家族の中にひっそりと帰ってくるわけです。そうしますと近所の人が警察に密告通報するわけです。まあ金がなんぼか頂けよったんでしょう。そういった人たちが次々と摘発され民衆裁判によって処刑をされておりました。その民衆裁判というのも結局、私だけでも十数回、多い時には6、7人くらいが一編に銃殺刑というのも見ました。あっさりした刑場でした。まあそういうような、今でこそ思い出してもあのようなことを、それが日本人同士でないだけに何の感情もなく見られたわけですが、一度は20人ぐらいのまとめた銃殺はリューサ(龍沙)公園という公園がありまして、そこに杭を打って縛られて20人ぐらいの銃殺をされたんですが、その中に日本人が3人混じっておりました。銃殺があった直後にかなりの日本人が一目散にその柱に括りつけて倒れている日本人のところに駆け寄って、それこそその縄をほどいて必死の状態で連れ去って帰ったという目撃をしました。朝鮮人も何人かおるし、あとは殆ど中国人、その人たちはたしか夕方まで放って置かれたという話を後で聞きました。とにかく「日本人は日本人同士で護ろう」が合言葉だったわけです。
まあそういうような事で色々な難儀はありましたけれども、私個人の場合は日本人が1人もいないフラルキ(富拉爾基)とかコウコウケイ(昂昂渓)、ああいうような所に勤めにいくことがありましたが。ノンコウ(嫩江)というのがありまして、チチハル(斉斉哈爾)にも支流がありましたが、フラルキ(富拉爾基)というところにノンコウ(嫩江)という、これはやっぱり川幅が300mくらいありますか、そこのノンコウ(嫩江)を泳ぎ渡った経験がありますが、これは「日本人がこの河を渡る」と、相当ニュースが入ったらしくて土手やら河原にはかなりな見物人がおるなかを泳いで、3人でしたが、2人で泳いで1人は全部私たちの衣服を預かってそして渡し舟で対岸まで行きましたが。私たち2人はお金がなかったので泳ぐことにした。そうしましたら中国人っていうのは満州に限らず中国大陸でも同じように泳ぐってことはあまりしないらしいんです。なぜか、その理由は知りません。それでこの河を、300mもある、しかもかなり流れも早いのに2人で泳いで渡ったのは昨日のように克明に憶えています。まあ今いってみれば、その時の状況をみた私と同年代か小学生くらいは何名かおるだろうと思います。まあそのようなことをしまして念願の、そのデマが「4月には帰られる」、4月になったら「6月になったらしい」、6月になったら「8月だ」、8月からは今度は9月だろうか、10月だろうか。まあそのような頃に私は7月の終わりに隊舎に一遍帰りましたら隊舎では病人やらもう体の衰弱しておるような者がかなり多かったのですが、「今度は9月には引き揚げっていうことが本決まりになった」と私が言いましたら、それを確認するために3、4人が町に使いをやられて、そして帰ってくるなり「金丸の言うたことは本当だ。しかも9月の初めに町方面から順次帰る」と。
引き揚げ準備~帰れない人たち
チチハル(斉斉哈爾)に当時ですね、日本人が各地から終戦当時、さっき言いました引き揚げ列車で帰ってきてチチハル(斉斉哈爾)に避難してきた人が合わせてやっぱり3万人くらいだったんでしょうか。都市としてはチチハル(斉斉哈爾)というところは北満のほうでもあるし、あまり、歴史は古いところですけれども日本人はそこはあまり、ハルピン(哈爾濱)まではおりましたがハルピン(哈爾濱)からまたさらに北ですから、あまり賑わった都市ではなかったので引き揚げる時期にはやっぱり3万人前後だったと記憶しております。そういった町の人たちを優先的に帰すのだと。もちろん駅方面は我々青年たちが殆んど勤めておったわけですから。駅の務めから貨物、荷物、そういったようなのを我々若い者がですね。だから一番最後になるということで、とにかく帰れるということを隊舎の(皆が)知ってからもうそれこそてんやわんやで、もう今度のはデマじゃなくて本決まりだということが確定したので「あと50日目だ、50日ぐらいだ」と。そういうような希望があるまでは元気がある者もかなりバタバタと倒れていきました。
病気になりましても医者はおるんですけれども薬が無い、極端に言えば体温計ひとつ無い。体温計などは私たちは終戦当時、9月、10月、11月とあの当時、ソ連に荷物を持って帰るのに積み込み作業をずっとしたわけです。その中に食料品、機械類、何でも関東軍の倉庫にあるものをそれぞれ滅茶苦茶に貨車積み込みをするときに、やっぱりポケットに入れて隠し持って帰ったというのが一番貴重なのが体温計だったわけです。体温計なら一箱12本入っているのをたとえば二箱ポケットに入れても目立たないわけです。病院に持っていったらそれこそ感謝された。しかし薬は無かったわけです。まあ栄養失調とか、特に胸部疾患ですね、胸部疾患は薬よりも栄養価が大事だということで、戦前はそれはもう特に結核患者なんかは、ああもう御馳走から御馳走で回復しておったというのが事実ですけれどももそんなのは無い。見殺しだったですね。それで私たちはそういったような人たちを、たとえば私たち同僚はもう当然ですが、社宅持ちの人たち、まあ娘さん、息子、息子でも小学生だとか。そういったような人たちが亡くなりますと、火葬はその頃はなかったんでしょうかね、みんな私たちの隊舎の若いところに依頼がきまして。でそれを掘る、掘って埋ける(いける=埋めるの同意語)っていうのがやっぱりボランティアのような状態じゃったわけです。しかしかなり掘らないとですね、その翌日は掘り返されておるわけです。やはり日本人の葬儀の習慣として、ある娘が亡くなったとするとその娘の大事にしておる着物、そういったものは着せて埋けると。今でもそういう風習は残っておりますね。棺桶に火葬して燃えるっていうことがわかっていながら大事な着物を入れる。埋葬するときにも何枚も重ねてですね、埋葬する。中国人はそれを知っとるもんですから、次の朝はもうスッポンポンにおるわけです。それが何て言いますかねえ、これはもう当時の中国というのは未開の地といいますか、そのようなところでした。そういうようなボランティアのような仕事やらもいろいろさしておったわけです。
結局9月18日が引き揚げ出発と決まってから、さあ引き揚げる準備を各家庭がしたわけです。私たちはそれが決まってから約300人ぐらいの若い者たちがそれぞれの家庭の希望によりまして荷物をもってもらうための、または病人がおって担架を担いでくださる者、子供たちがおって年寄りがおってその人たちをかろうて(=背負って)帰ってくれる者と、いろいろ用事がそれぞれ雑多でしたが。そういったところに配属になったわけです。私は、主人と奥様、それに年老いた老婆、それに子供が4人おりまして、一番上の女の子が小学校の五年生ぐらいでした。一番下の男の子はまだ生まれて2歳くらいか、3歳まではなっていなくて歩くには歩きよりましたがまあ荷物は持つことは出来ないくらいの計7人家族のところに、最初は2人で割り当てられたわけです。帰る時には担架を担いで、大分のえーあれは、(上を見て考えながら)ちょっとど忘れしましたが、私と仲良しだった者と組んでそうしようということで。まあそうこうするうちに18日に帰るって決まってから毎日毎日、日本人会の幹部連中が集まりましていろいろ計画を立てるそのなかに、医者が見放した病人、それと回復のない病人とか、または手のあまり要るような高齢者、そういった者をどうするかというような協議が一番難しいことだったらしいです。結果的には安楽死ということで落ち着きまして。私のところの老婆はその、老婆じゃない、奥さんがその対象人物にされまして、写真ではふくよかなご婦人でしたがその時はもう骨と皮、それこそもうゴツゴツしたですね、頭の冴えっていうのは全く落ちていなくていろいろと会話もできる人だったですが、もうそれこそこれでも女性かというくらいの痩せ方でした。私はそれをもう一人の、何とか(名前は)忘れましたがそれと担架を担ぐ予定だったんですが、結果的には8月15日が帰れるんだという数日前に八路軍から毎日のように日本人通訳を連れてきて妙な話をしました。「皆さんたちが今度日本に帰られるのは良かったですね。はっきりと日にちまで決まって良かったですね。十分に気をつけて帰りなさいよ。」そこまでは良かったんですが、「ところで一つお願いがある」と言いながら「満18歳以上、25歳までの独身男性は全て残ってもらいたい」。それはどういう事かと言いますと「現在我々は国府軍と戦闘状態にある」と。「チチハル(斉斉哈爾)と新京との中間くらいに現在激戦中である」と。「その後ますます激戦になると想定ができる。そこでその方たちにお願いしたいのは、食料運搬とか負傷人を後方に連れて帰るとか、また弾薬補充のための運搬連中とか、
しかし今までにそういう話は全くありませんでしたので急に言われて動揺したわけです。結果的には私ともう一人の連れ、担架を担ぐはずの同僚が。私は満では18までには3カ月足らんかったわけです。それで帰国組にされたわけですが、もう一人の、多田っていう人やったかな?その男は満18を過ぎておったがために残されたわけです。それで1人じゃ担架が持てないとそういうような塩梅で御主人の納得のもとに安楽死というふうにして、なったわけですが。たまたまですね、夜中にトイレに行きまして帰りました時に細い声で「金丸さん、金丸さん」と呼ばれましたので「なんか御用でしょうか?」と近寄りましたら御主人が傍におられましたけれども毎夜の疲れでもうぐっすりと寝込んでおられましたので「そこにある水を飲ませてくれ」と。まあ、あの水差しに入っておりましたのを飲ませてあげたんですが、水を飲まれたら「ありがとうございました」とお礼を言われて(声を震わせて)「金丸さんは郷里はどこか」と訊かれるので「私は宮崎だ」と答えましたら「ああ宮崎ですか。私は熊本です」と。「同じ九州で懐かしいですね」と言われて、(感極まって泣きそうな様子)「帰るときは私が役に立たないから子どもたちをね」と哀願されるように言われました。(一瞬の沈黙の後、首を振りながら)忘れることはできません。明日は安楽死されるとわかっておる人の最期の私との会話だったのです。
翌日早朝、医者が看護婦同行でさっそく処置が始まりました。私は傍におって見ておりましたが医者と看護士さんの背中の後ろだったのでどのような処置だったかは私には見えません。御主人がニコニコ笑いながら「しばらく休みなさいよ。疲れも取れるからね」と優しい声で夫人に語られたのです。3分とかからなかったでしょうか。眠るような姿で、今まで元気、元気じゃない、気もハッキリ、言葉もハキハキ言われた御夫人がもう亡骸となっておったわけです。そして夕方、御主人と二人であるところまで運びまして、野っ原ですが、そこで火葬を頼んで帰りました。翌朝早く遺骨を拾いに御主人と行きまして、その時御主人が遺骨を箱に入れながら大泣きに泣きました。男泣きでしょう。まあそういうような悲しいことなんかも色々と。まあ忘れられないような体験でございました。
引き揚げ列車~引き揚げ船、博多へ
結果的に9月18日の朝暗いうちに皆さんがある大きな広場に集合しまして。そしてそれぞれ用意されておったんでしょう、腕章をですね(腕章を腕に嵌める仕草)腕章に書いてあるわけです。それには“日本人俘虜第〇号、チチハル第〇号”それで名前まで書いてあったわけです。それをみんな各自1人1人。そして第〇大隊、〇中隊、〇小隊、〇分隊と細部に分けられまして。そして最終的に1個分隊、約16所帯、それで途中にいざというような時があったらこの腕章とそれとお互いに連絡を密にしながらとにかく船に乗るまではお互いがお互いを監視しながらと色々な細部の説明を受けましてね、で駅まで歩いて行ったわけです。
駅に到着しましたら、うーん(首を傾げながら)今まで見た事のないようなプラットホームのところで。私たちが職務として勤めておったプラットホームでなくて貨物のプラットでもなかったのですが、ああいったようなの、何ていうかですね、満鉄はたっぷりとホームを持っていましたからその内の一つだったんでしょう。そこで身体検査を受けました。その身体検査というのは徹底的な荷物の検査からです。まず男は男、女は女、一列に並びまして。女は女でそれぞれあったようですが、まず病人の担架、それに握り飯、そういった物からですね、荷物の検査。持って帰る物に何か入れとらんかとか、わざわざ荷解きをして調べるわけですが男はともかくも、女の場合はたいがい男装するために髪の毛を短くしておる人はともかくも、当たり前に髪を結ったりした人なんかは頭の毛をこうこう、こうこう(右手を頭にやって上下左右に振り回す様子)混ぜくったりですね、着物は当然ながら女の一番大事な裾まで手を入れてですね、調べておりました。そこまでしなきゃならなかったのかと。後でのことですが町方面(の人たち)が帰るときに、私たちは若くて在満時間も短くてそんなケチケチするようなスコタンだったんですけれども、5年、10年と在満の人たちはそれこそ大臣クラスの社宅が渡たっとって、やはり下女、下男そして小さいボイラーまであるというような、これも日本人住宅というのは相当な、まあそれがまあ日本人のいい面か悪い面か知りませんけれどまあそういうような事じゃったんです。そういったような人たちはですね、持って帰るお金も決まっとるわけです。何百円だったでしょうかね、それ以上はその場で取り上げるわけです。あー憶えとりません金額は。私なんかはもうほとんどゼロに近いくらいでしたけれども。金だけじゃなくて宝石類とか貴金属とかそういった物を、女の隠し場所っていうのはやはり、まあハッキリとは言われませんけれどわかるわけですね。それを町の人たちがそんなものに替えとったわけです。駅関係の人ではなくて町方面の人のときには多量に発見されたそうです。だから我々のときも特に女性の場合はそうだろうというようなことで調べられたんでしょうね。有難迷惑でしたでしょう。
さあそれがですね、やがて終わる頃にまあそうですね、20mくらい離れた列だったですが大騒ぎがありました。1人の男が数名の兵士に殴られたり踏んだり蹴ったり。そして土下座まで鼻血を出して土下座までひれ伏して謝っておるんです。女房や子供たちはワァワァ泣いておりました。「お前は残留だ」とどっかへ連れて行きました。後でわかったことですがその人がある写真を持っておったらしいんです。その写真が、日本兵が中国人の首を日本刀で打ち首する寸前の写真じゃったらしいんです。それで引率者の幹部連中が色々執り成しをしたようでしたけれども(首を振りながら)ただ申し訳は認められずにどこにどうして連れ去ってどういうような処分を受けたのか知る由もありませんでした。ただトラブルはそれのみでした。
そして今度、さあ列車に、乗ろうとする列車が来ましたがその列車を見て驚きました。一等車、二等車、高齢者や病人用に寝台車まで連結してあって三等車なんてものは一両も見ませんでした。その点は私たちなんかが常に見慣れた、どういうような人が乗るような列車だという事は百も承知しておりました、そういうようなのがずらりと自分たちの前に来てそしてそれに乗ったわけです。そうしましたら出発をする時に大きな垂れ幕にですね「長い間皆さんご苦労さま。無事に日本にお帰りなさい。無事を祈っております。日本民主国家万歳」と大きな垂れ幕があちらこちらに垂れ下がっておるわけです。しかも音楽が流れておりました。蛍の光でした。ほとんど全員がその時の感動というものに、感動させられてですね、今まで苛めた連中がこんなようにして見送ってくれるのかというふうに全日本人は感動しました。そして列車は滑るように出発したわけです。そして途中で我々が停まる駅というのはまったく用がないので次から次と走りっぱなしで列車は走ったわけです。もう列車内ではですね、歌がでたりなんたりで楽しい。昨日までに辛かったことなんぞはもう昔の夢のようだというような塩梅じゃったわけです。
そこまでは良かったのですが、ある所で列車が止まりまして「これから先は歩くんだ」ということでした。歩くっていうて、そりゃもう大変なことだから、しかし線路が外されていて枕木も掘り起こされておるんです。枕木がゴロゴロしておって線路がまあ斜めに置かれたり、もうとにかくアラバッチョに?掘り起こした、そしてそれがその道であって小さい子どもさんなんかはやっと跨いで歩くというようなまあ道ではないわけですが、そこを約二千数百名がですね歩くわけです。最初のうちは歩くよりしょうがないから黙々と歩いておるわけです。しかし手には手に、肩は肩に一杯の荷物を持っておるわけです。大事なものを、何一つとして要らないものじゃないわけです。歩くたびにですね、あるとこらへんからくると疲れて手からずり落ちるんです。落とすんじゃなくて手がしびれたりなんたりでずり落ちるんです。あるいはヨチヨチ歩く子どもが歩けなくなって座りこむと、何かを捨てんことには子どもが抱けない。そういうようなのでポタンポタンとそれこそ見事な荷物が落ちるわけです。そうしますと両側を中国人たちが何か祭りでも見てるんじゃないかというような状態でずーっと見てるわけです。その人数がですね相当な人数でした。その荷物が落ちたならば、我先にと駆け寄って早い者勝ちに持ち去っていくわけです。あれよあれよという間もないんです。もちろん両側を八路軍の兵隊が約50m間隔で我々を監視しながら護衛しておるんですけれども、中国人が持っておる物を奪い取ったのではなくて日本人が仕方なく理由はともあれ捨てたと。それには何ら口をつかないわけです。私が、いま家にかなりの量の資料を持っておりますが、その部分がその資料には書いてあります。中共軍の方から引き揚げてきた人の荷物というのはコロ島(葫蘆島)で乗船する時にはほとんど無に等しい。それはもう大連から帰る人、奉天から帰る人、ダイセッキョウ(大石橋)とかキンシュウ(錦州)、まあ新京あたり、また新京なんかは国府軍の地区でしたからまあ乗り換えがなかったのかなんか知りませんけれども。チチハル(斉斉哈爾)、ボタンコウ(牡丹江)、ハルピン(哈爾濱)、ここらは我々が帰る時はもう共産軍でドンドンパチパチのところを帰るわけですから、そんなのは最初からまあわかっておりましたけれども、まさか歩くというようなことは夢にも聞いておりませんでした。それが荷物をポタポタ落としてあまり荷物が減ったのはその時が理由じゃったとものの本にも書いてあります。結局、約12kmということじゃったらしいのですが歩く時間は5時間歩きました。若い者ばかりじゃなくて休憩一つ無いわけです。そして第二松花江というところで小さい小舟がいっぱい無数に係留してありまして、平均して10人くらい乗れるんだったと思いますが、それに乗ってエンジン付きの小舟でピストン輸送で河を渡ったのがもうすでに夕暮れでした。それで夕暮れで、もう一晩これはここで河原で夜が明けるまでせんことには、やっぱりあの何分隊、何小隊というそれもてんでんばらばらだったので。そして隊を編成するためには暗くちゃどうもならんと。翌日にしようということでその日は河原で野宿をしたわけです。野宿をしましたら雨がポツリンポツリン来ました。結局大降りではなかったのですが誰も雨具一つ持っとる者はいないんです。まあ濡れるほどの雨でもなかったので皆さんそれぞれ眠った人もおれば、広い河原で夜が明けたわけです。
そうしましたら編成を組む時に国府軍の方からある要望が来たわけです。その要望といいますのがですね、「満二十歳から三十歳くらいの女性全員を国府軍の慰安婦としてだしてくれ」と。
そういう触れがまわってきまして。まあ何ということかと。帰れるものなら引き返したいと。しかし後ろの方はもう、私なんかが泳いだショウカコウ(松花江)、ノンコウ(嫩江)よりもさらに、第二松花江ですから川幅は広いし泳いで帰る者は1人もおらない。前進もできない。どうしたものかと。それこそもうあちらこちらで会議を開き幹部たちがいろいろ説得しますけれども、応じるまでは列車を出さないと。それこそけんもほろろだったのです。そうしましたら約二千数百名の団体のなかで「自分たちは引き揚げるまで身を売って生活をしてきた。自分たちが内地に帰っても肩身の狭い思いをするので皆さんたちのために代わって残ります」と十数名の女性が自ら名乗り出てですね、それぞれ小銭を出しあっておられたようでした。その話が決まったら途端に列車が来たわけです。その列車たるや無蓋車、有蓋車がいくつかありましたが殆どが無蓋車。無蓋車ならまだいいんですけど、大きな材木を運ぶとかトラック類を運ぶとかいうプラットといって車輪があって上はのっぺらぼうです。ところどころにあれがありました、棒を立てるところがあるんです。棒を立てるところがあっても棒はないんです。それを張り巡らせるロープもないんです。しかたなく荷物を真ん中のほうにズーっと積みまして真ん中寄りを子ども、女性、病人、高齢者。それを荷物を抱くように両方から手を握ってですね、転落しないように。で、我々若い者はそれを今度は鎖をですね、手と手と鎖を(両手を隣と結ぶ仕草)ぐるーっと外まわりに、中のほうが落ちんように。ところが列車というのはレールを走ってるうちはいいですけれども、分岐、列車が右にいったり左にいったりレールが分かれる分岐点、あの所に行く時には(身体を揺らして)ガクッ。(インタビュワーに)おわかりでしょ。急に地震の激しい揺れに(全身を震わせて)グラグラッとするわけです。客車であったらそれが、色々と逃げるためのスプリングとかああいったのがいろいろとどこにもあって、車両というのはそれはもう最高の車両でしたからあったんですけども。貨物を載せる、特にプラットなんかはですね、そういった振動を止める設備なんかは全く無いわけです。ガタガタガターッ。(激しく揺れる様子で)転落事故というのはありませんでした、おかげで。しかし雨が降りだしました。もう土砂降り、しばらくは土砂降りでしたがずぶ濡れになるほどの一歩手前に止んでくれたのは有難かったわけです。
そうしましたらですね、駅でもなんでも無いところで急に列車が停まったんです。そうしたら監視兵たちが口々に「この先に時として列車妨害が起きる。仕方がないので機関士に金を握らせたら強引に通過してくれる。どうするか?」というふうに監視兵たちが言うわけです。どうせゆ強請じゃないかと十人が十人同じような気持ちでしたけれども金で解決できるならばというところでまたいくらかみんなが出しあっていたようでした。それで無事にそれからハルヨシ?を通ってシンキョウ(新京)で4日間逗留しました。その逗留が何の意味かわかりませんがそれがキンシュウ(錦州)にいてから4日間の逗留というのは意味がわかったわけですが、4日目に再度シンキョウ(新京)から列車に乗ったんですが、その時はプラットはありませんでしたけれども無蓋車でした。殆どが無蓋車でした。貨物列車。まあとにかくこの貨車が南の方にいけばそれでいいんだ、仕方があろうかという風にみんな考えておりましたので、まあ無蓋車だからどうのこうのという気持ちはさらさらありませんでした。それでシンキョウ(新京)を出発してホウテン(奉天)に1時間くらいプラットホームのところで、列車待ちかなんかだったんでしょう。その時キツリン(吉林)の方に行く前にホウテン(奉天)で5時間くらい駅前の公園で写真を撮っておりますが、あー記憶がありましたけれども、私たちが帰る時に見たホウテン(奉天)駅は空襲を受けて爆弾を受けてかなり傷んだホウテン(奉天)駅でありました。
1時間後にそのまま続けてキンシュウ(錦州)までぶっ通しで、キンシュウ(錦州)に着いたのが、うーん時間は憶えておりませんが、このキンシュウ(錦州)で約10日ほど保留されたわけです。これはやっぱり全満からコロトウ(葫蘆島)に帰るということで船待ちだったんです、順番待ち。それが止められたんじゃなくて船待ち、しばらく順番待ちという触れがあったときにあまり残念な気持ちはありませんでした。いずれそれが1週間であれ10日であれその日が来たら船に乗れるんだという希望がありましたので。その時に食料をどうするか、いろいろな問題がありまして、私たちがそのとめてあるところは各方面から大きな鉄条網が張ってありまして、そこの中にみんな保留、滞留しておるわけです。われわればっかりじゃなくてですね、ボタンコウ(牡丹江)だとかハルピン(哈爾濱)だとかチャムス(佳木斯)だとか、そういったような殆ど北満からの人たちばっかりのようでしたがおるわけ、そこにずーっと網があって、そこに中国人が物を売りに来るんです。まずは饅頭、食料品、煙草類、いろいろな物ですね、アルコール、白酒(パイチュウ)です。そういった物を、それを買うことについては監視する者はいないので思う存分に買えたんです。値段も安かったんじゃない、高いなという思いはありましたけどそれ以外の物がないわけです。それで私は奥さんを安楽死させた主人と老婆、4人の子どもたちを、私は連れて帰るのが役目であったから、私はその子たちを大事にしておりましたので。全て金のいることは主人が全て、家族の一員として私の代わりを消費してくれたわけです。
ほんで10日目に船に乗る、明日はいよいよ乗船する日だというのが決まった時に嬉しいことが2つあったんですよ。9月18日にチチハル(斉斉哈爾)に残留されていた同僚がですね、殆ど全員が帰ってきたわけです。なんかあの仮病を使ったらしいですね。まあ結果的には国際情勢が「日本人を残留させておる」と国際的な問題がおこったらしくて、そういう事をしてはいけないという国際的な命令が出たらしいんですけれども、その連中は仮病を使ったら全員が認められた。それと今度はあの第二松花江で残留した十数名の女性全員がですね、私たちのところに一応同席をして、その女性たちは船も一緒でした。ただ残留された同窓たちは10日ほどやっぱり乗船待ちらしいということでまあそのまま錦州に残ることになりました。荷物の検査というのはありませんでしたがその時にですね、あれはDDTとかいうなんか、あれを頭のてっぺんからですね、それこそ白いメリケン粉かなんかをぶっかけられるような風でですね、女子(おなご)なんかこうやってタオルで(頭にほっかむりする仕草)5時間くらいはしばっとけというような塩梅で。虱とりですね。
ほんで乗船する船がそこに着いとったんですが、その船が3,000トンの雲仙丸といってそれは立派な客船だったです。私なんかは渡満するときには、下関から釜山まで行くときには同じ客船でもコウアン(興安)丸という、5,000トンだと聞いておりましたが、その3,000トンの立派な客船に乗ったわけですが、乗ったら船室がこんな風にして棚になっとるわけです。天井がもう上の方は大人が(頭を低くして)こんなせんことには満足に立たれんぐらいの背幅ですね。それに二千数百人と聞いておりましたが、定員は五百人と書いてあったけれども実際は三千人近い人員じゃったらしんです。しかも北満のほうから来たんだからここまで来るのに並大抵のことじゃないということを考案されて特別に客船を変更になったそうです。出航直前になりまして京都の舞鶴港にってことに決まっておりましたが、出航直前になって九州の博多ということに変更になりました。それはもう帰れるんだから九州だろうが北海道だろうが内地の土を踏めばいいんだから、とにかくトラブルも何もなくてですね、そしてあの何時頃に出航したのかわかりませんが昼過ぎてくらいじゃったかなと思います。
結局博多に上陸しましたときにあそこでもう1回白い粉を受けたんだったかはっきり記憶しておりませんが、あそこでお金を百円、それから日本国内1か月通用する国鉄の乗車券を1枚、食事券を1枚、それぞれ個人個人に手渡されて、第〇大隊、第〇中隊、第〇小隊の団体もその時点で解散をしたわけです。最期に残ったのはもう私と同じ高橋というのがおりましたがそれと二人で、博多の町をいうのをですねとてもじゃないがそれこそ今度の津波で流された北海道のあれと同じような博多の町であったのを記憶しております。結局、日豊線回りで私は宮崎に帰りつきました。帰り着いたときはえー来客中じゃったようでしたが「ただいま帰りました」と家の前に立った時に、立ち姿だった母親は(少し頬を緩める様子で)わーっと吃驚してへたへたと座り込んだのを憶えております。来客中の父は私を見てただ「おー、おー、おー」とその言葉だけであとは喜んでくれました。まあーそれがだいたいの私の終戦から引き揚げるまでの概略であります。
聞き手:ありがとうございます。1点だけ、最初の所から送ってくれたのは共産軍?
終戦の時はですね、国府軍です。というのは共産軍と国府軍はその時に既に、
聞き手:戦闘?
ええ。
聞き手:最初の列車を用意してくれたのは?
中共ですね。
聞き手:中共軍が垂れ幕を出して立派な列車で送ってくれたと?
はい。
聞き手:で歩いた途中の列車は国府軍?
歩いて河を渡った先はもう蒋介石軍、国府軍。共産軍から国府軍に引き渡されたわけです。その間ドンドンパチパチの砲声なんかもやっぱり国際で決められておったんでしょうね、休戦状態にということで。
聞き手:ありがとうございました。
体験記録
- 取材日 年 月日 (miniDV 60min*2)
- 動画リンク──
- 人物や情景など──
- 持ち帰った物、残された物──
- 記憶を描いた絵、地図、造形など──
- 手記や本にまとめた体験手記(史料館受領)─
参考資料
- 地図 ───
- 年表 ───
戦場体験放映保存の会 事務局
■お問い合わせはこちらへ
email: senjyou@notnet.jp
tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)
■アクセス
〒114-0023 東京都北区滝野川6-82-2
JR埼京線「板橋駅」から徒歩5分
都営三田線「新板橋駅」から徒歩7分
Copyright(c) JVVAP. All Rights Reserved.