稲村 繁さん
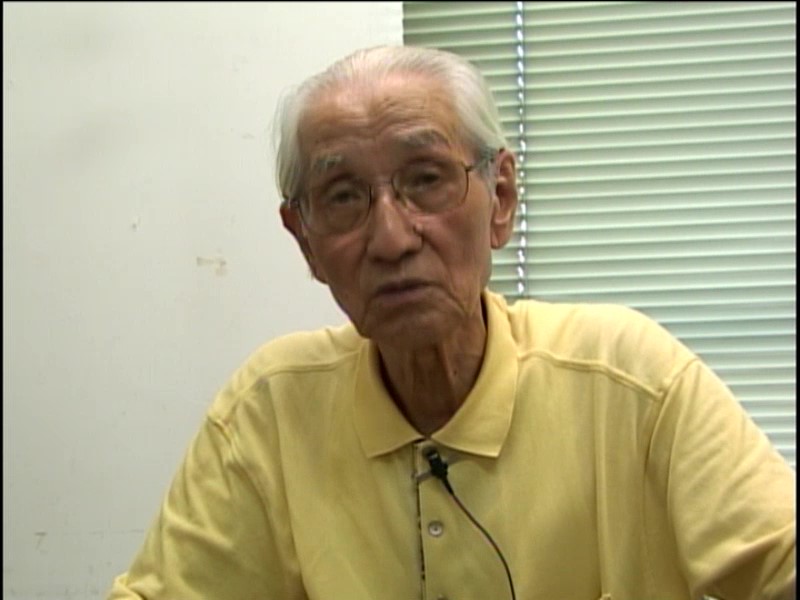
| 生年月日 | 1921(大正10)年8月21日生 |
|---|---|
| 本籍地(当時) | 東京都 |
| 所属 | |
| 所属部隊 | 電信第1連隊(東部88部隊)→第800部隊(関東軍第2航空軍)→ハルピン航空連隊、敗戦時の所属は第2航空通信連隊(満洲996部隊) |
| 兵科 | |
| 最終階級 |
プロフィール
1921(大正10)年8月21日、東京生まれ
1942(昭和17)年9月に早稲田大学を繰上卒業し臨時徴兵検査を受検
10月1日に電信第1連隊(東部88部隊)へ現役入営
幹部候補生に合格し甲種幹部候補生として陸軍通信学校で教育を受ける
電信第1連隊へ原隊復帰し、見習士官・少尉任官を経て関東軍に転属
第800部隊(関東軍第2航空軍)、ハルピン航空連隊、敗戦時の所属は第2航空通信連隊(満洲996部隊)。
ブリヤート・モンゴル州でシベリア抑留を経験
1948(昭和23)年5月29日 復員
戦後、「戦争体験を語り継ぐ会」で会長と語り部の活動を行った
インタビュー記録
初めに
私は「戦争体験を語り継ぐ会」の会長及び語り部をやってます。この会は、今年で創立20周年を迎える組織なんです。この会ができましたいきさつは、戦争体験者が20年前にたくさんいて、新聞社にいろんな投書をしてきたわけです。その投書が非常に多かったんで、朝日新聞の方から、戦争体験をされてる方が組織を作って「戦争体験を語り継ぐ会」を発足させたらどうかということから出来上がった会で、色々な場所に行って戦争体験を語り継いで今日まで来ました。私がこの会の会長をやりますのは3代目なんですけれども、初めにたくさんおられた方がやはり高年齢化で、だんだん亡くなってきたんで、現在私が会長をやってます。これから、どういうことを皆さん方にお話ししたかを、お話ししたいと思います。
経歴
私は、1921年、まあ大正10年なんですが、大正10年生まれで、現在、満84歳です。
大正時代は、今の平和な時代と違って、私が生まれた年には総理大臣が東京駅で殺されたと(註:原敬暗殺事件のこと)、そういう決して平和な時代ではなかったんです。それで、大正12年には関東大震災があり、昭和に入っても東北地方だとか北海道が大飢饉に見舞われたりと、そういう様に非常に不安定な昭和の初期だったんです。
皆さん方ご存じのように、2.26事件だとか5.15事件だとか、非常に今から考えると不思議なくらい不穏な、決して平和ではない時代だったんです。そうして、1931年、いわゆる15年戦争という戦争が始まったわけです。満洲の1農村のところでボヤみたいな戦争、事件が起きて(註:満洲事変のこと)、そのボヤがいつの間にか大きな火事になって、15年間も続いた戦争になったわけです。
ちょうど今年は60年目です。終戦して。60年前の今日、私はどこにいたんだろうと振り返ってみますと、なんとシベリアのブリヤート・モンゴル州(註:ブリヤート・モンゴル・ソビエト社会主義自治共和国のことか。現在のブリヤート共和国。)という非常に寒いところにおりました。1500人の兵隊とともに、私は捕虜としてブリヤート・モンゴル州の収容所にいたわけです。振り返ってみまして、どうしてそういう風になったのか、簡単にお話ししていきたいと思います。
私は早稲田(早稲田大学)に行っておりましたけれども、卒業が6か月繰り上がりまして、昭和17年9月に卒業し、10月1日に現役で軍隊に入りました。
軍隊で初年兵教育を受け、そうして3か月の初年兵教育が終わって、当時は(甲種)幹部候補生、どうしても幹部候補生になるということで、幹部候補生試験を受けて合格し、士官学校(註:予備士官学校、通信兵なので実際には陸軍通信学校に行っている)へ行って、そこで半年訓練を受け、将校となって、今度は相模原の部隊から満洲の関東軍に転属になりました。
当時の、我々時代の学生時代というものは、中学校は5年制で、そして、我々は皆中学校を卒業して、ほとんどの生徒が就職なりなんかして、高等学校、大学行くのはごくわずか、1割にも満たないのが大学に行った時代でした。そうして、我々は、もう31年(1931年)から戦争が始まってましたんで、中学校では教練という学科があって、各中学校には陸軍から将校が2、3名来て、教練という時間に、鉄砲の担ぎ方、鉄砲の撃ち方、歩き方、走り方、そういう軍隊に入ってから教わることを中学時代から教わっていた時代です。今のように、我々は、皆さん方が自由を謳歌して自分の好きなことをやり、なんでもあるという現代とは違って、徴兵制というものがあり、20歳になると男子は全部検査を受けて、甲乙丙丁というようにランク付けされて、合格したものは皆軍隊に2年なり3年入って軍事教練を受けたわけです。
しかし、戦争が始まり、なお日米開戦というに、アメリカとの戦争が始まってからは、どんどんどんどん戦線、戦争が拡大して兵隊が足りなくなり、その20歳になるまで待っていられないんで、20歳の兵隊検査がとうとう最後には19歳に繰り上がった。また、中学5年生を卒業すれば兵隊になれる、いわゆる少年兵、こういう制度までできた。ですから、中学校に、5年生に卒業したら兵隊になってくれというような勧誘もされてた時代だったんです。そういうことで、随分少年兵になった中学生がいっぱいいたんです。私が言いたいのは、戦争が始まるとどうしても勝たなければならない、そのためには国としてはなんでもやるということなんです。そういうことで若い人たちは皆戦争に駆り出されたわけです。
皆さん方が知ってるように、昭和18年、神宮(註:明治神宮外苑競技場)に関東一円の大学生が皆集められて雨の中、東条陸軍大臣(註:総理大臣兼陸軍大臣)が「君たちは今日まではペンを持って勉強していただろうけれども、明日からはペンを銃に変えて国のために死んでくれ。」と、そういう風に言われたんです。これがいわゆる学徒出陣という名の元に残された歴史です。そういう時代で戦争はますます苛烈になり、内地に残ってる人は空襲を受け、兵隊じゃない一般の市民の人もどんどん、どんどん死んでいったわけです。
語り継ぐ意義
私がなぜ今頃になってこういう60、70年前のことを話すというのは、今の日本をよく考えてみると、私はもう日本は戦争に足を突っ込んでいるという認識でお話をしています。日本の自衛隊は、政府が軍隊ではないと言っても、世界各国は自衛隊を軍隊と見てるわけです。軍事費に使うお金は、世界でも10番以内に入るくらいの軍事費を自衛隊に使っているのが今の日本です。戦争で、日本はこの15年戦争で300万人の日本人が死にました。よその国ではこの戦争によって2000万人以上の人が死んだと言われています。そのためにはなんでもすると、そういうのが戦争なんです。戦争というものはそう難しいことではありません。勝つか負けるか、生きるか死ぬかというのは戦争の姿です。
色々お話したいこともたくさんありますけれども、私の経験をこれからお話ししますけれども、これからお話しするのは私の戦争体験であって、15年戦争に参加した兵隊は1人1人が違った戦争体験を持っています。ですから、これからお話しする私の話は私の戦争体験であって、他の人の戦争体験ではありません。ですから、私が体験した本当のことを皆さんにお話しします。
終戦前後からシベリアまで
先ほどお話しましたように、満州へ行って終戦を迎えたわけですが、ソ連と戦い、中国の兵隊と戦いながら、最後は、先ほどお話ししましたように、8月15日に負けてしまったわけです。この日本が負けることは、もう前から私どもがわかりました。なぜかというと、私の部隊は航空部隊(註:後述されるが996部隊のこと)で、通信網が皆、完備してましたから、長崎、広島に原爆が落ちた時、アメリカ軍の放送で、原子爆弾が落ちて、何十万人の兵隊、広島人の人や長崎の人が一瞬にして死んでしまったという放送を聞いた時に、「あー、もう日本はもう戦うことはなくて負けるな。」ということは予感してました。ですから、8月15日に日本が、負けたということを聞いても、特に驚きはしませんでした。ただ、「はあ、これで生きて日本に帰れる。」という気持ちはありました。ですから、兵隊に、「戦争は終わった。これから日本へ帰れる、だから命を大切にして帰る日を待とう」と。
そういうことで終戦を迎えましたけれども、皆さん方あまり知りませんけれども、戦争が終わって日本へ帰ってくると思ったのが、なんと満洲にいた日本の兵隊を含めて60万人の日本人がシベリアの国に2000カ所、2000カ所以上の収容所に連れて行かれて、何年にもわたって労働をしたわけです。そうして、なんと1割以上の、5万または10万とも称される日本の兵隊が、シベリアで死にました。戦争が終わって、なぜ60、そんな多くの日本人が死ななければならなかったのか、こういうことになったのは誰の責任なんだということで、我々は本当にシベリアの地で、地団太踏んで悔しがりました。
私は1500人の兵隊と共にシベリアの奥地に行きましたけれど、半年の間に500人の部下を死なせました。朝起きて、さあ食事をして作業に出ようと思った時に起きてこない兵隊がいると。起きろと言っても起きてこない兵隊は皆死んでたんです。夕べ一緒に床を取って寝た戦友が、翌日の朝起きてこない。よく見たら死んでた。そういう悲惨なとこでした。私がいたところは、6月に雪が降って(やんで?)8月には雪が降る、零下58度までの寒さを経験した非常に過酷なシベリアの収容所でした。
これは朝日新聞に出ました、私のシベリアの話の記事です。(朝日新聞「シベリア抑留苦難生々しく」を見せながら。(当該記事が発見できず。))ここに私の写真が出てます。これは、この写真(註:稲村さんがパンを持っている写真)が原稿ですけれども、ここに持っているこのパン、これは350グラムのバンです。これが我々捕虜に対して与えられた1日の主食なんですね。将校は、この350グラムではなくて、さらに少ない300グラムが将校に支給されたパンです。このこれだけのもので、零下30度という極寒の地で、伐採、石炭堀り、ダムの構築、鉄道での石炭の積み下ろし、こういうような重労働をさせられては、栄養失調になり、病気になり、死んでいくのが当たり前だったんですね。
この過酷な条件で耐えられなくなった自殺をする気の弱い兵隊もいました。今思いますと、この死んだ私の可愛い部下たちをどうしてこういう状態にしたか、誰の責任なんだということで、当時我々は、地団太踏んで悔しがったんですけれども、なんともいたしかたがない、そういう自由のない、希望のない、いつ返してくれるのかわからないという過酷な体験を積みました。
稲村さんが感じる戦争責任
ですから、私は、色々なところで戦争の責任について言及します。戦争責任、私は、昭和天皇にも戦争責任はあるということを断言して、各講演会でお話します。戦争が終わって、なぜ死ななきゃならなかったのか、誰がこういう事態を引きおったか。その例を引きますと、日米開戦、要するに米英に戦線布告した時に昭和天皇は詔勅を出しました。それに、曰く、「日本が、大東亜共栄圏で植民地の色々な人々を解放するために戦っているんだと。それに対して米英は邪魔をして、反対をして、我々の目的を達してないようにしていると。だから、米英に対して宣戦を布告するんだから、汝臣民、要するに国民はそのことをよくわきまえて日本のために働いてくれ。」と、こう開戦の詔勅に言ったわけ。
この同じ天皇が、8月15の終戦の時にも日本国民に対して詔勅を出しました。なんと言ったか。「戦局利にあらず。色々頑張ってきたけれども、原爆というどうにもならないような、一発で何十万人も殺すような爆弾を落とされてしまったと。これを放置すれば大和民族がなくなってしまう心配があると。だからポツダム宣言を受けるんだと、だから、大変だろうけれども頑張って祖国復興のために働いてくれ」と。同じ1人の天皇が開戦の時になんと言ったか、終戦の時になんと言ったか。同じ1人の天皇が戦いを始め、戦いを終わらせ、その間に300万人以上の日本人が死んでしまったという事実に対して、戦争責任がないとは私は思いません。
昔であれば、こんなことを言えばすぐ治安維持法という法律に引っかかって、すぐ私は投獄されてしまうでしょうけれども、ありがたいことに、今は、憲法があり、言論の自由が守られ、戦争責任を昭和天皇はあると叫んでも別に捕まることもないということはありがたいことだと思ってます。
語り継ぎの活動と稲村さんの思い
これから少し、私が今どういう活動をしているかということについてお話ししたいと思います。まあ60年前、70年前の私の辿ったことは、今までお話ししたようなことでお分かりと思いますが、私が今現在やっておりますのは、色々な小中高、大学へ行って、私の経験した体験を、今の時代にはそぐわないけれども、そういう事実があったんだということをお話して、こういうことからいろんなことを学んでもらいたいということから、色々な学校へ行ってお話してます。それが私の今の主とした活動です。もちろん50代60代ぐらいの戦争を知らない方々にも色々な公民館だとか色々な場所において、お話をしてますが、やはり私の1番お話したいのは、君たち若い人たちに、君たちのことなんだから、一生懸命私の話を聞いてもらって、これからの21世紀を生きていくための1つの参考にしてもらいたいと。そういうことからいろんなことを学校行ってお話してます。
生徒は非常によく聞いてくれてます。今の学校の教育で、幕末まではいろんな、明治維新のことまではよく教わるんですけれども、本当のこの近代史、昭和のどういうことがあった、大正の末期はどうだった、そういうような近代、超近代、1番身近な歴史についてはほとんど学校で教えていない、そういうことがよくわかります。それで、私は色々お話するんですけれども、話した、話す時に必ず、私の話を聞いたらば、どう思ったんだということを要求して、生徒から返事をもらいます。それが、これは一例ですが、ある東京の中学校で(註:学校から稲村さんに送られてきた手紙を見せながら)3年生約100人に対してお話をしました。そうしますと、やはり1人1人が私に手紙をよこします。その手紙を学校の担任の先生が要約してこう書いて、1組、2組、3組という風にして、これは私のところへ送ってきたもんです。ここにいろんなことが、生徒が私の話を聞いて、私は戦争のことをどう思うというような偽らない感想が書かれてます。この実物はちゃんと私のとこにあるんですが、これは担任の先生がそのクラスをまとめて、改めて「稲村さんへの手紙」ということで私のところへ送ってきたもんです。また、今日来ました、この手紙(実物をみせながら)も、私がつい先日、横浜のキリスト教会の信者の方にお話しまして、それを聞いてどういうふうに思ったかをこう書きつづった私への手紙です。
ですから、私がこのお話を続けていく1つの理由は、聞いてくださった方が、「本当に戦争とはどういうものか、平和のありがたさがどういうものか、そういうことがよくわかった。だからどうしなきゃならないと思う。」というようなことを書き綴って、私のとこへ(手紙が)帰ってくるわけです。ありがたいことだと私は思ってます。ですから、私が今やってることは決して無駄ではないんだという信念を持って、今続けているわけです。
色々戦時中のことをお話しします。中学生や小学生、学童疎開を知ってる子供もいません。小学生にお話ししますけれども、私たち戦争の時代、あれ戦争中の昔は、小学生は、空襲にあって死んでは困るんで、みんな田舎へ行って勉強したもんだと。それが、学童疎開と言って、お父さんやお母さんと別れて、田舎のお寺だとかそういうところに泊まって、そして勉強しました。そういうお話をしたり、また中学生あたりにも、君たちが今経験している中学校の生活なんてものは昔は全然なかったんだということから、今の平和を考えてくれということも言っています。灯火管制だとか空襲だとか、いろんなことはみんなこれから体験し得ないことなんですけれども、そういう過酷なことを体験しないように勉強してもらって、21世紀は君たちが担っているんだからということを叫んでいるわけです。
人それぞれ皆考えが違いますから、私へ帰ってくる手紙も色々違います。しかし、たとえ100人のうち1人でも2人でも、私の話すことを理解してもらってくれるならば、私の今やってるこの活動が決して無駄ではないという信念を持ってお話してます。
語り継ぎの工夫
大体その小学校、中学校、高校行くと内容が違いますし、語る言葉もみんな違います。それで、特に小学校では、この先ほどお見せしたこの食事分配のこのパン(稲村さんがパンを持っている写真を出して)これを実際に使った劇までやります。これは、捕虜生活でこの350グラムのパンを誰にでも分けてくれるんではなくて、ノルマというものがあって、ノルマっていうのはシベリアから帰ってきた帰還兵が広めた言葉なんです。ロシア語ですね、ノルマっていうのは(норма)。このノルマというものは、ある仕事をやるのに、1人の兵隊は1日に100個できるけれども、ある兵隊は70個しかできない兵隊もいる、ある手先の器用なものは150個作る兵隊もいると。そのノルマ100パーセントを基準にして、150パーセントやった兵隊にはこの350グラムのさらに半分のパンを余計にもらえると。100パーセントやらなかった兵隊はこのパンが少なくなるんだよと。こういうようにノルマによって食事の量が変えられてしまったというようなことがあるんです。
そのことを生徒たちに劇でやらせるわけです。ちょっとした例を申しますと、この食事分配の劇をやらせるのに15人ぐらいの役割を振りまして、150パーセントやった兵隊が、私は150パーセントをやったんだと、だからパンを余計くれという風に食事分配の時に主張すると。そうすると、そのパンは誰からその分を出すんだということになると、ある兵隊は、今日作業に休んだものは、この350グラムを全部丸々もらわないで、仕事しなかったんだから、そのものが負担すべきだという発言もあると。また、ある兵隊は、病気だからこそいっぱい食べてもらって早く元気になってもらわなきゃいけないと、こういう主張をする兵隊もいると。色々な意見を言うわけです。そういうことを実際に小学校、中学校の生徒に役を振りまして、やらせるわけです。病気で休んだ兵隊に役を振って、その兵隊は、私は休んだんだから、皆さん方がそうやって食事の量を言い争ってるのは見るに忍びないから私の分を供出します、という役割の病人の兵隊もいるわけです。そういうことは、シベリアの寒さをいくら口で言ってもわかりません。けれども、日常の主食がどうやって分配されるかを、こんな白い食パンであろうと実際にやってみると、「あー、日本の兵隊、捕虜になった兵隊は毎日の食事のパンの分配ですらそういういさかいが起きるんだな。」と、そういう現実が分かってもらえるからだと思うんです。で、この劇は非常にみんな嫌がるかと思いましたら、面白いことに、みんな、僕もやりたい、私もやりたいということで、その劇に出演することを希望する学生が非常に多いってことなんです。これは私もちょっとびっくりしたんですけれども、今の子供はそれだけ非常に自己主張って言いますか、自分を前面に出す、そういう積極性があるんだなとは思いました。えー、色々なことをお話ししましたけれども、こういうようなことで、今私は学校活動、そういうことをやっております。
稲村さんのメッセージ
まあ50歳代の人とか30歳代の人、または女性の方ばっかりの会合、そういうようなことで、色々お話しする内容は違いますけれども、要するに、皆さん方が今生きてるということ、これは厳然たる事実です。この生きてるということが当たり前ではないんだということを理解してもらいたい。
我々の時代はいろんな夢があった。私は小学校の時から学校の先生になりたかった。私は子供が好きだったんで、5人兄弟の長男坊だった。何しろ妹や弟の面倒見るのが忙しい。子供と遊ぶのが大好きで、学校の先生になろうと思って。しかし、当時はその夢をみんな捨てなきゃならない時代だったんです。いろんな夢を抱いたと思うんです。大学に入ったのも。しかし、その夢をみんな捨てなきゃならなかった時代なんです。今の時代は、自分のやりたいことはなんでもできるはずです。そういう時代をなくなし(無くし)てはいけない、だから私はこうやって叫んでるんだ、ということをぜひ理解してもらいたいと思います。以上です。
満洲での軍隊生活
聞き手:一応、お話のところでシベリアのところお話いただいたんですけど、シベリアに行く前の新京の部分とハルピンのとこでも、航空隊でやられてましたよね? そこら辺のお話もちょっとさせていただきたい。
満洲っていうのは、本来は中国の領土ですよね。それが日本軍部、そういうものから、いつの間にか満洲国っていうものを作ってしまって、事実上属国じゃありませんけれども、日本の関東軍という100万の軍隊が満州には駐留してたんです。外国に日本の軍隊が100万も駐留するっていうことは考えられますか。そういう既成事実になっちゃったんですね。ですから、満州には、先ほどお話しした東北地方だとかいろんな日本の農村の人を、村ぐるみ、この満州へ移住させて、開拓団、いわゆる農村を満州に展開したわけです。だから、満州の、まあ私、今日地図持ってきませんでしたけども、その地図には、もう国境地帯にいろんなもうその開拓団が入ってきて、その名前が何々長野だとか、何々岩手だとか何々宇都宮だとか、自分の出身の地をつく名前を付けた部落を満州の各地に、全満般にやったんです。そうして、なおかつその農民たちが安心して生活できるように、100万の関東軍が周りにいましたから、安心してその開拓にあたりはやったんです。ですから、私がハルピンに行ったのも、ハルピンにちゃんと日本の部隊がいたわけです。
寧安(註:ねいあん、現在の黒竜江省牡丹江市の南端。)という街にも日本のその996部隊という部隊があった。だから、全満にそういう日本の軍、兵隊がみんな駐留してたわけです。100万の関東軍ですよ。なぜかというと、内地は空襲受けても満洲は空襲受けない。1番の敵であると思ったソ連と、当時日ソ中立条約という条約があったわけです。要するにソ連と日本がお互いに侵略しないで中立を保とうという条約ができたから、満洲でソ連との国境があっても、そこから攻められるという心配はないから、爆撃が受けられないから内地でいるよりも満州の方が安心だったんですよ。東京だとか大都市は空襲を受けてんのに、満洲に住んでる人には空襲なんてないんですもん。ね。だから満州なら安心。あの安心して毎日暮らしてたんです。だから灯火管制もない。内地のあれは空襲を避けるために夜はみんな灯火管制するわけ。真っ暗になる。満洲は何もない。空襲を受けることないんだから。そういう時代ですから、全満に日本の部隊があったわけです。日本の。わかります?そういったその部隊の、フィリピン、要するにハルピンですか、ハルピンにも部隊がありましたから、私がそこへ転属になったと。それでまたそっから寧安というところへまた転属になって、そういうことです。
聞き手:その時に、あのやられた具体的な仕事だとか体験みたいなところ、もうちょっとお話し。
それはね、要するに軍隊生活で、戦争でやってませんからね。もう普通の軍隊生活、特に満洲行きましたのは、私は初年兵じゃない、もう将校ですからね、別にもう日常で、いつ攻めてこられても、ソ連とも戦ってないわけですから。ただ、中国だとかそういうとこが戦争状態に入ってても、なんら直接、日々戦争の心配はなかったです、自分の身が危なくなるとか。ですから、普通の要するに軍隊生活です。食料も内地の部隊と違って十分ありました。ほら、もう満洲で取れる穀物やなんかが豊富にありますからね。それで100万の関東軍を維持するとなったら、その食料なんかだけど、大変膨大なもんですよ。で、ま、東京は食料不足でも、満洲は食料不足なんてことありませんよ。あの広さのところでね、穀物ができるんですから。そういうことです。
ですからね、山下奉文がシンガポールで米軍(註:正しくはイギリス軍)をやっつけてね、ほいでどうしたかっていうと、戦争をしますと、やはり兵隊が少なくなる、くたびれる。ですから、山下奉文の軍は、それが終わったらどこきたかと思うと、満洲来たんですよ。満洲で何か月間休ませて、そして減った兵隊を補充し、武器やなんかもなくなった分を補充し、ほいで、どこ行きました。フィリピンへ出て行ったでしょ。ね。(註;山下奉文がマレー作戦の第25軍司令官から、満洲の第1方面軍司令官に異動し、さらにフィリピンの第14方面軍司令官へ異動したことを指していると思われる)そのように、満洲っていうところは、支那とか南方で戦争して、くたびれたり傷ついたりした部隊を一時休ませるとこだったんです。そうして、そこで休ませて、減った人員を補充して、ほんでまた立派な部隊に直して、それでまた南方へ出した。そういう、だから南方で戦い、「支那」中国で戦って満州へ来て、ここで休ませて補充してまた南方へ出すと、そういう役目を持ってたのが満洲なんです。わかります?
それで、先ほど言ったように、農民たちが、日本の農民が全部退去して、開拓団として、満州へ移住させましたよ。これは何十万人もいるわけですから、それを守る役目もやはり関東軍が、軍隊がいるから安心してみんな百姓やってたわけです。 そういう特殊な、日本じゃないけれども、満州という1つの国、ま、傀儡国ですよね、言わせれば。だから、外国はみんな認めてませんよ、満洲国なんてものは。ただ、日本が勝手に作っちゃってやってるわけですから。そういうとこのハルピンなり寧安の仕事はそういうものです。(関東軍の任務は)在留邦人の保護を目的としてますね。それと、兵站基地だった、補給基地だった。そういうのが満洲のあれ(仕事)です。
ソ連侵攻後の満洲
聞き手:終戦の時、寧安にいかれたんですね。
そうです。
聞き手:当然、国境を越境してきたんですよね、ロシア兵が。その時のとこのお話を
はい。そのね、もう我々はそこでやったら、要するに開戦、要するにソ連が侵攻してきたというんで、すぐ満州の関東軍の、我々の部隊の直属上司である新京に総司令部があって、そっからみんな各部隊に電報が来て、命令が来るわけです。その時に、「996部隊は直ちに奉天に引き上げろ。」っていうこと、こう下りてこいってことです。要するに、国境地帯で、こっから(満ソ国境地帯)みんな入ってきたんでしょ。戦えっていうんじゃないんですよね。そこ(国境近辺)で阻止して、その在留お百姓さんたちを守るっていうことではなくて。ね、本来なら守るべきですよ。それが、大本の総司令部から来た命令は直ちに、要するにね、相手がこう戦争して、日本こう戦争でしょ(国境から侵攻してきたソ連軍と、ソ連軍に向かって行き防衛する関東軍)、ここ(国境近辺)で食い止めて死守しろというんじゃなくて、この日本の防衛線を海に近い方まで下げて、ここ(国境近辺)で陣地を構築して迎え打つというようなことから、要するにここの線(国境近辺の防衛線)をここ(奉天近辺)まで下げろっていうことなんです。だから、我々の部隊にもここ(奉天)へ戻れって。だから、この周辺地区にいるものに、みんな戻れ戻れっていう命令が来るわけ。だから、どんどこどんどこ、みんな軍隊は、周辺地区にいた軍隊は全部こっち(奉天に)来た。関東軍も100万ってもね、真ん中あたりの大都会の人間はあまりいませんよ。こんなとこいたって、百姓は全部国境地帯だとか遠く離れたところで、みんな農村でいるんですよ。だから、そこを守るためには、やはり日本の関東軍も大体そういうとこへ展開してるわけですよね。それがだっと命令で、下がってこいったわけだ。そしたら、なんとね、その命令をよこした総司令部はどこ行っちゃったかってのはね、朝鮮に逃げてっちゃった。だから、満洲からね、自分たちだけが朝鮮の方行っちゃっててね、そっから、だから我々、新京に戻ってきた時に総司令部なんかいないんですよ。
だから、我々腹立ちましたけどね。ちょうどそこに戻ってきた時にはもう終戦だったですよ。ですから、その軍司令部やなんかにいた家族やなんかいの一番に汽車だとか、飛行機に乗ってみんな帰っちゃった。 だから、今問題になってる、もうさっきもお話した残留孤児ね、残留孤児なんてのはできるのは当たり前ですよ。だから、我々はそういう人たちの悲惨さっていうのを目の当たりに見てきました。我々は軍隊ですからね、ある程度戻ってくるのに歩かなくてもいいように列車を確保し、ほいでどんどん、どんどん下がってくるでしょ。一般の農民たちは乗る貨車がないじゃないですか。だから、無蓋車、要するに石炭やなんかを積む、そういったとこに、我がちに(我さきに)みんな乗る。だけど、いつ動くかわからない、我々軍隊だとすぐ出発させろとかって言っても。だから、そういう人たちは本当にね、惨めだったです。
あなたがたが、NHKの「大地の子」というテレビドラマ(1995年11月11日~12月23日放送。中国残留孤児を取り上げている。)をご覧になったかどうかは知らないけれども、あれの第1回目に出てるように、悲惨なもんですよ。今まで大威張りできたのが一旦負けたとなると、周りは全部敵国人ですよ、ね。もっとも満洲ですよ。ですから、この広大なとこで守ってくれる関東軍がいなくなって、どうして何十万人の開拓民が、逃げてこられます?想像を絶する悲惨さですよ。だから、可愛い子供を、親しい、ね、満洲の農民の人に預けるとか、そうせざるを得ないでしょう?産めよ増やせの時代だから、みんな、4人も5人も乳飲み子を抱えた人がどうやって歩いたりなんかして国境から逃げてこられます?我々も助けてやりたいんだけど、それもやってられない。悲惨だったですよ、満洲は。そういう状態にしたのは果たして誰かって言って辿っていけばね、やはり軍部の上の人、政治家、そういう人たちに不満をぶつける以外ないでしょう。満州の生活ってのはそういうとこです。996部隊の時も、戦争がはじまって、ソ連が攻めてくる前までは平和な地元農民だとか満洲の農民とか開拓民の人とか、みんな仲良くやってたんですよ。だから何も争い事は起こらないでやってた。だからね、もう収穫時期になり青々として高粱はある、何でもある、そういう平和な時代だったですよ。だけど、一旦そうなった時(ソ連が攻めてきた時)にはもう全部天地がひっくり返ったんだって。そういうことです。満洲の我々が経験したのは。
だから、ソ連が攻めてからはね、地獄だったんです。地獄の逃避行ですね。ひどいもんですよ。満洲のね、新京の駅でね、線路のとこにね、日本のお金が山のように捨てられてるわけ、満州国の発行した紙幣が。前の日まで、それでいろんなものが買えたりなんかしてた、流通してたお札が、8月15日で紙切れになって、いくらもう、何十万円も何百万円ものお札がね、捨てられてても、拾う人1人もいない。だって満洲の人だって、それ拾ったって何も買えないんだから。そんなもんですよ。昨日まで、この1枚100円札があればなんでも買えて、というお札が、一朝にして紙屑になった。戦争っておっかないものです。ほんとにね、もうお札が束になってね、線路に積んである。誰も拾おうとしない。
ほらもうね、外国行って敗戦国になって、周りが全部で敵国だとなれば、どうなります?満洲には満鉄って言って、日本の国が作った鉄道があって、ね。だからこれ勤めている日本の家族ってのは、いっぱいいたの。満鉄の従業員。この人たちはね、私たち、武装解除を受けた時にね、新京の町で我々がグッと収容所まで行くときに、女の人は全部もう丸坊主だったですよ。総じてです、化粧じゃなく、もうね、炭塗る。(顔に塗る動作)女と見れば全部、ソ連兵に凌辱されるから。それで、その人たちが言いました。兵隊さん、もう私たちの仲間になんなさい。なぜか。もうね、日本へ帰す帰すと言ってもね、嘘であなた方は全部シベリアに連れて行かれますから。だけど、我々はもう組織で動いてますからね。ソ連の将校が来て、武装解除をした後は直ちに日本へ帰すからって言われりゃ、そうせざるを得ないんですよ。みんな若い部下たちを持ってますから。自分1人なら逃げられても、そういうことで皆シベリアへ連れて行かれちゃった。ほら。だから現地の人も非常に大変だったと思いますね。そういうことが満洲から引き揚げた人じゃなければ、内地で苦労した方でもわからないと思いますね。何か他に質問ありますか。
武装解除からシベリアに行くまで
聞き手:武装解除の時、前っていうのは戦闘全くなし?ロシア軍との接触っていうのはもう全くもう砲火を交えないで、そのまま武装解除?
そうそう、要するにね、もう最初はだっーともう、ソ連がもう全満の間のとこから日本の内地満洲にがっと入ってきたでしょ。ですからね、全部命令が、天皇の玉音放送だなんてね、聞こえるところもあれば聞こえないとこもあるわけですよ。ですから、満洲でも、ちゃんとしたところは天皇の玉音放送が聞こえたっていうところもあれば、そうじゃないとこもありますけれども。だから、我々、1番最初に知ったのはね、新京の駅へ着いたら、もう地元の「満人」たちは、日本は負けたんだ、日本は負けたんだって、こう大声で言ってんでしょ。それでわかったようなもんですよ。別に上層部の軍隊、あのね、司令部から、日本は負けたからどうしろこうしろ、そんなんじゃない。もう現地で、要するに中国人が日本はもう負けたよと言ってんだから。それでああ日本は負けたなと。
それで、ずっと最初の時ですからね、もう命令系統も何もないから、そりゃ混乱して、略奪だとかなんかいろんなことありましたよ。だけども、それでしばらく、2、3日経った後、向こうもちゃんと武器引き渡しだとかいろんな、ね、交渉になって、どこどこへ集まれっていうんで、私たちはずっと安東(あんとう、北朝鮮との国境付近。現在の吉林省南端)と言って、ちょうど地図で見れば新義州(現在の北朝鮮側の中国との国境付近)、昔、橋一つ渡ったら昔の日本(註:かつて朝鮮半島は日本領だったため)ですよ。いまの北朝鮮。鴨緑江ってのがある。鴨緑江っていう川が流れて、その向かいが新義州の安東っていうとこね。新義州っていうのは朝鮮の方の名前。こっち側のは中国側が安東って、この橋渡っちゃえばね、当時で言えば日本なんですよ。
よっぽどこの強硬に渡ってね、釜山まで戻っちゃえば日本へ、さっとシベリアの方にならず(行かず)、帰れたんです。だけどね、1500人のやはり1つの部隊を率いてったら、自分個人の意思じゃどうにもなりませんよ。やはりそういった部下を掌握して、戦争が終わったんだから、なんとしても日本へ返さなきゃならんわけですよ。ですから、要するに我々は、ソ連との、日本の上の方との交渉で、武器を引き渡すというようなことで、全部武器をそこで渡したわけです。
そして、今度はまた元へ、新京へ戻れ、奉天に戻れっていうことで、またとことこととことこ戻ってきて、収容所入って、そこで編成されて貨車に乗せられて、また国境を渡って、さっき言ったブリヤートモンゴル州へ連れて行かれた、そういうことなんです。(しばし沈黙)
収容所に入るまで
ですから、毎日毎日が大変でしたよ。(しばし沈黙)そういう立場に皆さんが立ってみたら本当にわかると思う。なかなか、しかし、ただ聞いただけじゃわからないと思うけれど、地図をご覧になって、中国の広大、広大なね、ああいった地図を、要するに極東の世界地図を広げてみて、そこにポツンと2つのところへ集められて、時の、ね、いかに人間の弱さっていうか、恐れっていうか、恐怖心というか、そういったものは、その場に立ってみなきゃわからない。いくら言っても。
ほいでシベリアに連れてかれた時に、これからどうなるんだろうと。あの広大なあれ(大地)でしょ、ね?こうね、連れてかれてね、降ろされたとこ。シベリアテントなんて、駅なんたって何もないですよ。プラットホームも何もないんだから、こう貨車で連れてかれて、はい止まって降りろ。ここでみんなバラバラ、バラバラバラ降りる。そいで、列を作れったらね、日本なら2列か4列ですよ。ほんで、番号言えばさあっーてすぐにわかる。向こうはなんとね、10列に並べさせるわけ。10列縦隊。これはね、向こうの兵隊、計算ができないんですよ。10列だと1、2、3、4、5ですぐわかるわけだ。5で50人でしょ。だからね、シベリアで我々が並ばされるのは、いつでももう10列。必ず1番先頭に10人並ばされて、そっから後ろずっとーとみんな並ぶわけ。それで列を数えてくわけ、ね。できるのは広大なシベリアだから、狭い土地だったらそんなことできるわけないでしょう。シベリアだから全部10列縦隊でも十分な、それで行進するんだって。そのまま行進ですよ。10列のなった、こう、10人いて、だっと並んでる。その1500人がこうやって(列をなして)歩いてくる、ね。
それで、我々の時なんか、夜になると止まれ、そこで寝よう。シベリアのもう雪の積もってる荒野ですよ。だってどこまで宿泊設備がないんだから。だから起きた時に、翌日起きた時に立ち上がってこない兵隊もいるわけですよ、ね。それが死んでた。凍死したり、要するに心臓麻痺起こしたり、いろんな病気抱えてる。ほんで、また行く。それで、宿営地に着くまでに大変だ。
で、我々が行ったとこはね、刑務所だった。それまではソ連の囚人たちが入った刑務所が、わたしたち、我々を入れるために全員出させて、それで我々はそこに入れられたわけ。1500人が入るとね、1番先に作らなきゃならんのはトイレなんですよ。1500人のトイレっていったら大変ですよ。ですから、昔の向こうのトイレはうまくできたもんで、広いですからね、ダーっとに1メートル、2メートルぐらいの幅のね、たっーて、みんな穴掘りをして、大体2メートルぐらいまで深く掘って、ただ板渡すだけですね。で、板渡して、トイレになる。それをまず1番先に作らされましたけどね。
それで、次にやられたのは、なんて言いますか、この(腋を指して)要するに発疹チフスを1番恐れましたからね。すぐ、毛を剃るために、入浴場ってのは要するにサウナですよ、向こうのあれはね。だから、サウナにみんな入れられて、だから服脱ぐ、サウナ入る。最後出る時に毛(腋をさして)を剃ったのを確認して、剃ってないと服くれないんです。いやでも応でも皆剃る。それで出て、収容所入れられて、そういうなとこだったんですよ。大変だったです。何かありますか。
収容所の中で(配給や生活について)
聞き手:先ほど劇で、劇で、パンというか、配給の配分、あれは誰かまとまった単位で支給されて
そうそう、要するにね、これぐらいの長さの黒パンを何人かにやってポンと、何人分としてくるわけです。それを分配、こう、食事当番が10人なら、10人で10等分して切るわけです。最初はね、なんでもなくね、パンパン、パン、パンパン、10人切って、ぱっと分けた。そのうちにね、異議を申し立てるもんが出たわけ。なんだと思います?両脇を欲しいんですよ。歯ごたえがあるし、真ん中よりも。え、わかります、この気持ち?ほんとにね、命を繋ぐパンなんですよ。だから、目の色が変わる。ね。おやつじゃないんだ。だから、このパンでもね、端っこと真ん中とでは違うんですよ。だからって端っこの方くれっていうのは多い。ですから。しまいに私なんか考えたのは、番号をつけて、1、2、3と分けて1番目、最初はこれもらえると。だけど、いつの間にか順番毎日ずらせますからね、必ず自分また、なるんですよ。まそういう風にしました、ね。その番を、今、先ほど言ったように、ノルマによって分配をしろということになると、この分け方が大変だということ、ね。それで、両脇もあるでしょ。だから、私がやりましたのは、両脇をまずカットしちゃう。このね。そうするともう同じもんでしょ。それをこう等分して、それで今度の両端の残った耳で、耳をまた10等分して、みんなのパンの上に乗せる。そうすると、みんな固いとこももらえる。とね。それでみんな分けてました。
それがもう半年ぐらい経つとノルマ制度が確立して、ノルマによって食え、要するに、階級はないんだから、一等兵であろうとね、上等兵であろうと、階級はなくなったんだからって何でも言うわけですと、やはりね、階級がなくなっちゃうとね、やーさん(註:やくざ)育ち、出身の兵隊もいるわけですよ。1番のさばるのは、やはりやーさん育ちね。やはり暴力で訴える、そういうので中だけでも大変でしたよ。
密告制があってね、誰々は憲兵だったとか、あれは申告の時に上等兵って言ったけど、本当は下士官なんだとか、要するにね、向こうの言いなりで、密告すれば早く帰してやるとかね、なかなか大変だったんです。ですからね、捕虜になった時に、憲兵だとか、そういった警察官だとか、そういうような人はね、みんな身分も偽りましたよ。1番向こうから狙われるのは、憲兵だとか、警察官だとか、ロシア語を話せるものとか、こういうの、いの一番でスパイ扱いされますからね。そういうことでね、随分身分を変え、笑い話はね、東条だとかね、そういう名の知れた名字の兵隊もいるわけですよ。東条って名前であるばっかりにダモイ、要するに、帰してくれるのをカットされたってのはいくらでもあるんです。だから、自分の身分を偽ると、こういうことがありましたね。
私なんかあれでしょ、満洲であれ、国、今こうやって元気でやってるよって言ってから終戦、戦争始まって、だから帰ってきてから聞いたけど、もう音信不通ですよね。何にも。私から便りもなければ、どうなったか、死んだか生きたかわからないのは3年以上続いたんです。なぜわかったかというと、ソ連に捕虜になってから3年目ぐらいに、向こうのソ連から往復はがきを持ってきたの、ソ連製の。それで、ハラショーラボータは、ハラショー(хорошо)ってのはいいって意味で、ラボータ(работа)は労働者、ハラショーラボータにはこのハガキをやるから、日本の国へのお父さんやお母さんに手紙を書けっていうことでね。そんなものまでノルマ達成のいいものとかって区別されてくじゃん。ほんで、将校にはくれましたから、私は、それ書いたって、東京の自宅はもうね、焼けちゃって、ないんだろうと思ったから、私は田舎の親類に手紙を出しましたよ。それ、往復はがき。これからね、半年たってもなしのつぶて。あなんだ、またごまかされてね、書かされたけれども、これはまた何時のこったら、半年過ぎて10か月ぐらい経ったら日本から返事が来ましたよ、往復のハガキの半っぴれが。ほいで、もちろん親戚に出しましたがね、福井の親戚。福井の親戚が、あー、やっと繁さん(稲村さん)がシベリアにいるってことが分かったと言うんで、東京の疎開先の私の両親に手紙を届けてくれ、それで初めて両親は、あ、息子は生きてたんだなと、しかしそれがシベリアのどっかにいるんだなってことだけがわかったんだね。
そんなもんだったですよ。だいぶ時間かかりましたけど、なにか他に。だから、先ほどの質問ね、パンがそういう、うん(うなずき)。
聞き手:冬でも労働、もちろん作業は、真冬でも作業はありました?
これはね、零下30度を超えると待機、ね。零下31度になるとね、作業に行かないで営内で待ってます。だけど、営内待ってても、30度が零下25度になったっていうと、出てって、8時、6時。8時から6時までね。
死をめぐって(自殺、逃亡、埋葬)
聞き手:先ほどこう、自殺をしてしまう兵隊の、自殺をしてしまう兵隊の方もいたと。
うん。これはね、要するに、もう精神、自由はないでしょ。要するに毎日の労働は厳しいでしょ。やはり精神的に弱いものはね、要するに耐えられなくなって自殺するんですよ。逃げていけば鉄砲で撃たれることを分かってて逃亡するんですよ。
聞き手:逃亡しようとした人というのは、結構そうやって逃げようとした人は割と数はいるんですか?
ほんとたくさんはいませんよ。だって逃げられないもの。鉄条網も収容所の周りに、みんな向こうの兵隊もいるし、犬もいるしね。高い望楼から見てるし。まず、大体最初に言われた時にね、逃げたいと思っても逃げんなら、インドの方に行くにはヒマラヤ山脈を超えなきゃインドに行けませんよと。こっちの方はね、興安嶺というのは高い寒い山を越えなきゃいけませんと、こっちにはゴビ砂漠がありますよと。だから今ここにいるのが1番安全なんだと。だから逃げようっていう気はないね。ただ、もう自殺者ってのはそういう風に、精神的に弱い。そういうもんだよね。
(しばし沈黙。)
ただね、私もこうやっていつも言うんだけど、当時、60、70年ぐらい前の現状において、自分の胸にふつふつと沸いてきた怒り、怖さ、恐怖、死に対する恐怖、そういった感情が今、同じ感情にはなれないということ。だから、私の感情も風化しつつある。そうでしょ、その当時のね、現状に部下の凍死死体やなんかを見た時の憤りが、そのことを今話して、同じ憤りではないということ。だから、だから、戦争、そういったことに対する怒りも、なんかぬるま湯、時代の流れの中に薄められていくんじゃないかと。それが1番ね。心残りですね。ほら、同じ心情にはなれませんよ。
ほんとにね、部下が毎日ね、死んでるの見たらね、いたたまれないですよ。それで、これまた埋めるのに3日もかかんですから、もう凍土でしょ、ね。ほんと、体の病気のものを作業に出さないで、休ませたものを呼んできて、「お前、このあれ(遺体)を埋める、埋めなくちゃなんないんだから、穴掘れ」と言ってやったって何もないし、凍土ですからね。焚き火をして温める。ほんで、しばらくして焚き火であったまると溶ける。それをまたスコップでこう掻き出す。それで、その後にまた焚き火をする。で、だんだん、だんだん掘ってって、ね、ある程度の大きさになってから初めて埋める。だから、1人埋めるのに3日ぐらいかかったこともあるんですよ。冬場は。最初が冬場だったでしょ。だから、なかなか大変だったんですよ。ただ、いいことには、凍らないですからね。腐らないんだから。
で、最初はね、素っ裸にしろって言うんですよ。死んだものに服は必要ないって、ね。全部もうパンツから何から、もう素っ裸にしようってんですよ。いくらなんでもそれはできないから、要するに下のね、あれ(下着、ふんどし)だけは履かしてくれっていうことでしましたけどね。そんなもんですよ。(しばし沈黙)
ですから、遺骨収集だなんだってね。ほら、今、随分日本からも行きましたけれども、まだまだわからないで、だって、何も墓石が立ってるわけじゃないですからね。大体この辺に埋めたはずだなんだって、60年も経っちゃ、どうなってるかわかりませんよ。
シベリア抑留の記憶の継承について
それで、今、靖国神社の問題も、今出て話しますけど、靖国神社っていうのは戦死した兵隊が祀られる、ね。シベリアで死んだ兵隊は戦死じゃないんですよ、戦争は終わってからだし。だから、シベリアで死んだ兵隊は靖国神社に祀られてないんですよ。そう言ってて、こんな戦争を起こした、私利私欲で起こしたんじゃないっていうA級戦犯の人が祀られてるというこの矛盾。私、なんかやはりおかしいんじゃないかと思うんですよ。それじゃシベリアで死んだ5万や10万の兵隊は靖国神社にね、祀られる資格はないのかと。戦死じゃないんだ。そういういろんな問題を含んでんですよ。
それでね、1番腹立たしいのは、原爆の日だとかそういう日は必ず、毎年毎年繰り返し繰り返して来て、新聞、テレビでもやって、こう(取り上げたり、大規模な追悼式典を)やるでしょ。シベリアのなんとかの記念日なんてないじゃないですか、え?(沈黙)あなた方考えてもどう思う?原爆の日だとかいろんなことがあって、その時には全国的に、ね、いろんな催しができて、記憶にとどめようとして、いろんな原爆からの。なんかシベリア捕虜の問題について、この新宿にありますよ、平和なんとかっていう財団(註:当時、平和祈念展示資料館を管理していた平和祈念事業特別基金、もしくは平和祈念展示資料館そのもの)をね、あそこに行くと、確かに収容所の中のね、もう人形やなんか飾ってあります。あそこだけでしょ。あとは舞鶴に引き揚げ者の記念碑がある。舞鶴には何らかのいろんな、その時に置いてった品、記念品や、ね、いろんなあれがあって、展示されて、そんなもんじゃないですか。え。だから、あんまり新聞や、テレビが取り上げない。
私はね、相模原に住んでるから、相模原の学校なんか行くと、必ず言うのは60万、今、相模原市の人口は62万人なんです。「君たち相模原の、人口は62万人だけど、この62万人、赤ちゃんからおじいさんまで全部今のいる場所から、汽車に乗せられて、よそのシベリアならシベリアに連れてかれて、何年もいろんな仕事をさせられたとしたら、どうだ?そういうことが現実にあったんだよ。」と行って言うんですよ。その60万人という人数の多さってものは、相模原市の人全部まだよ(?)と、それと同じなんだっていうことを言うんですよね。
いろんなことを、あれ、脈絡なく話したかもしれないけれども、その時その時の雰囲気、または聞く人の年齢、そういうことによって全部私の話内容は違います。だから、女子大なんかにいれば、当時の女の人はどうだったんだということを話するわけです。
聞き手:それは満洲?それは満洲で、その当時の人っていうのは、
うん、だから、その女子大生なんか、いや、当時の日本の女子大生だとかが、女の学生あたりはどうだったと。私の家内も女子美(当時は女子美術専門学校)の生徒だったんですけど、聞けば、やはりほとんど学校には行かないで、飛行機の部品、工場へ、直接行って、1週間に1回女子美部の授業があったかなかったか。随分軍需工場から爆撃も受けて、同級生が何人も死んだと。そういうことですね。だから、女の人だって言っても決して戦争から逃げられないと。で、よく言うんですよ。先ほども言ったように、戦争が始まったらなんでも国はやるんだということで、当時の女の人には、なるだけ早く結婚してくれ、そうして子供は5人産んでくれということを女の人には国が言ったんですよ、子供5人は産んでくれって。
だからね、平和だ、平和だっていうのをね、色んなことに話は行っちゃったけれども、そういうことをね、その場その場の雰囲気、その場その場のやり取りの間に話がある。やはり私も80何年生きてきて、いろんな経験してるからね。あ、これはこの話にした方がいいな、これはこの話にした方がいいなという、いろんな経験が持ってるから、それは言える。どうにでも対応できる。そういうことです。話しちゃった。
聞き手:ほかなにかあれば。
いや、こういうことだから、聞きたいことがあればいくらでもですね。。
侵攻時の戦争体験(ソ連軍との遭遇)
聞き手:満洲ですよね。満洲では戦争体験、敵と遭遇したことがありました?
満洲での戦争?ソ連が侵攻するまではなんでもなかったけど、もう、その、もうね、我々も、寧安っていうとこは国境から近いですけど、そこでやったでしょ。ほんで、引き揚げろっていうことをして、こうずっと、ね、飛行機に乗ってパッと帰っちゃうわけじゃなく、駅へ出て、要するに千何百人の兵隊を全部、持ち物も出して駅へ行く。駅だって、もうしょっちゅう、今の日本みたいにね、5分おきに来るわけじゃないんだから。1時間、1時間、1日に5本、5本か6本しか通ってないのにです、ね、そっち、それに乗っていかなきゃなんないでしょ。だからこう行く。それでこう、そこ行く。その時、ソ連がどんどん入ってくる
ね。だから私なんかね、向こうの30トンの戦車がずっとそばまで来て。私たちさ、歩兵部隊だとかそういう部隊じゃないから、敵の軍隊と直接前線でぶつかるための軍隊じゃないわけだ。航空通信だから、通信が主な仕事だから、機関銃だとか鉄砲ってのはあまりない部隊、連隊なのよ、要するに。だから、戦車を撃つ大砲もなければ、そういうの何もないわけ。それで、持ってくのは通信機。トンツートンツーできる通信機だとかね、暗号書だとか、そういうものを持っていくわけでしょ。そこで戦車がこう来るんだから。いや、だからね、300メートルぐらいのところまで敵の、あ、戦車が来た時に、もうダメだと思いましたよ。だってこっち戦車やっつける大砲も何もないんだから、ね。だけどもね、ソ連軍も日本の軍隊は強い。特に関東軍はね、もう日本の1番の精鋭部隊だということは全世界が知ってたから。向こうだって知らない土地へ無造作にだだだっと来て、どこで爆弾が埋めてあるか、ね、地雷が埋めてあるかもわかんないでしょ。だから向こうも来るは来たけれども、しゃにむにこう(手でグワーっと仕草をする)は来ないわけよ。
だから、だっーて来て、私たちのあれ行ってると思った300メートルぐらいのところへだっーと戦車が出て、あーもうここで一戦交えてダメかなと思ったらね、くるっと回って戦車がいなくなっちゃう。だから、それと、直接はなかったけども、その途中では空爆を受けましたよ、バンバンと。だから、随分空襲は受けましたよ。ほら、どうしても向こうが狙うとすれば鉄道狙うでしょ。ダーッ(手で空襲のそぶりをする)。だから、満洲の戦闘ってのは、たったわずか5日かそれぐらいでしょ。ね。だから、実際のね、本当にドンパチは、パーンてやったら、本当に、黒竜江っていう川を挟んでいた部隊がね、否が応でもでも、そこでドンパチやるぐらいなもんで、そうじゃないところはそう日露戦あれ、シベリアの満洲で向こうと戦ってるってことはない。それと、日本の、終戦後でもあったっていうのは、日本が負けたからっていうことが前線の部隊に伝わらないっていうことはいくらでもあったわけよ。戦争は終わったんだけど、まだ終わったと思わない軍隊はやはり戦うもんね。そういうような局部(局地)戦はあった。そういうことです。だから満洲で大激戦っていうのはないの。
長引いちゃいますけど、こんなもんで。
参考資料
- 地図 ───
- 年表 ───
戦場体験放映保存の会 事務局
■お問い合わせはこちらへ
email: senjyou@notnet.jp
tel: 03-3916-2664(火・木・土・日曜・祝日)
■アクセス